|
別添1
危険物事故防止に関する基本方針
平成15年5月27日
危険物等事故防止対策情報連絡会
| 1 |
趣旨
昭和50年代中ごろから概ね緩やかな減少傾向を示していた危険物施設の火災・漏えい事故は、平成6年頃を境に増加傾向に転じ、平成12年中に発生した火災・漏えい事故件数が統計を取りはじめて以来最多となる511件を記録するなど、過去最悪の水準を推移している。
近年における事故増加の要因については、様々な角度から調査分析を進めているところであるが、全体に占める割合及び増加傾向の大きい要因として、火災に関しては一般取扱所、製造所、給油取扱所等における管理不十分・確認不十分等の人的要因、漏えいに関しては給油取扱所、地下タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、一般取扱所等における人的要因や危険物施設の老朽化等に伴う腐食・劣化をあげることができ、事故防止を図るうえでの重要課題と考えられる。また、科学の進展等に伴い数多くの物質が新たに開発・生産されており、危険物と同様の性状を有していながらその潜在的危険性が認識されていない新規危険性物質の出現が懸念されるところであり、これらによる事故を未然に防止する必要がある。
一方、危険物施設の位置、構造及び設備並びに貯蔵・取扱いの形態は個々に異なることから、とりわけ人的要因に係わる事故防止を図るためには当該施設の実情に即した対策を講じることが必要となる。その前提として、過去の危険物事故等を教訓とし、的確に当該施設の危険要因を抽出しておくことが必要であり、危険物事故や事故防止に関する情報を広く収集・分析して関係者の間で共有することが必要である。
以上のような状況を踏まえ、危険物関係業界・団体、研究機関、消防関係行政機関等の連携・協力の下、共通の認識・目標に基づき、官民一体となって総合的な事故防止対策を強力に推進していくため、「危険物等事故防止対策情報連絡会」(以下「連絡会」という。)において、官民共同の行動指針として「危険物事故防止に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
|
| 2 |
目標
危険物施設の火災・漏えい事故の大幅な低減を目標とする。当面の目標としては、危険物施設における事故が増加傾向に転じた平成6年頃のレベル以下に、事故の件数及び被害を低減することを目指す。
(参考)平成6年中の火災・漏えい事故件数:287件→平成12年中:511件、平成13年中:503件(震災による件数を除く。)
|
| 3 |
推進方策
上記の目標を達成するため、次に掲げる項目を中心に、総合的な事故防止対策の推進を図る。
| (1) |
危険物事故に関する調査分析及び事故情報の共有化の推進 |
| (2) |
危険物事故防止及び危険物災害に対応する消防活動支援に関する情報整備 |
| (3) |
新規危険性物質に関する情報の把握及び安全対策の推進 |
| (4) |
新技術・新素材の活用、危険物施設の老朽化対策など事故防止技術の研究開発及び普及の推進 |
| (5) |
危険物保安エキスパートの育成及び資質の向上 |
| (6) |
危険物保安に関する基準遵守及びその履行状況を担保するための客観性・透明性の確保 |
| (7) |
危険物保安に関する安全意識の高揚 |
|
| 4 |
推進体制等
| (1) |
官民一体となって危険物事故防止を推進するため、危険物関係業界・団体、研究機関、消防関係行政機関等(以下「関係機関」という。)が参画する連絡会において、基本方針に基づく全体的な行動計画として、年度ごとに「危険物事故防止アクションプラン」(以下「アクションプラン」という。)をとりまとめる。アクションプランにおいては、事故の発生状況や危険物施設の設置・維持の現況等から事故防止上特に重要と考えられる事項を「危険物事故防止に関する重点項目」として抽出するとともに、危険物保安に携わる「推進主体別の主な実施事項」をとりまとめる。 |
| (2) |
各関係機関においては、基本方針及び当該年度のアクションプランに基づき、それぞれ果たすべき役割や事故の発生状況等を勘案して、当該分野の年度計画、目標等を設定し、個々の事業所、関係諸所等(以下「個別事業所等」という。)に対して周知徹底を図る。また、必要に応じ関係機関等の間で積極的に連携を図り、相互に協力して効果的・効率的に事故防止を図る。 |
| (3) |
個別事業所等及び各関係機関においては、当該分野の年度計画、目標等を踏まえつつ、事故防止対策を自主的・積極的に実施する。 |
| (4) |
各関係機関においては、年度ごとの実施結果(当該機関の実施事項のほか、必要に応じ個別事業所等の実施事項)についてとりまとめを行い、連絡会へ報告する。 |
| (5) |
個別事業所等及び各関係機関においては、それぞれの実施結果等を踏まえ、必要に応じ自主的に改善を図る。 |
| (6) |
連絡会においては、これらの結果等に基づき危険物事故防止に関する全体的な検討を行い、次年度のアクションプラン等に反映する。 |
| (7) |
基本方針、アクションプラン及び年度ごとの全体的な実施結果については、各関係機関において幅広く周知を図る。 |
|
〈基本方針に基づく危険物事故防止の推進イメージ〉
|
| 危険物関係業界・団体、研究機関、消防関係行政機関等の連携・協力の下、共通の認識・目標に基づき、官民一体となって総合的な事故防止対策を強力に推進 |
| 〈主な推進方策〉 |
| (1) |
危険物事故に関する調査分析及び事故情報の共有化の推進 |
| (2) |
危険物事故防止及び危険物災害に対応する消防活動支援に関する情報整備 |
| (3) |
新規危険性物質に関する情報の把握及び安全対策の推進 |
| (4) |
新技術・新素材の活用、危険物施設の老朽化対策など事故防止技術の研究開発及び普及の推進
|
| (5) |
危険物保安エキスパートの育成及び資質の向上 |
| (6) |
危険物保安に関する基準遵守及びその履行状況に関する客観性・透明性の確保 |
| (7) |
危険物保安に関する安全意識の高揚 |
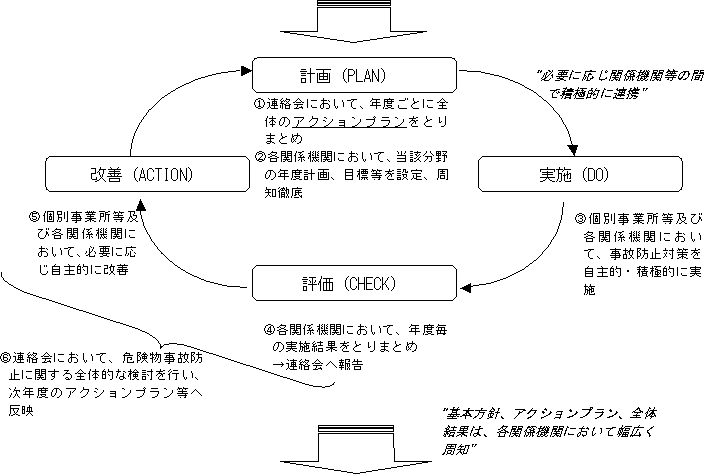
| ○ |
危険物施設の火災・漏えい事故を大幅に低減 |
| ○ |
当面の目標として、危険物施設における事故が増加傾向に転じた平成6年頃のレベル以下に、事故の件数及び被害を低減 |
|
(参考)平成6年中の火災・漏えい事故件数:287件
→平成12年中:511件、平成13年中:503件(震災による件数を除く。)
|
|
|
|