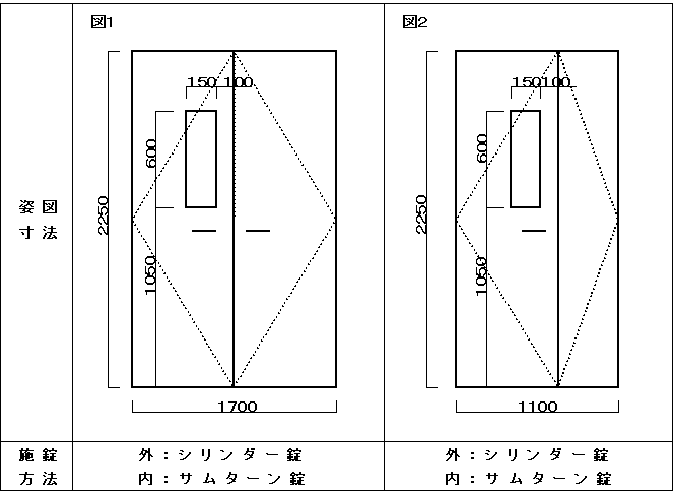|
消防予第281号
平成14年9月30日
各都道府県消防主管部長 殿
消防庁予防課長         
消防用設備等に係る執務資料の送付について
標記の件について、別紙のとおり質疑応答をとりまとめたので、執務上の参考とされるとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知方お願いします。
別紙
第1 消防用設備等の点検要領の改正
(点検要領の取扱いについて)
| 問1 |
「消防用設備等の点検要領の全部改正について」(平成14年6月11日消防予第172号。以下「点検要領」という。)別添の屋内消火栓設備の機器点検「ホースの耐圧性能」欄中「ホースの端末部に充水し、耐圧試験機等により所定の水圧を5分かけて確認する。」とあるが、耐圧試験機以外の方法は認められるか。
また、認められる場合は具体的にどのような方法が考えられるか。 |
|
| ( |
答) |
| 前段 |
お見込みのとおり。 |
| 後段 |
ホースクランプ等を用いてホースの端末部付近の部分を閉鎖し、手押しポンプ、動力消防ポンプ等で加圧して確認する方法が考えられる。 |
|
(不活性ガス消火設備の総合点検について)
| 問2 |
点検要領別添の不活性ガス消火設備の総合点検において、試験用ガスは窒素ガス又は空気とされたが、二酸化炭素消火設備の総合点検において、試験用ガスとして窒素ガスを用いる場合は、二酸化炭素消火設備の設計圧力の上限を超えない範囲に圧力を調整して実施すべきか。 |
|
|
(連結送水管の設計送水圧力の取扱いについて)
| 問3 |
点検要領別添の連結送水管の機器点検「配管の耐圧性能」欄中「締切静水圧は、設計送水圧力(加圧送水装置を設けた場合は、締切圧力)とする。」とあるが、平成2年12月1日以前の連結送水管の設計送水圧力は法令上定めがないが、水圧はどの値とすべきか。 |
|
| ( |
答)
消防法第17条の3の2に規定する検査の際に用いた送水圧力とする。 |
|
(連結送水管の配管の耐圧性能試験について)
| 問4 |
点検要領別添の連結送水管の機器点検「配管の耐圧性能」欄中「屋内消火栓設備と当該配管を共用している部分を除く。」とあるが、連結送水管の送水口から送水口直近の逆止弁までの間の配管については、配管の耐圧性能を確認しなければならないということか。 |
|
|
(遠隔試験機能付きの自動火災報知設備又は自動試験機能付きの自動火災報知設備の点検について)
| 問5 |
消防法施行令(以下「令」という。)第21条第1項に基づき自動火災報知設備の設置が義務付けられる共同住宅等であって、「共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例について」(平成7年10月5日消防予第220号)を適用しない場合の住戸等内の自動火災報知設備の機器の外観上の点検項目については、住戸等の外部から感知器に係る機能の点検が可能な遠隔試験機能付きの自動火災報知設備又は自動試験機能付きの自動火災報知設備が設置されている場合に限り、住戸等内に立ち入って実施しなくともよいか。 |
|
(答)
外観上の点検項目、異常が発生した場合の措置等を共同住宅等の居住者に対して周知徹底しており、共同住宅等の居住者等により外観上の点検が実施されている場合にあっては、お見込みのとおり。 |
第2 非常警報設備に関する基準の改正
(放送設備の通話装置について)
| 問6 |
非常警報設備の基準(昭和48年2月10日消防庁告示第6号。以下「非常警報設備の基準」という。)第4、2(1)ロに「防災センター等と通話することができる装置(以下「通話装置」という。)を付置する場合は」とあるが、通話装置は消防法施行規則(以下「省令」という。)第25条の2第2項第2号の2に規定される起動装置若しくは起動装置の直近に設置すればよいか。 |
|
|
第3 新ガス系消火設備に関する基準の改正
(常時人がいない部分の取扱いについて)
| 問7 |
毎日定期的に点検員が点検のため入室する電気設備室、通信機械室等は、省令第19条第5項第1号に規定する「常時人がいない部分」にあたると解してよいか。 |
|
|
(自走路を有する機械式駐車場の取扱いについて)
| 問8 |
自走路を有する機械式駐車場は、省令第19条第5項第1号に規定する「常時人がいない部分」として取り扱ってよいか。 |
|
| ( |
答)
自走路部分は、原則として常時人がいない部分以外の部分に該当する。 |
|
(常時人がいない部分以外の部分への新ガス系消火設備の設置について)
| 問9 |
消防法施行規則の一部を改正する省令(平成13年3月29日総務省令第43号。以下「改正省令」という。)の施行日以前には、令第32条の規定を適用して、常時人がいない部分以外の部分にも窒素、IG-55、IG-541(以下「イナートガス消火剤」という。)及びHFC-23、HFC-227ea(以下「HFC消火剤」という。)を用いるガス系消火設備(以下「新ガス系消火設備」という。)が設置されていたが、改正省令の施行日以後も引き続き十分な検討・評価のうえ、常時人がいない部分以外の部分にも、令第32条の規定を適用し、新ガス系消火設備の設置を認めてよいか。 |
|
|
(新ガス系消火設備の設置場所の面積及び体積を制限する理由について)
| 問10 |
省令第19条第5項第2号の2及び第20条第4項第2号の2表中「防護区画の面積が千平方メートル以上又は体積が3千立方メートル以上のもの」には、新ガス系消火設備が設置できないこととされたが、その理由如何。 |
|
| ( |
答)
改正省令は、これまでに知見の十分に蓄積されたものについて本則化したものである。法令で規定されている部分以外の部分に不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備を設置しようとする場合には、消火剤の消火特性、安全性にかんがみ、当該部分の建築構造、空間の形状、人員の状況、避難経路等を踏まえ、避難安全性、消火の確実性について、個々の防火対象物の実情に応じ、十分検討・評価を行い、令第32条の運用により対応されたい。 |
|
(多量の火気を使用する部分等に対する新ガス消火設備の設置制限について)
| 問11 |
省令第19条第5項第2号の2及び第20条第4項第2号の2表中「鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分、ガスタービンを原動力とする発電機が設置されている部分又は指定可燃物を貯蔵し、若しくは取り扱う防火対象物若しくはその部分」には、新ガス系消火設備が設置できないこととされたが、その理由如何。 |
|
| ( |
答)
改正省令は、これまでに知見の十分に蓄積されたものについて本則化したものである。法令で規定されている部分以外の部分に不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備を設置しようとする場合には、消火剤の消火特性、安全性にかんがみ、当該部分の建築構造、空間の形状、人員の状況、避難経路等を踏まえ、避難安全性、消火の確実性について、個々の防火対象物の実情に応じ、十分検討・評価を行い、令第32条の運用により対応されたい。 |
|
(省令第19条第5項第16号ハの解釈について)
| 問12 |
起動装置の放出用スイッチの作動に連動して、自動閉鎖装置を設けた開口部を閉鎖し、音響警報装置により消火剤が防護区画内に放射される旨を周知した後、貯蔵容器の容器弁又は放出弁を開放することは、省令第19条第5項第16号ハに規定する「起動装置の放出用スイッチ、引き栓等の作動により直ちに貯蔵容器の容器弁又は放出弁を開放するもの」に該当するか。 |
|
| ( |
答)
必要最低限の時間であるものについては、お見込みのとおり。 |
|
(放出された消火剤及び燃焼ガスを安全な場所に排出するための措置について)
| 問13 |
省令第19条第5項第18号(省令第20条第4項を準用する場合を含む。)に規定される「放出された消火剤及び燃焼ガスを安全な場所に排出するための措置」とは具体的にどのような措置か。 |
|
| ( |
答)
新ガス系消火設備については「二酸化炭素消火設備の設置に伴う疑義について」(昭和51年11月29日消防予第110号)に準じて措置されたい。 |
|
(安全な場所の取扱いについて)
| 問14 |
省令第19条第5項第18号に規定される「安全な場所」とは具体的にどのような場所か。 |
|
| ( |
答)
放出された消火剤及び燃焼ガスが著しく局部滞留を起こさない場所で、かつ、人が直接吸入するおそれのない場所とされたい。 |
|
(圧力上昇を防止するための措置の取扱いについて)
| 問15 |
省令第19条第5項第22号の2に規定する「防護区画内の圧力上昇を防止するための措置」として避圧口を設ける場合の開口部の面積算定方法をご教示願いたい。 |
|
| ( |
答)
当面、以下によられたい。 |
| A= |
K・Q/√(P-ΔP)
A:避圧口面積(平方センチメートル)
K:消火剤による定数(イナートガス消火剤:134
| HFC-23:2730 |
| HFC-227ea:1120) |
|
| Q:噴射ヘッドからの最大流量 |
( |
イナートガス消火剤:m3/分 |
| HFC消火剤:�L/秒) |
P:防護区画の許容圧力(パスカル)
ΔP:ダクトの損失(パスカル) |
|
(局所放出方式の取扱いについて)
| 問16 |
二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備のうち、局所放出方式のものについては、防護空間内が常時人がいない部分であれば、人が出入りする区画があっても設置を認めてさしつかえないか。 |
|
| ( |
答)
お見込みのとおり。なお、当該防護対象物の周囲における安全対策に留意されたい。 |
|
第4 防火対象物の指定
(ジェットスキー用の保管庫の取扱いについて)
| 問17 |
ジェットスキー用の保管庫は令別表第1の何項に掲げる防火対象物に該当するか。 |
|
|
(空室が過半を占める防火対象物の取扱いについて)
| 問18 |
防火対象物全体が休業中の場合の取扱いについては「休業中の防火対象物の取扱いについて」(昭和50年6月16日消防安第65号)において示されているが、防火対象物の過半が空室である防火対象物の空室部分についても同様に取り扱ってよいか。
また、空室部分については令別表第1に掲げる防火対象物に該当せず、無用途として取り扱ってよいか。 |
|
| ( |
答)
前段及び後段とも、「スケルトン状態の防火対象物に係る消防法令の運用について」(平成12年3月27日消防予第74号)によられたい。 |
|
第5 無窓階の判定
(合わせガラスの取扱いについて)
| 問19 |
材料板ガラスをフロート板ガラス(JIS R 3202 厚さ3.0mm)2枚とし、ポリビニルブチラール膜(膜厚0.76�@)を中間膜とした合わせガラス(JIS R 3205 板厚6.8mm)は、省令第5条の2第2項第3号に規定する開口部に該当するものと解してよいか。 |
|
| ( |
答)
開口部の外部にバルコニー、屋上広場等の破壊作業のできる足場が設けられ、開口部がはめ殺しでない場合に限り、お見込みのとおり。 |
|
(ガラス小窓付き鉄扉の取扱いについて)
| 問20 |
下図のガラス小窓付き鉄扉は、省令第5条の2第2項第3号に規定する開口部に該当するものと解してよいか。 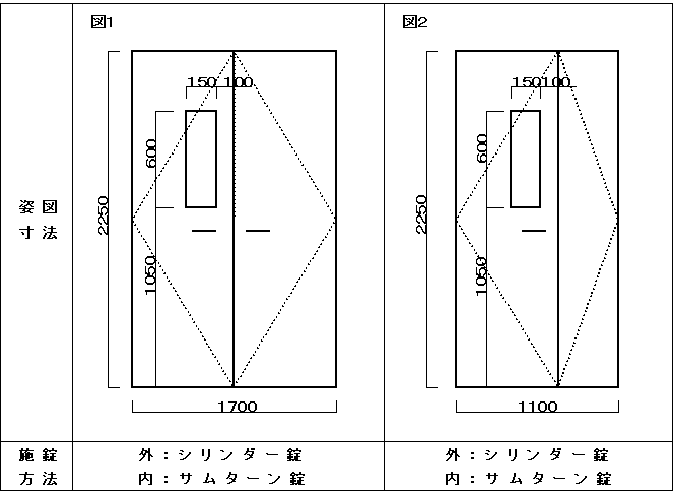 |
|
| ( |
答)
ガラス小窓を局部破壊しサムターン錠を開錠できる場合は、お見込みのとおり。 |
|
第6 消防用設備等の設置基準
(木製の陳列棚の取扱いについて)
| 問21 |
物品販売店舗等において、容易に取り外しできないよう木製の商品陳列棚を壁全面に直に取り付けた場合、令第11条第2項は適用できないと解してよいか。 |
|
|
(13条区画の取扱いについて)
| 問22 |
省令第13条第1項の区画の開口部に設ける「特定防火設備である防火戸」についてご教示願いたい。 |
| 1 |
省令第13条第1項第1号の区画に面して小荷物専用昇降機が設置される場合、当該部分に設けられた出し入れ口の戸も開口部として取り扱うべきか。 |
| 2 |
開口部として取り扱う場合、出し入れ口の戸を随時閉鎖できる特定防火設備である防火戸とすることは認められるか。 |
| 3 |
出し入れ口の戸の閉め忘れを音声によりアナウンスする等の措置を講じた随時閉鎖できる特定防火設備である防火戸は、省令第13条第1項第1号ハに規定する措置と同等以上のものとして取り扱ってよいか。 |
|
| ( |
答)
1 お見込みのとおり。
2 認められない。
3 認められない。 |
|
(シリコン油を用いる電気設備の取扱いについて)
| 問23 |
令第13条第1項に規定する発電機、変圧器その他これらに類する電気設備のうち、当該設備の冷却又は絶縁のためにJIS C 2320に規定される電気絶縁油のうち第6種絶縁油であるシリコン油を使用するものにあっては、「電気設備が設置されている部分等における消火設備の取扱いについて」(昭和51年7月20日消防予第37号)第1、1(2)又は3(5)の「冷却又は絶縁のため、油類を使用せず、かつ、水素ガス等可燃性ガスを発生するおそれのないもの」に該当するものとして取り扱ってよいか。 |
|
|
(不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備に用いる配管の取扱いについて)
| 問24 |
不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備に用いる配管については、継目無鋼管及び電気抵抗溶接鋼管のいずれを用いてもよいか。 |
|
|
(水道用ステンレス鋼管の取扱いについて)
| 問25 |
JWWA G 115(水道用ステンレス鋼管)は「令8区画及び共住区画を貫通する鋼管等の取扱いについて」(平成8年3月27日消防予第47号)別添2に該当するものとして取り扱ってよいか。 |
|
|