特集1 熊本地震の被害と対応
1.地震の概要
平成28年4月14日21時26分、熊本県熊本地方の深さ11kmを震源として、マグニチュード6.5の地震が発生し、益城町で震度7を観測した(特集1-1表)。
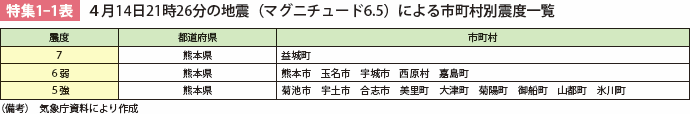
さらに、28時間後の4月16日1時25分、熊本県熊本地方の深さ12kmを震源として、マグニチュード7.3の地震が発生し、益城町及び西原村で震度7を観測した(特集1-2表)。
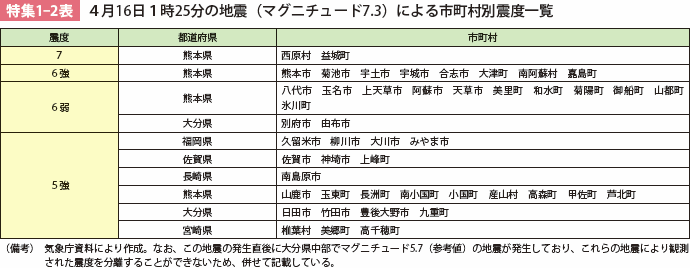
その後、熊本県から大分県にかけて地震活動が活発な状態で推移した。気象庁は、これらの地震を含め、4月14日21時26分以降に発生した熊本県を中心とする地震活動を「平成28年(2016年)熊本地震」(以下「熊本地震」という。)と命名した。
一連の地震は、10月31日までに震度1以上が4,123回、震度5強以上が12回発生した(特集1-3表)。
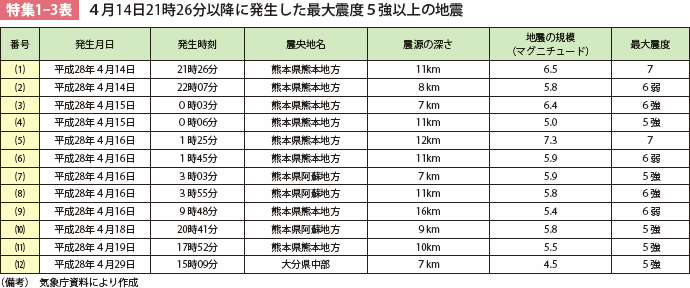
気象庁による震度観測開始以降、震度7を観測したのは、平成7年(1995年)兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)、平成16年(2004年)新潟県中越地震及び平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)に続き、本地震がそれぞれ4、5例目となった。これまで、国内において2度の震度7を観測した地域は例がなく、さらに、連続して発生したことも観測史上初めてのことであった。

(1) 人的被害
家屋の倒壊や土砂災害が多数発生したことにより、死者139人、重傷者957人、軽傷者1,486人、その他分類未確定の負傷者138人(10月27日時点)と多くの被害が生じ、そのほとんどが熊本県での発生となった(特集1-4表)。
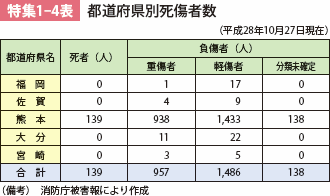
※ 死者数の内訳は次のとおり(熊本県より報告)
1. 地震の直接的な影響による死者数(警察が検視により確認) 50人
2. 災害による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による死者数 84人
3. 6月19日から25日に発生した大雨による被害のうち熊本地震との関連が認められた死者数 5人
(2) 物的被害
- ア 住家被害
- 住家については、全壊8,298棟、半壊31,249棟、一部破損141,826棟(10月27日時点)と甚大な被害が発生し、その多くが熊本県に集中した(特集1-5表)。
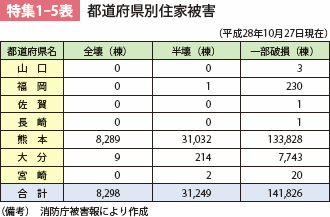
- イ その他の被害
- (ア) 道路の被害
熊本県及び周辺各県の高速道路、国道、県道等においては、4月14日21時26分及び4月16日1時25分の地震等により、各所で路面の亀裂、陥没、落石、落橋等の被害が発生し、多くの通行規制が実施された。
また、南阿蘇村において阿蘇大橋が崩落し、地域住民の生活に大きな影響を与えた。
(イ) 地方公共団体の庁舎の被害
複数の市町村で災害対策の拠点となる庁舎が被災した。庁舎4階部が大きく損壊した宇土市を含め、庁舎が使用できなくなった熊本県内の5市町(八代市、人吉市、宇土市、大津町及び益城町)においては、公民館や体育館等にその機能を移転し、災害対応業務等が行われた。




(3) 6月19日からの梅雨前線に伴う大雨による被害
西日本から関東の南にかけて停滞する梅雨前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、大気の状態が非常に不安定となり、6月19日から25日にかけて、西日本を中心に大雨となった。
これに伴い、熊本県においては、地震により地盤が緩んでいるところに大雨が降ったことが原因と考えられる土砂災害等が発生し、死者5人、軽傷者3人、全壊13棟、半壊102棟、床上浸水151棟、床下浸水498棟、一部破損10棟の被害が生じた(10月27日時点)。
(4) 避難の状況
4月14日21時26分の地震発生後から、激震に見舞われた地域の住民は、小中学校や公民館等の公共施設をはじめとする避難所に避難した。地震発生から一夜明けた4月15日5時00分時点においては、熊本県内で、505箇所の避難所に4万4千人を超える住民が避難している。4月16日1時25分の地震発生により、避難者の数は急増し、熊本県では、最大で855箇所の避難所に18万人以上、大分県では、311箇所の避難所に1万2千人以上の住民が避難した。
また、地震による地盤の緩みが生じている中での大雨の影響により、土砂災害の発生が懸念されたことから、発令された避難指示及び避難勧告は、4月21日21時50分時点が最大規模となり、それぞれ4,198世帯、10,268人以上及び108,187世帯、266,940人以上が対象となった。
避難者数については、熊本県で、4月17日9時30分時点が最大となり、855箇所の避難所に183,882人が避難した。また、大分県では、同日8時00分時点が最大となり、311箇所の避難所に12,443人が避難した。このほか福岡県、佐賀県、長崎県及び宮崎県においても、多くの住民が避難した。
また、避難生活が長期化する中、相次ぐ余震に対する不安から、屋外において避難生活を過ごす被災者が多く、車中泊避難をする住民も多くいた。
