第2章 消防防災の組織と活動
第1節 消防体制
1.消防組織
(1) 常備消防機関
常備消防機関とは、市町村に設置された消防本部及び消防署のことであり、専任の職員が勤務している。平成28年4月1日現在では、全国に733消防本部、1,714消防署が設置されている(第2-1-1表)。
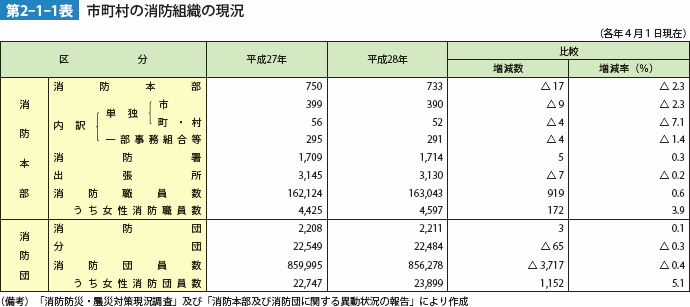
消防職員は16万3,043人であり、うち女性職員は4,597人である(第2-1-1表、第2-1-1図)。
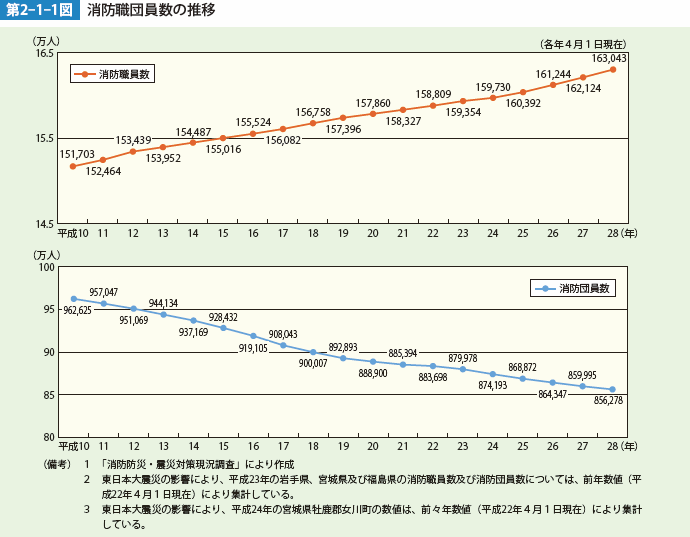
市町村における現在の消防体制は、大別して、〔1〕消防本部及び消防署(いわゆる常備消防)と消防団(いわゆる非常備消防)とが併存している市町村と、〔2〕消防団のみが存する町村がある。
平成28年4月1日現在、常備化市町村は1,690市町村、常備化されていない町村は29町村で、常備化されている市町村の割合(常備化率)は98.3%(市は100%、町村は96.9%)である。山間地や離島にある町村の一部を除いては、ほぼ全国的に常備化されており、人口の99.9%が常備消防によってカバーされている。
このうち一部事務組合又は広域連合により設置している消防本部は291本部(うち広域連合は22本部)であり、その構成市町村数1,109市町村(367市、602町、140村)は常備化市町村全体の65.6%に相当する。また、事務委託をしている市町村数は139市町村(34市、85町、20村)であり、常備化市町村全体の8.2%に相当する(第2-1-2図)。
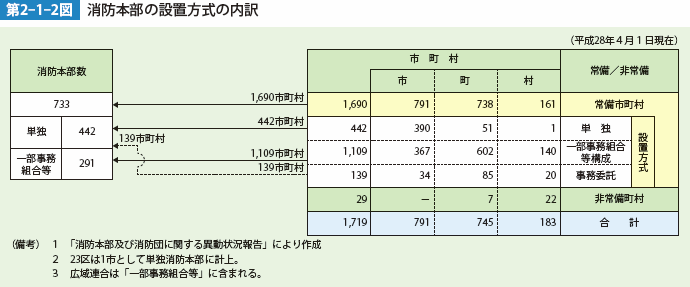
(2) 消防団
消防団は、市町村の非常備の消防機関であり、その構成員である消防団員は、他に本業を持ちながらも、権限と責任を有する非常勤特別職の地方公務員として、「自らの地域は自らで守る」という郷土愛護の精神に基づき、消防防災活動を行っている。
平成28年4月1日現在、全国の消防団数は2,211団、消防団員数は85万6,278人であり、消防団は全ての市町村に設置されている(第2-1-1表、第2-1-1図)。
消防団は、
- 地域密着性(消防団員は管轄区域内に居住又は勤務)
- 要員動員力(消防団員数は消防職員数の約5.3倍)
- 即時対応力(日ごろからの教育訓練により災害対応の技術・知識を習得)
といった特性を活かしながら、火災時の初期消火や残火処理、風水害時の警戒や救助活動等を行っているほか、大規模災害時には住民の避難支援や災害防御等を、国民保護の場合には避難住民の誘導等を行うこととなっており、特に消防本部・消防署が設置されていない非常備町村にあっては、消防団が消防活動を全面的に担っているなど、地域の安全・安心確保のために果たす役割は大きい。
また、消防団は、平常時においても火災予防の啓発や応急手当の普及等地域に密着した活動を展開しており、地域防災力の向上、地域コミュニティの活性化にも大きな役割を果たしている。

