3.消防と医療の連携促進
(1) 救急搬送における医療機関の受入状況*8
全国各地で救急搬送時の受入医療機関の選定に困難を生ずる事案が報告されたことから、消防庁では、平成19年10月に、平成16年中から平成18年中における産科・周産期傷病者搬送の受入実態についての調査を初めて実施した。また、平成19年中の救急搬送における受入状況等実態調査においては、産科・周産期傷病者に加え、重症以上傷病者、小児傷病者及び救命救急センター等への搬送傷病者も対象として調査を実施した。
「平成27年中の救急搬送における医療機関の受入状況等実態調査」では、平成26年中の同調査と比較し、照会回数4回以上の事案の件数については、全ての類型において減少した。割合については、小児傷病者搬送事案のみ横ばいであり、それ以外は減少した(第2-5-7表)。現場滞在時間30分以上の事案の件数については、小児傷病者搬送事案及び救命救急センター搬送事案が増加する一方、重症以上傷病者搬送事案、産科・周産期傷病者搬送事案が減少した。割合については、重症以上傷病者搬送事案は減少、救命救急センター搬送事案は横ばいであり、産科・周産期傷病者搬送事案及び小児傷病者搬送事案は、増加した(第2-5-8表)。
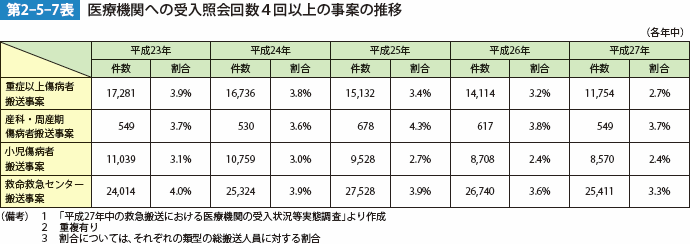
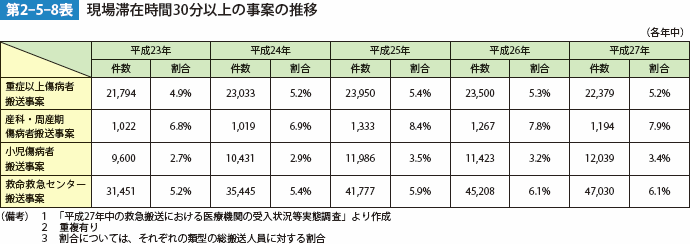
*8 東日本大震災の影響により、平成23年1月から4月までの釜石大槌地区行政事務組合消防本部のデータの一部及び平成23年1月から3月までの陸前高田市消防本部のデータは除いた数値により集計している。また、東日本大震災に伴う緊急消防援助隊による救急活動は、本調査対象から除外している。
(2) 傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準
救急搬送において、受入医療機関の選定困難事案が発生している状況を踏まえ、消防庁では平成21年、厚生労働省と共同で、都道府県に対する「傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準」(以下「実施基準」という。)の策定及び実施基準に関する協議会の設置の義務付け等を内容とする消防法改正を行った。この改正消防法は、平成21年10月30日に施行され、現在、全ての都道府県において協議会が設置され、実施基準も策定されているところである。各都道府県は、法定協議会において実施基準に基づく傷病者の搬送及び受入れの実施状況を調査・検証した上で、その結果を実施基準の改善等に結び付けていくことが望まれる。
消防庁としては、各都道府県の取組状況や課題を把握するとともに、効果的な運用を図っている地域の取組事例等を広く把握・紹介するなどして、フォローアップに取り組んでいる。
各都道府県や地域において、消防機関と医療機関をはじめ、医療機関相互、さらには、地域の実情に応じて、専門科医、保健所、福祉、警察等の関係機関等が一堂に会し、搬送と受入れの実態について、事後検証等を通じて徹底的な議論を行い、問題意識を共有するとともに、日常的に「顔の見える関係」を構築する中で、円滑な搬送と受入れに向けて、より具体的・効果的なルール作り(実施基準の改定等)を行っていくことが重要であり、各団体において、更なる取組を図っていくことが求められる。消防庁としても、引き続き、都道府県の協議会における実施基準の運用改善や見直しの議論に資するよう、必要な調査や情報提供を行うこととしている。
なお、消防法が改正され、実施基準に基づく救急搬送が実施されたことを踏まえ、地域における救急医療体制の強化のため、地方公共団体が行う私的二次救急医療機関への助成に係る経費について、特別交付税による地方財政措置を講じている。
(3) 救急医療体制
傷病者の主な搬送先となる救急病院及び救急診療所の告示状況は、平成28年4月1日現在、全国で4,292箇所となっている(附属資料43)。
初期救急医療体制としては、休日、夜間の初期救急医療の確保を図るための休日夜間急患センターが559箇所(平成28年3月31日現在)、第二次救急医療体制としては、病院群輪番制病院及び共同利用型病院が2,733箇所(平成28年3月31日現在)、第三次救急医療体制としては、救命救急センターが284箇所(平成28年8月1日現在)整備されている。また、救命救急センターのうち広範囲熱傷、指肢切断、急性中毒等の特殊疾病傷病者に対応できる高度救命救急センターは、36箇所(平成28年8月1日現在)整備されている。
救急告示制度による救急病院及び救急診療所の認定と初期・第二次・第三次救急医療体制の整備については、都道府県知事が定める医療計画の下で一元的に実施されている。
これらの救急医療体制の下、消防法の規定により都道府県が策定する実施基準では、傷病者の状況に応じた医療の提供が可能な医療機関のリストが作成されており、消防機関はそのリストを活用して、救急搬送業務を行っている。
