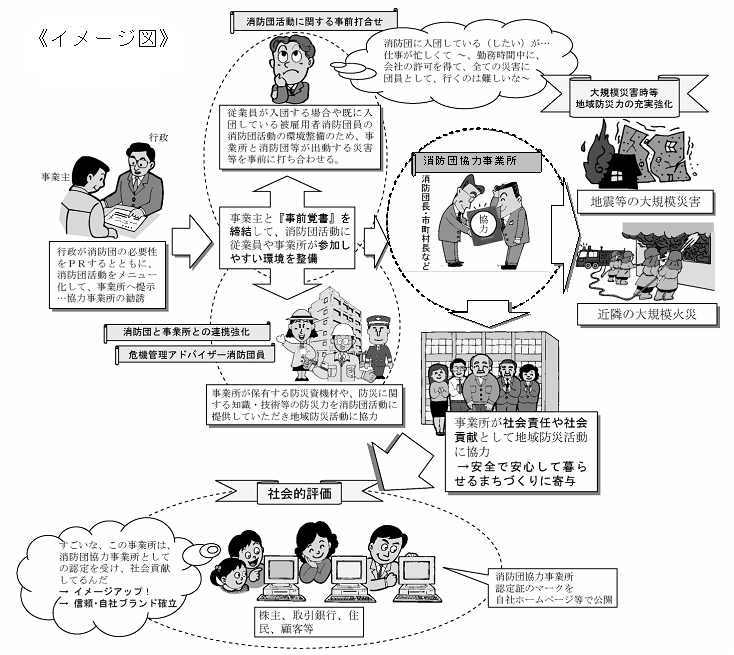報道資料 総務省
平成18年4月7日
消防庁
消防団と事業所の協力体制に関する検討結果
-地域防災力の充実強化に向けた消防団と事業所との協力体制について-
消防団は、大規模災害や有事における国民保護の必要性から考えると、地域住民の安心安全を確保するため欠かさない組織で、今後とも大いに活躍することが期待されているところです。昨年の台風第14号等の豪雨災害、福岡県西方沖地震や宮城県沖を震源とした地震など、大規模災害が全国各地で相次いで発生し、多くの犠牲者を出し、家屋等にも甚大な被害が及んだところですが、各地の消防団は、防災活動や住民の避難誘導、被災者の救出・救助活動などの活動を行い、大きな成果を上げており地域住民からも高い期待が寄せられています。
しかしながら、消防団員数の減少、消防団員の被雇用者化など、多くの課題に直面しており、地域防災力の確保に向けて国、都道府県、市町村及び消防団が一体となった対策が必要となっています。
そこで、消防庁では、特に全消防団員の約7割が被雇用者であることから、消防団活動への一層の理解と協力を得るために、平成17年8月に「消防団と事業所の協力体制に関する調査検討会」を設け、これまで、消防団と事業所の協力体制の在り方について検討を行ってまいりました。このたび、同検討会において、議論・整理された検討結果が取りまとめられましたので、お知らせします。
《添付資料》
消防団活動への一層の理解・協力を得るために(概要)
-「消防団と事業所の協力体制に関する調査検討会」報告書-
※ 報告書については、消防庁のホームページに掲載いたしますのでご覧下さい。
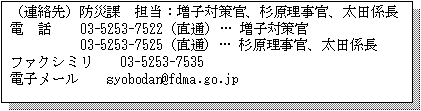
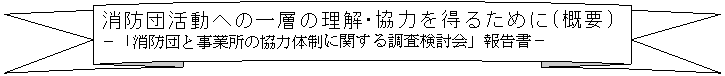
Ⅰ 消防団の現状と課題と検討の方向性
- 消防団の位置づけ
消防団員は、平素は生業を持ちながら、消防活動を行う権限と責任を有する非常勤特別職の地方公務員で地域の安全確保のために不可欠な存在。
- 消防団の役割の拡大
① 大規模災害等への対応
② 地域防災コーディネーターとしての役割
③ 有事における国民保護への対応 - 消防団を取り巻く社会環境の変化
① 産業・就業構造の変化
② 地域・時間別の地域防災の格差
③ 地域コミュニティの変化
④ 若年層人口の減少
⑤ 高齢者人口の増大
⑥ 行政の事業所等へのPR不足
⑦ 事業所の社会責任及び社会貢献
⑧ 広域市町村合併による再編 - 検討会における検討の進め方
① 事業所の立場からの検討課題
② 被雇用者消防団員の立場からの検討課題
③ 市町村、消防本部等の立場からの検討課題
Ⅱ 事業所と消防団の協力体制に関する調査結果
日本商工会議所及び日本経済団体連合会の協力を得て、各地の事業所を対象としたアンケート調査を実施した。
Ⅲ 消防団と事業所との連携体制の強化に関する提言
- 事業所における被雇用者消防団員の活動環境の整備
- 消防団活動に関する事前打合せについて -従業員である被雇用者消防団員においては、雇用事業所からの理解を得て、消防団活動が行える環境整備が必要である。そのため、消防団等から事業所にアプローチし、まずは、相互で話し合い協力していただくことが必要である。その上で、事業主と消防団で予め消防団活動について、必要な事項(例えば、勤務時間中における災害出動及び訓練等への配慮として、ボランティア休暇扱いにするなど)があれば、それを取り決める。そして、必要な場合は、覚書きの締結等により調整することにより、被雇用者消防団員の活動環境を整備する。
- 事業所との新たな協力関係の構築
- 消防団と事業所との連携強化策について -大規模災害発生時等において、事業所が有する重機等の防災資機材の提供と併せてその資機材の操縦技術を有する従業員が機能別団員(機能別団員とは、昨年度、新たに構築した制度で、特定の災害・活動のみに参加する消防団員をいう。)となり、事業所が社会責任及び社会貢献の一つと捉え、地域防災活動に協力してもらえる関係を構築する。
- 事業所における防災知識・技術に関するストックの活用
- 危機管理アドバイザー消防団員について -大規模、特殊災害については、消防職員や消防団員の知識・技術だけでは、迅速かつ的確な意思決定や災害応急対策の実施が難しくなっているのが現状である。そのため、事業所や大学機関等の専門機関の研究者、学識経験者等に機能別団員になってもらうことにより、防災対策に関する助言(アドバイス)等を専門家から受け、迅速かつ的確な意思決定や災害応急対策が実施できる関係を構築する。
- 消防団活動への協力が社会責任及び社会貢献として捉えられる環境づくり
- 消防団協力事業所について -事業所が消防団活動に協力することが「地域防災活動」につながり、ひいては、環境のISO認証制度等のように、社会責任及び社会貢献として認められ、なおかつ、事業所の信頼性の向上につながるよう環境を整備する。