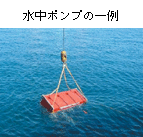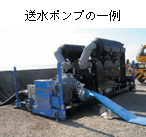[石油コンビナート災害対策の課題]
1 災害対策の推進
特別防災区域に関しては、消防法や高圧ガス保安法等の規制に加えて石油コンビナート等災害防止法により、特定事業者に対する災害の拡大防止を図るための規制や義務付けを行うとともに、道府県に防災本部を常設し、消防機関をはじめとした防災関係機関、特定事業者が一体となった防災体制が確立されている。
こうした中、平成15年に発生した苫小牧市内の石油精製事業所の事故を受け、石油コンビナート等災害防止法が改正されるとともに石油コンビナート等災害防止法施行令が改正され、大容量泡放射システムの配備を特定事業所に義務付けることにより、防災対策を強化し、災害対応に努めることとされた。
(1)特定事業所における防災体制の充実強化に伴い検討すべき事項
特別防災区域における事故は年々増加傾向にあり、平成19年中の事故件数は過去最多となっている。特に、石油や高圧ガス等を大量に貯蔵し、取り扱う石油製品製造関係の特定事業所において事故が増加しているほか、屋外タンク貯蔵所における漏えい事故が大幅に増加している。その中でも、内部浮きぶた付き屋外タンク貯蔵所の浮きぶたの異常時における応急措置に苦慮する事案が見受けられたほか、石油コンビナート等災害防止法第23条の規定に基づく異常現象の通報を怠った事例が判明するなど、特定事業所の事故防止体制に憂慮される事態が見受けられることから、特定事業所の防災体制の現状を把握し、適切な指導、助言等を行っていく必要がある。
(2)大容量泡放射システムの配備に伴う今後の課題
新たに大容量泡放射システムが配備されたことに伴い、今後、特定事業者と道府県を中心とした関係防災機関等が一体となった防災訓練を行っていく必要がある(囲み記事「大容量泡放射システムの配備について」参照)。
大容量泡放射システムの配備について
平成15年の十勝沖地震による浮き屋根式屋外タンク貯蔵所の全面火災を受けて、直径34メートル以上の浮き屋根式屋外タンク貯蔵所が存する特定事業所に大容量泡放射システムが配備されることとなりました。
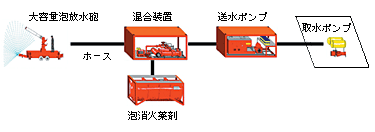
大容量泡放射システムは、一の特別防災区域内に所在する特定事業所が共同して設置する、いわゆる共同防災組織による配備のほか、二以上の特別防災区域にわたる区域であって、地理的条件、交通事情、災害発生のおそれ、特定事業所の集中度その他の事情を勘案して政令で定めた12の区域ごとに所在する特定事業所が共同して設置する、いわゆる広域共同防災組織による配備が可能とされています。
大容量泡放射システムに必要とされる基準放水能力は、浮き屋根式屋外貯蔵タンクの直径に応じ、毎分1万リットル~8万リットルとされ、泡放水砲1基当たりの放水能力は、従来の3点セット(大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車)の3倍~10倍の泡放射を行うことが可能となっています。実際に配備される泡放水砲は、1万リットル~4万リットルの放水能力を有するものであるため、直径の大きなタンクには複数の泡放水砲が配備されます。
また、大容量泡放射システムは放射距離を確保するため、泡放水砲ノズル本体では空気を取り込まずに、滞空中に発泡する仕組みのノンアスピレート方式を主流としています。

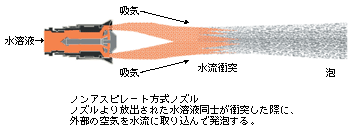
大容量泡放射システムは我が国初の防災資機材であり、メーカーごとにポンプ、混合装置又はホースなどの大きさや形状、特性等が異なっており、今後、大容量泡放射システムを用いた関係機関等が一体となった防災訓練等の実施が課題となっています。