第3節 災害に強い安全なまちづくり
1 防災基盤等の整備
(1)公共施設等の耐震化
消防庁では、地震等の大規模な災害が発生した場合においても、災害対策の拠点となる施設等の安全性を確保し、もって被害の軽減及び住民の安全を確保できるよう防災機能の向上を図るため、「災害に強い安全なまちづくり」の一環として、公共施設等耐震化事業により、
〔1〕 避難所となる公共・公用施設(学校や体育館など)
〔2〕 災害対策の拠点となる公共・公用施設(都道府県、市町村の庁舎や消防署など)
〔3〕 不特定多数の住民が利用する公共施設(文化・スポーツ施設、道路橋りょう、交通安全施設、福祉施設など)
の耐震化を推進している。
なお、「防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査報告書」(平成20年11月)によると、地方公共団体が所有している公共施設等のうち、災害応急対策を実施するに当たり、平成19年度末まで地方公共団体が所有又は管理している防災拠点となる公共施設等の19万2,735棟のうち12万415棟(62.5%)の耐震性が確保されていると考えられる(第4-3-1図)。
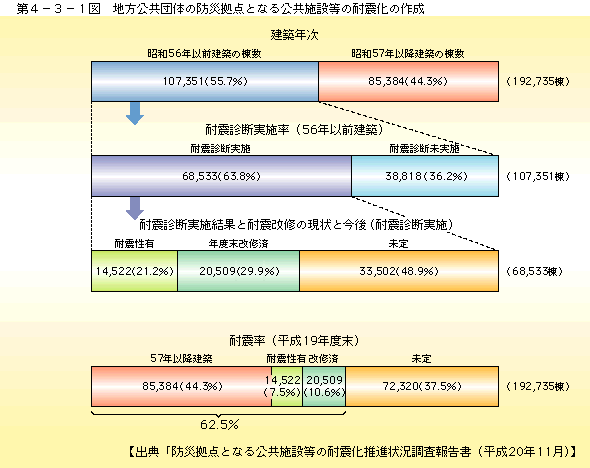
消防庁では、地方公共団体が公共施設の耐震化を進める上での参考となる資料として「防災拠点となる公共施設の耐震化促進資料(耐震化促進ナビ)」を作成し、すべての地方公共団体へ配付するとともに、消防庁ホームページにおいて公表している。
さらに、初動対応の要となる都道府県・市町村庁舎等の耐震率の向上や家具転倒防止等自主防災の推進など「切迫する大地震に立ち向かう施策」に取り組んでいるところである。
(2)防災施設等の整備
災害に強い地域づくりを推進するためには、消防防災の対応力の向上に資する施設等の整備が必要であり、消防庁では、消防防災施設整備費補助金や防災基盤整備事業等により、防災情報通信施設や耐震性貯水槽等の整備を促進している。
平成16年(2004年)新潟県中越地震の際には、一部の市町村において停電により窓口業務や県防災行政無線等に支障が生じ、平成17年7月23日の千葉県北西部を震源とする地震及び同年8月16日の宮城県沖を震源とする地震の際には震度情報の送信が遅延するなどの障害が生じた。
こうしたことから、消防庁では、非常用電源の整備、保守点検の実施と的確な操作の徹底、防災行政無線を使用した通信訓練の実施等を地方公共団体に要請するとともに、迅速かつ確実な震度情報の伝達を可能とする次世代の震度情報ネットワークのあり方に関する検討を行い、地方公共団体に提言したところである。
(3)防災拠点の整備
大規模災害対策の充実を図る上で、住民の避難地又は防災活動の拠点を確保することは非常に重要であり、想定される災害応急活動の内容等に応じた機能を複合的に有する「防災拠点」として整備していくことが必要である。
このため、平常時には防災に関する研修・訓練の場、地域住民の憩いの場等となり、災害時には、防災活動のベースキャンプや住民の避難地となる防災拠点の整備が必要である。消防庁では、防災基盤整備事業等により地方公共団体における防災拠点の整備を促進している。
