3 情報処理システムの活用
(1)防災情報システムの整備
大規模災害発生時の災害応急活動においては、広域的な対応が重視され、より迅速な情報収集・伝達と地方公共団体の対応力を把握した上での調整判断が不可欠となる。
消防庁では、震度情報や緊急消防援助隊派遣時などの広域応援に対応するための情報などについて、防災情報のデータベース化と国・地方公共団体間のネットワーク化により、情報の共有化と迅速な収集・伝達を図り、円滑な広域応援の実施や地方公共団体等における防災対策の高度化のため、防災情報システムの整備を推進している。
全国の市町村で計測された震度情報を消防庁へ即時送信するシステム(震度情報ネットワーク)は、平成9年4月から運用を開始しており、本システムで収集された震度データは、緊急消防援助隊の派遣等、広域応援活動に活用するとともに、気象庁にも提供され震度情報として発表されている。
近年、システム機器の老朽化等により震度情報の送信が遅延するなどの問題が生じているため、消防庁では次世代震度情報ネットワークのあり方に関する検討を行い、平成18年3月に報告書を取りまとめたところである。
(2)災害対応支援システムの導入と活用
災害発生時には、正確かつ迅速な状況判断の下に的確な応急活動を遂行する必要があり、そのためには、災害発生時にはシミュレーションにより被害を推測することができ、かつ、平時には円滑な災害対応訓練に活用できるシステムを導入することが有効であることから、消防庁では、地震被害予測システム等の開発・普及に努めている。
中でも、消防研究センター(旧独立行政法人消防研究所)で開発した「簡易型地震被害想定システム」(第2-9-4図)は、簡単な操作で即座に地震による被害を推計することが可能であり、的確な状況判断、初動措置の確保、日常の指揮訓練等に役立つことから、全都道府県等に配布しその活用を図るとともに、消防庁の消防防災・危機管理センターにおいても被害予測に同システムを活用している。
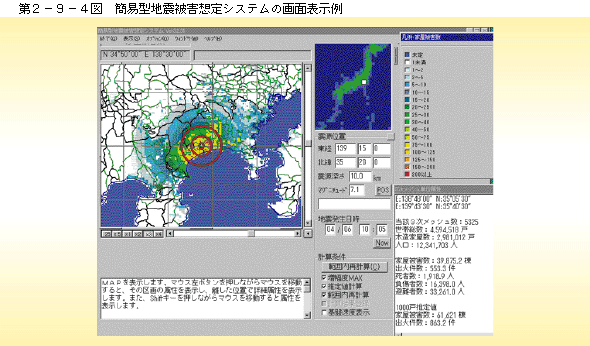
(3)各種統計報告オンライン処理システム
行政事務の情報化に対応し、統計事務の効率化・迅速化を図るため、平成14年度からVPN(Virtual Private Network:仮想専用線)を活用した、以下に掲げる各種統計報告のオンライン処理を可能とするシステムの開発を行っており、平成15年度から順次運用を開始している。
・火災報告等オンライン処理システム
・防火対象物実態調査等オンライン処理システム
・ウツタイン様式調査オンライン処理システム
・「危険物規制事務調査」及び「危険物に係る事故及びコンビナート等特別防災区域における事故報告」オンライン処理システム
・救急救助調査オンライン処理システム
・石油コンビナート等実態調査オンライン処理システム
消防庁では、これらのデータを迅速的確に収集・整理することにより、各都道府県、各消防本部への速やかな情報提供、各種施策への反映を支援している。
なお、平成20年度からは「消防防災・震災対策等現況調査」をオンライン処理システム上で運用を開始した。またこれを機に、消防庁と各都道府県、市町村及び消防本部との間の接続方式をVPNからSSL(Secure Sockets Layer:WEBブラウザとWEBサーバ間で情報を暗号化して通信する方式)に変更し、セキュリティの強化を図ったところである。
