2 国民の保護に関する基本指針・国民の保護に関する計画
(1)基本指針と指定行政機関等の計画
国民保護法に基づく国民の保護に関する基本指針(以下「基本指針」という。)は、平成17年3月25日に閣議決定され、その後随時変更が行われている。
【基本指針の構成】
〔1〕 基本的人権の尊重や指定公共機関の自主性の尊重など、国民の保護のための措置の実施に関する基本的な方針
〔2〕 着上陸侵攻、ゲリラや特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空攻撃の4つを想定される武力攻撃事態の類型とし、それぞれの特徴及び留意点を示した武力攻撃事態の想定に関する事項
〔3〕 国民保護措置を的確かつ迅速に実施するための体制の整備に関すること
〔4〕 住民の避難、避難住民等の救援、武力攻撃災害への対処に関する措置、国民生活の安定、武力攻撃災害の復旧等についての国、地方公共団体等のとるべき措置
〔5〕 武力攻撃に準ずる大規模テロ等の事態(緊急対処事態)における国民保護措置に準じた措置の実施
〔6〕 国民の保護に関する計画等を作成する際の関係者からの意見聴取
指定行政機関(各省庁)の長、都道府県知事及び指定公共機関は、基本指針に基づき、国民保護計画又は国民の保護に関する業務計画(以下「国民保護業務計画」という。)を作成することとされている。指定行政機関及び都道府県の国民保護計画については、平成17年度中にすべての団体の計画が閣議で了承され、指定公共機関の国民保護業務計画についても、平成18年5月までに全指定公共機関で作成された。
市町村長及び指定地方公共機関は、都道府県の国民保護計画に基づき、国民保護計画又は国民保護業務計画を作成することとされており、平成19年度末までに大部分の団体が計画を作成したところである(第3-2図)。
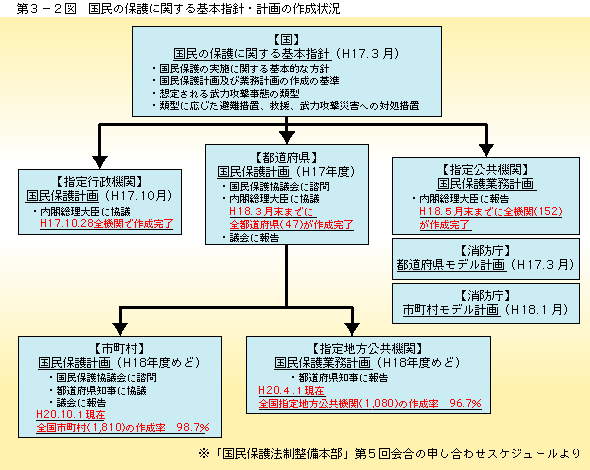
(2)消防庁国民保護計画
消防庁は、指定行政機関の一つとして、基本指針に基づいて、その所掌事務に関する国民保護計画を作成することとされている。消防庁の国民保護計画では、消防庁が実施する国民保護措置の内容、実施方法、体制、関係機関との連携方法等を定めている。
消防庁の国民保護計画は、平成17年10月28日に他の省庁の国民保護計画とともに閣議で了承され、その後随時変更が行われている。
【消防庁国民保護計画の特徴】
〔1〕 テロやゲリラの侵攻などの突発的な事案においては、全職員体制の消防庁緊急事態連絡室を設置し、地方公共団体との連携や情報交換のための初動体制を整備すること。
〔2〕 必要に応じ、全国瞬時警報システム(J-ALERT)等により、地方公共団体や住民に瞬時に緊急情報を伝達すること。
〔3〕 自然災害の場合等において他県の消防部隊が応援に駆けつける緊急消防援助隊の仕組みを、武力攻撃やテロの場合においても活用するため、部隊の増強や資機材の整備を図ること。
特に、NBC災害に対応するためには、対応能力を持つ緊急消防援助隊による応援が重要なため、当該拠点となる消防本部の充実を図ること。
〔4〕 住民の避難誘導において重要な役割を果たす消防団や自主防災組織の充実を図るため、啓発の充実や設備の整備等を支援すること。
〔5〕 住民の避難誘導や被災者の救助に当たっては、平成17年4月に発生したJR西日本福知山線列車事故のように事業所の協力が必要となることから、被災時における事業所と地方公共団体との連携を支援すること。
