4 住宅用火災警報器のすみやかな普及に向けた取組
(1)依然高水準にある住宅火災被害
住宅火災による死者数は、平成15年以降5年連続して1,000人を超えるかつてない高い水準で推移している。このうち、約6割が65歳以上の高齢者であることから、高齢化の進展にあわせて今後さらに死者数が増加することが懸念されており、住宅防火対策の推進が消防行政の最重要課題の一つとなっている。
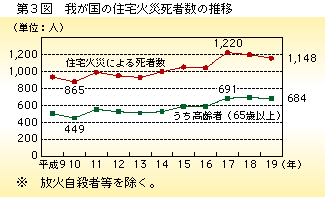
(2)住宅用火災警報器の設置の義務化
〔1〕 義務化の経緯
住宅火災においては、火災に気付かず逃げ遅れることにより犠牲になるケースが多いと考えられている。このため、米国、英国等においては既に住宅に火災警報器の設置が義務付けられていたが、米国では、その普及に伴い住宅火災による死者数が半減するという効果が現れている。こうしたことから我が国においても、戸建を含む全ての住宅を対象に住宅用火災警報器(以下、「住警器」という。)の設置を義務付ける消防法の改正が平成16年に行われた。平成18年6月から全国で義務化された新築住宅に続き、市町村条例で定めることとされていた既存住宅についても一部地域で既に義務化が始まっており、平成23年6月の義務化の全国拡大に向けて普及促進の取組が活発に行われている。
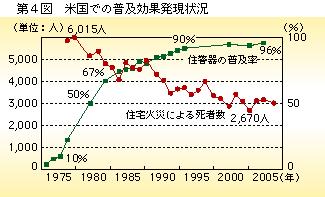
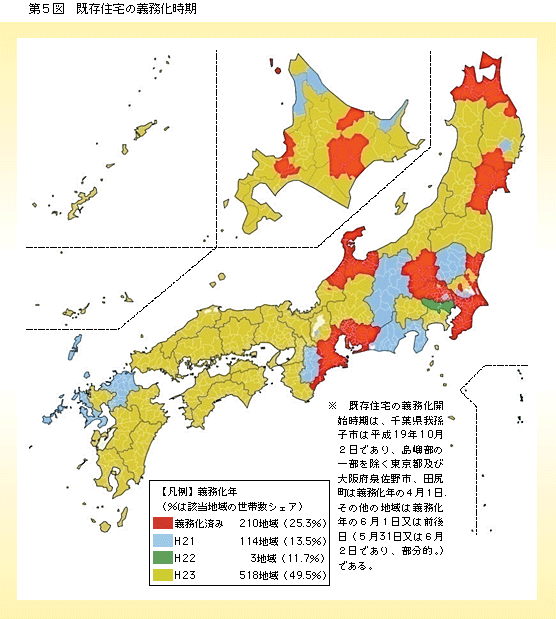
警報により早期に火災に気付き、「無事に避難できた。」、「初期消火に成功した。」といった奏功事例も全国から多数寄せられてきている。住警器の設置は住宅防火対策の「切り札」と言え、その一刻も早い各家庭への普及が期待される。
〔2〕 住宅用火災警報器の普及状況
住警器の普及状況については、各地域においてアンケート等の方法により調査が行われているところであるが、消防庁においてその結果を収集し、独自の方法で平成20年6月時点に換算したところ、全国の推計普及率は35.6%となっている。この結果を見ると、未だ十分には普及が進んでいないため、今後も普及促進活動を強力に推進する必要がある。
なお、普及状況のデータは、効果的な普及策の展開や死者発生防止効果の説明等に活用されることにより、住警器のさらなる普及促進に資することが期待されるところであり、各地域において創意工夫を凝らした様々な方法で普及状況の把握が進められている。
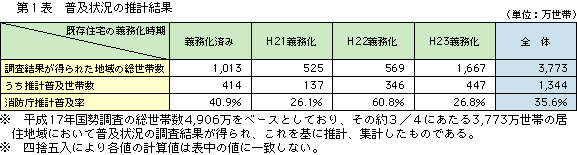
(3)住宅用火災警報器の普及に向けた取組
店舗や事務所等を対象としていた従来の消防用設備とは違って、一般家庭の住宅を対象とする住警器の普及には、これまでとは違う工夫を凝らした取組が求められる。このため各地域・各主体が知恵を出し、協力しながら様々な取組を試みているところであり、その成果として住警器の普及が図られ、住宅火災による被害の低減、安心・安全の地域づくりの実現が期待される。
〔1〕 地域住民組織による取組
住警器の普及に最も効果を発揮しているのは、自治会や婦人会等の地域住民組織による取組である。特に自主防災組織や婦人(女性)防火クラブ、消防団等の防火活動に努めてきた組織を中心として、地域社会との繋がりを活かした効果的な取組が展開されている。
ア 共同購入の実現で地域の普及率を一気に向上
茨城県大子町では、消防団が中心となって住警器の共同購入を推進している。パンフレットやチラシの配布、注文の受付、集金を各分団長が責任者となって行い、販売事業者と交渉して低価格での購入を実現させた。その結果、町全体の普及率は平成19年12月時点で約50%となった。また、ほとんどの世帯で消防団員が取付け作業を行うことにより、早期に火災覚知できる適切な設置が徹底されている。
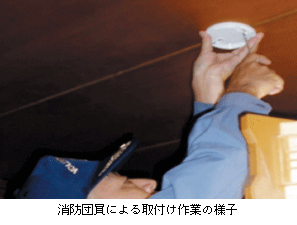
イ 町会による古紙回収収益で住警器を購入
東京都豊島区の巣鴨三明町会では、古新聞の資源回収収益金での住警器配布を企画した。住警器の購入にあたっては販売事業者と粘り強く値引き交渉を行い、町会加入者全世帯に無料で配布することができた。また、1人暮らしの老人世帯には取付け作業も町会役員が実施した。
ウ 実火災をイメージした隣近所が支え合う安全体制づくり
茨城県那珂市の額田地区では、住警器の設置が効果を上げるためには避難誘導に対する近隣住民の協力が欠かせないと考え、地区会費で高齢者宅に住警器と連動した外部ブザーを設置することにした。さらに、ブザー鳴動時に近隣住民が避難誘導する訓練も実施しており、実火災に備えた体制づくりに努めている。
〔2〕 地域事業者による取組
地域に根ざして活動する事業者も住警器の普及に向けた取組を展開している。地域社会に貢献し、地域とともに発展しようとする経営理念が地域の事業者に浸透し、効率的に住宅防火が推進されることが期待される。
ア 不動産事業者による普及促進
都市部では一般的に賃貸住宅世帯が多く、それらへの住警器の普及が住宅火災による被害の低減の鍵となる。千葉市宅地建物取引業協同組合では、組合員である不動産事業者を対象に住宅火災の実態や住警器の設置義務化、奏功事例等を説明する研修会を開催し、意識啓発を図っている。また、住警器を設置した賃貸住宅には、それが一目でわかるステッカーを独自に作成して各戸の玄関に貼付する活動を行い、安全性をアピールすることで地域社会との信頼を築いている。

イ 身近な公共交通機関で住警器普及促進広報
関東バス株式会社では、東京都の荻窪消防署と連携して同署管内を運行する路線バス200台で住警器の普及を呼び掛ける車内広報を無償で実施した。車内にポスターの掲示、配布用リーフレットの設置を行うとともに、車内アナウンスでも住警器の設置を呼び掛けた。実施にあたっては乗客からの質問等に対応できるよう、住警器についての乗務員教育も行っている。
〔3〕 地域力を活かした取組の促進
住警器の普及には各地域・各主体の取組が必要不可欠である。このため、消防庁では、消防団や婦人(女性)防火クラブ、自主防災組織等のリーダーを対象として住警器の普及を呼び掛けるシンポジウムを全国各地域で開催している。シンポジウムでは、他地域での地域力を活かした先進的な取組事例の紹介も行っており、住警器の普及を推進するための知恵や工夫を参加者が持ち帰り、自分の地域での取組に活用することにより住警器の普及が加速することが期待される。
