5 大規模・高層建築物等の自衛消防力の確保
(1)大規模地震発生時等における建築物等の防災対策の課題
消防法では、一定規模の防火対象物に対して火災による被害防止を図るため、管理権原者(建築物の管理行為を法律、契約又は慣習上当然行うべき者。所有者や借受人が該当)が防火管理者を選任し、消防計画を作成させてこれに基づく消火、通報、避難の訓練実施等の防火管理業務を行わせることが義務付けられているが、地震災害を想定した計画の作成や訓練の実施の取組については義務付けられていなかった。また、自衛消防組織についても、これまで防火管理業務の一環として消防計画に定める事項の一つとされてきたものの、組織構成等の具体的内容に関しては関係者の自主的な取組に委ねられていた。このため、特に大規模・高層建築物等は、適切な対策が実施されていない場合の消防防災上のリスクが極めて大きいため、大規模地震に対する自衛消防力の確保を図ることは、喫緊の課題であった。
(2)大規模地震等に対応した自衛消防力確保のための消防法の改正
平成19年6月22日に消防法の一部を改正する法律が公布され(平成19年法律第93号。以下「平成19年改正消防法」という。)、平成21年6月1日から施行されることとなった。平成19年改正消防法では、消防法第36条により防火管理に関する規定が火災以外の災害にも準用されることとなり、一定の大規模・高層建築物等の管理権原者は、資格を有する者のうちから防災管理者を定め、地震災害に対応した消防計画を作成し、これに基づいて地震発生時に特有な災害事象に関する応急対応や避難の訓練の実施その他防災管理上必要な業務を行わせなければならないこととされた。また、新たに消防法第8条の2の5の規定が設けられ、一定の大規模・高層建築物等の管理権原者は、火災その他の災害による被害を軽減するために必要な業務を行う自衛消防組織を設置しなければならないこととされた。
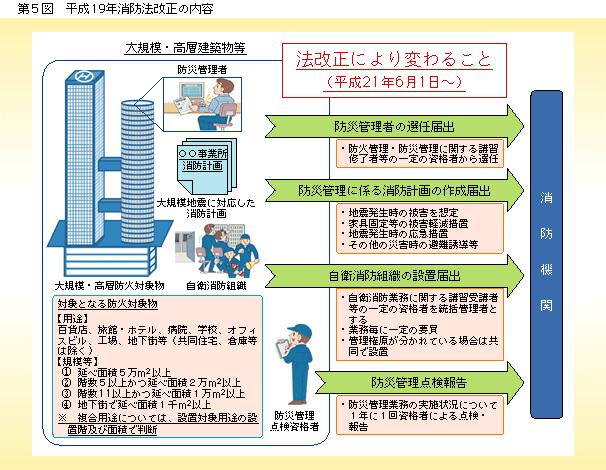
(3)今後の取組
平成19年改正消防法による大規模地震等への対応や自衛消防組織の設置等の取組が円滑に進められるために、消防庁が消防計画の作成主体である管理権原者・防災管理者と制度の運用に当たる消防機関双方への技術的支援を的確に実施することが重要である。
特に、消防計画の基本的な内容については、少なくともおおむね震度6強程度の地震による被害を想定し、これを踏まえて消防計画を作成する手順等についてとりまとめた消防計画作成ガイドラインを示しているところであるが、今後も特に災害想定手法、地震発生時の対応行動及び新たな訓練手法等について最新の知見を取り入れたものへと充実強化を図っていくことが必要である。
また、自衛消防についての優れた取組への表彰等により、防火対象物関係者の積極的な取組を促進し、自衛消防力の向上とともに地域貢献等による地域防災力の向上を図ることが重要である。
