2 火山災害対策の現況
(1) 国における火山災害対策
我が国には110の活火山が存在している。火山災害に結びつく危険性が高い火山現象は、噴石、火砕流、火山泥流、溶岩流、降灰、土石流、火山ガス、山崩れ及びそれに伴う津波など多岐にわたる。
火山災害に対しては、活動火山対策特別措置法等に基づいて諸対策が講じられており、消防庁では火山を有する地域の市町村に対して、避難施設の整備に要する費用の一部に国庫補助を行っている。
さらに、平成12年(2000年)の有珠山及び三宅島の火山災害を踏まえ、消防庁は平成13年から最新の火山防災に関する情報や関係団体で有する情報等を共有していくことを目的とした「火山災害関係都道県連絡会議」を開催している。
こうした中、火山災害の一層の軽減を図るため、平成19年12月に気象業務法の一部が改正され、重大な火山災害の起こるおそれのある旨を警告する「噴火警報」等の発表が開始された。加えて、火山活動の状況を関係地方公共団体や住民、登山者・入山者等が取るべき防災対応等に応じて5段階に区分した「噴火警戒レベル」が全国29火山(平成23年8月現在)を対象に運用されており(第1-8-1表)、今後その他の火山についても、噴火警戒レベルに応じた防災対応について、後述する火山防災協議会における共同検討が進められる予定である。
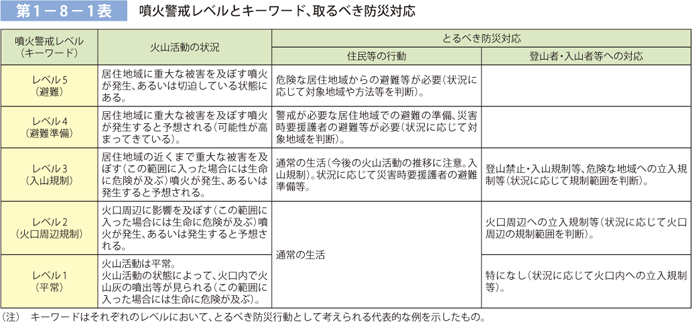
また、内閣府、消防庁、国土交通省及び気象庁では、平成20年3月、より効果的な火山防災体制を構築するための火山情報と避難体制について検討した結果を「噴火時等の避難に係る火山防災体制の指針」として取りまとめた。関係都道県及び関係市町村に対して、平常時における協議会等の開催、噴火時等の異常発生時における合同対策本部の設置、具体的で実践的な避難計画の策定、住民等への啓発等、指針を踏まえた火山防災対策の推進を要請している。
平成23年1月以降の霧島山(新燃岳)の噴火活動の活発化に当たっては、地方公共団体の取組のサポートのため、政府は「霧島山(新燃岳)噴火に関する政府支援チーム」を派遣した。また、霧島山(新燃岳)噴火に関する政府支援チーム、国土交通省宮崎河川国道事務所、宮崎県、鹿児島県により、関係県・市町、国の出先機関、火山の専門家等からなる「コアメンバー会議」が開催され、住民の避難計画、土石流対策、降灰対策計画等についての検討や情報共有が実施された。
また、土石流対策として、1月27日以降、警戒避難を支援するため、降灰等の調査・解析を行い、降雨時における土石流の想定区域及びその時期についての情報を市町に提供している。なお、5月1日の改正土砂災害防止法の施行後は、同法に基づく土砂災害緊急情報として通知を行っているところである。
(2) 地方公共団体における火山災害対策
ア 近隣地方公共団体や関係機関との連絡・協力体制の整備
火山の周辺にある地方公共団体や協議会では、噴火警報等の伝達、避難対策及び登山規制の実施等のため、広域的な連絡・協力体制が整備されている。現在、十勝岳、有珠山、北海道駒ヶ岳、樽前山、雌阿寒岳、草津白根山、雲仙岳、阿蘇山、九重山(硫黄山)の9火山の関係市町村では災害対策基本法に基づく地方防災会議の協議会が設置されており、これらのうち7つの火山においては、それぞれ噴火に関連する事前措置その他の必要な措置について、市町村相互間地域防災計画が作成されている。任意の協議会を含めると、25火山で協議会が設置され、情報共有、避難の対応等についての検討・調整等の連携体制が整備されている。
また、火山災害時に応急対策を迅速かつ的確に実施するため、火山周辺の地方公共団体においては、協議会等の場を通して、火山観測を行っている気象台、砂防部局、火山専門家のほか、警察、消防機関、自衛隊、海上保安庁等との連携が図られている。
イ 火山ハザードマップの作成、提供
火山が噴火した際にどの地域にどのような危険が及ぶのかを分かりやすく示した火山ハザードマップを協議会等において作成し、地域住民に配布することを通じて、防災情報を積極的に提供することが、平常時から住民に対して、防災意識の高揚を図ることにつながる。平成23年4月現在、全国の41火山において火山ハザードマップが作成されている。
消防庁では、有珠山の噴火や三宅島の火山活動を踏まえ、火山周辺の地方公共団体に対してハザードマップの作成を要請するとともに、平常時から住民に対して防災情報を積極的に提供し、防災意識の高揚を図る必要性を示している。
ウ 火山防災に関する計画の整備
火山の周辺にある地方公共団体では、火山の特性、地理的条件及び社会的条件を勘案して、噴火警戒レベルに応じた防災対応等、火山防災に関する計画を地域防災計画の中に整備することが重要である。平成23年4月1日現在、都道府県で14団体、市町村で115団体が地域防災計画の中で火山災害対策計画を別冊または独立した編、章として整備しており、最新資料の活用による計画の見直しも適宜行われている*1。
*1 東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び福島県のデータは除いた数値により集計している。
エ 避難体制の整備
ひとたび火山が噴火すると、噴石・火砕流・泥流等が短時間で居住地域に襲来する可能性がある。人命の安全確保のためには、事前に時間的余裕をもって避難勧告・指示が行われる必要がある。
地方公共団体では、住民に被害が及ぶおそれがあると判断される場合に、噴火警報の内容や噴火警戒レベルに応じ、避難勧告・指示を行えるよう、体制の整備が進められている。
オ 実践的な防災訓練の実施
火山の周辺にある地方公共団体では、消防機関をはじめとする防災関係機関との密接な連携の下、定期的に実践的な防災訓練が行われ、平成22年度は火山災害を想定した防災訓練が都道府県4団体で延べ5回、市町村では延べ48回実施されている。なお、その際には、関係地方公共団体による合同訓練も実施されている*2。
*2 東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び福島県のデータは除いた数値により集計している。
カ 住民や観光客への情報伝達体制の整備
噴火警報や、避難勧告、避難指示等の災害情報を確実かつ迅速に住民に伝達するためには、防災行政無線(同報系)の整備が非常に有効である。火山地域の市町村における防災行政無線(同報系)の整備率は、78.3%(平成23年3月31日現在)である*2。
*2 東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び福島県のデータは除いた数値により集計している。
また、観光客、登山者の立入りが多い火山にあっては、火山活動の状況に応じて発表される噴火警報に基づいて、登山規制、立入規制等の措置が取られ、観光客等への周知が図られている。
