5 主な課題と取組等
(1) 全国瞬時警報システム(J-ALERT)の整備・高度化
武力攻撃等の際に住民が適切な避難を速やかに行うためには、住民に正確な情報を迅速に伝達することが必要となることから、消防庁では、全国瞬時警報システム(以下「J-ALERT(ジェイ・アラート)」という。)の整備を推進している(第3-2図)。
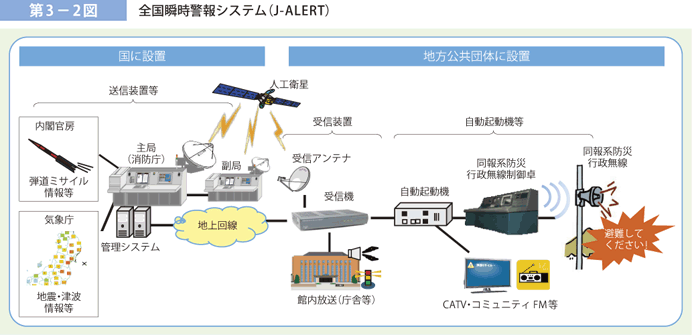
J-ALERTとは、弾道ミサイル攻撃に関する情報や緊急地震速報、津波警報、気象警報などの緊急情報を、人工衛星等を通じて送信し、同報系防災行政無線等を自動起動することにより、人手を介さず瞬時に住民等に伝達することが可能なシステムである。弾道ミサイル発射情報など国民保護に関する情報は内閣官房から、緊急地震速報、津波警報、気象警報などの気象情報は気象庁から、消防庁の送信設備を通じて全国の都道府県、市町村等に送信される。
J-ALERTは平成19年2月に10市町村で運用を開始し、平成21年度補正予算による交付金によってほぼすべての団体への一斉整備を進めるとともに、そのシステムの改修・高度化に向けた取組を行った。この結果、平成22年4月現在で395団体(46都道府県及び349市町村、整備率22.0%)であった運用団体は、平成23年6月現在で1,718団体(46都道府県及び1,672市町村、整備率99.1%(福島県及び福島県内の市町村は調査対象外))となっている。
高度化したJ-ALERTでは、地方公共団体が受信した緊急情報を同報無線等だけでなく他の防災システムと連携させることも可能となるため、消防庁としても、ファクシミリ、メールやケーブルテレビなど多様な伝達手段の活用について検討していくこととしている。
(2) 市町村における避難実施要領のパターンの作成
国民保護法では、市町村長は、住民に対して避難の指示があったときは、避難実施要領を定めなければならないと規定されている。この避難実施要領は、避難の経路、避難の手段等を定めるものであり、極めて迅速に作成しなければならないものであることから、その作成を容易にするため、基本指針では、市町村は複数の避難実施要領のパターンをあらかじめ作成しておくよう努めることとされている。
しかしながら、避難実施要領のパターンを作成済みの市町村は平成22年4月1日現在で3割程度にとどまっており、作成率の向上に向けた一層の取組が求められる。このため、消防庁としても、平成22年度に作成済み市町村の事例を取りまとめて都道府県に情報提供したほか、平成23年度は「「避難実施要領のパターン」作成の手引き」を作成し地方公共団体に配付するなど、都道府県と連携しながら作成の支援を行っている。
(3) 安否情報システムの運用
武力攻撃等により住民が避難した場合などにおいては、家族等の安否が確認できるようにすることが重要であり、国民保護法では、総務大臣及び地方公共団体の長は、武力攻撃事態等において、避難住民及び死亡又は負傷した住民の安否に関する情報を収集・整理し、国民からの照会に対し、速やかに回答することとされている。
このため、消防庁では、地方公共団体の職員等が避難所や病院などで収集した安否情報*4を、パソコンを使って入力でき、さらに全国データとして検索可能な形にできる「安否情報システム」を導入し、平成20年4月から運用を開始したところである(第3-3図)。平成22年3月には、情報入力や検索をより効率的に行えるようにするため、住民基本台帳カードとの連携やあいまい検索の機能を付加した。また、これに伴い、平成22年6月、安否情報システムを利用した安否情報事務処理ガイドライン(参照URL:http://www.fdma.go.jp/html/intro/form/pdf/kokuminhogo_unyou/kokuminhogo_unyou_main/anpi_Gaido.pdf)及び操作説明書を改正した。
*4 安否情報:氏名、出生の年月日、男女の別、住所、国籍、個人を識別するための情報等をいう。
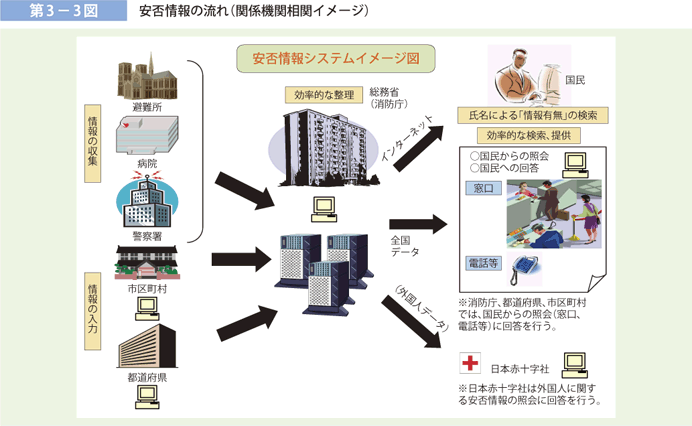
迅速・的確な安否情報の収集及び提供のためには、今後とも地方公共団体が安否情報を入力するための運用体制の強化を図ることが重要であり、消防庁では、警察・医療機関等の関係機関との協力体制の構築などの支援に取り組んでいる。加えて、平成22年6月から、消防庁の主導により仮想のデータを用いた安否情報システムの入力訓練を実施しており、各団体の積極的な訓練参加を促している。また、東日本大震災においても本システムを活用しており、今後、住民の避難情報を収集する全国避難者情報システムとの情報共有のあり方や大規模な自然災害における一層の効果的な運用について検討することとしている。
(4) 訓練
国民保護計画等を実効性のあるものとするためには平素から様々な事態を想定した実践的な訓練を行い、国民保護措置に関する対処能力の向上や関係機関との連携強化を図ることが重要である。
国民保護法においても、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれの国民保護計画又は国民保護業務計画で定めるところにより、それぞれ又は他の指定行政機関の長等と共同して、国民保護措置についての訓練を行うよう努めなければならないとされている。
このため、消防庁では、内閣官房等の関係機関と連携し、国と地方公共団体が共同で行う国民保護共同訓練の実施を促進するとともに、訓練を通じて事態対処法及び国民保護法等に基づく対応を確認し、その実効性の向上に努めている。国民保護共同訓練は、国民保護計画が全都道府県で作成された平成17年度に開始され、以降平成21年度までに、全ての都道府県において少なくとも一回実施されたところである。
平成23年度は、国民保護共同訓練としては、空港における爆破テロを想定した初めての実動訓練や、県境を越えた大規模な住民避難を想定した訓練等が計画されており(第3-1表)、今後も新たな要素を加味するなどしながら継続的に訓練を行うことが求められている。
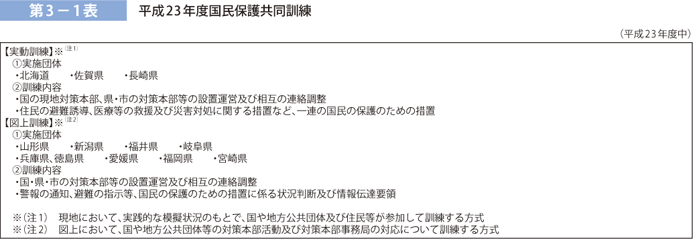
(5) 地方公共団体職員の研修・普及啓発
地方公共団体は、前述のとおり、国民保護措置のうち、警報の通知・伝達、避難の指示、避難住民の誘導や救援など住民の安全を直接確保する重要な措置を実施する責務を有している。これらの措置は関係機関との密接な連携の下で行う必要があり、職員には、制度全般を十分理解していることが求められる。
このため、職員に対する適切な研修等が重要であり、消防大学校においては、地方公共団体の一般行政職員、消防職員、消防団員等が危機管理や国民保護に関する専門的な知識を修得するためのカリキュラムとして危機管理・国民保護コースを設けている。都道府県の自治研修所や消防学校においても、国民保護に関するカリキュラムの創設等に積極的に取り組むことが望まれる。
また、国民保護措置を円滑に行うためには、消防団や自主防災組織をはじめとして住民に対しても、国民保護法の仕組みや国民保護措置の内容、避難方法等について、広く普及啓発し、理解を深めていただくことが大切である。
このため、消防庁では、啓発資料等として、これまでに、地方公共団体の担当職員や消防団・自主防災組織のリーダー向けに国民保護の基本的な仕組み、消防の役割、訓練のあり方等について、わかりやすく示した冊子やDVD等を作成し、地方公共団体が行う普及啓発活動に活用できるようにしている。
(6) 地方公共団体における体制整備
都道府県知事及び市町村長は、国民保護計画で定めるところにより、それぞれの区域に係る国民保護措置を的確かつ迅速に実施するために、夜間・休日等を問わずに起きる事案に的確に対応可能な体制等の必要な組織を整備することが求められるが、今日の地方公共団体には、国民保護関連事案に対する体制の整備はもとより、地震等の自然災害や新たな感染症など、住民の安心・安全を脅かす様々な危機管理事案に対しても、的確かつ迅速な対応が強く求められている。
このため消防庁では、平成18年度より「地方公共団体の危機管理に関する懇談会」を開催し、危機管理について知識・経験を有する有識者からの意見・助言をいただき、施策への反映に努めている。このほか、地方財政措置として、平成23年度も引き続き、国民保護対策関係職員の人件費を交付税算定上、基準財政需要額に計上するなど、地方公共団体の体制強化の支援にあたっているところである。
(7) 特殊標章等
指定行政機関の長、地方公共団体の長等は、武力攻撃事態等においては、指定行政機関や地方公共団体の職員で国民保護措置に係る職務を行う者又は国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者に対し、ジュネーヴ諸条約の追加議定書*5に規定する国際的な特殊標章(第3-4図)及び身分証明書(以下「特殊標章等」という。)を交付し、又は使用させることができる。これは、国民保護措置に係る職務を行う者等及び国民保護措置に係る職務のために使用される場所等を識別させるためのものである。この特殊標章等については、国民保護法上、みだりに使用してはならないこととされており、各交付権者においては、それぞれ交付対象者に特殊標章等を交付する際の取扱要領を定め、交付台帳を作成すること等により、特殊標章等の適正使用を担保することが必要である。
*5 ジュネーヴ諸条約の追加議定書:1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)第66条3
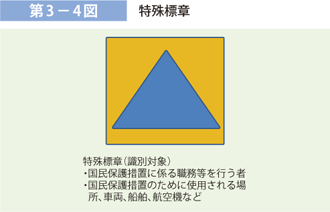
消防庁においては、関係省庁間の申合せ等を踏まえ、消防庁特殊標章交付要綱を作成し、地方公共団体や消防機関に対して、各交付権者が作成することとなっている交付要綱の例を通知するなど、特殊標章等が適正に取り扱われるよう取り組んでいる。
