第3章 消防庁・消防機関等の活動
第1節 政府の活動
政府においては、発災直後に官邸対策室を設置するとともに、関係省庁からなる緊急参集チームを招集した。3月11日15時には、緊急参集チーム協議が開始され、〔1〕被害情報の収集に万全を期すこと、〔2〕人命救助を第一義として、住民の避難、被災者の救援救助活動に全力を尽くすこと、〔3〕被害の状況に応じ、緊急消防援助隊、警察広域緊急援助隊、自衛隊の災害派遣部隊、海上保安庁の部隊、災害派遣医療チーム(DMAT)等による被災地への広域応援を行い、被災者の救援、救助をはじめとする災害応急対策に万全を期すこと等が確認事項として決定された。
同日15時14分には、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき、同法制定以来はじめて、緊急災害対策本部(本部長:内閣総理大臣)が設置され、第1回の対策本部会議では「災害応急対策に関する基本方針」が決定された(第3-1-1図)。
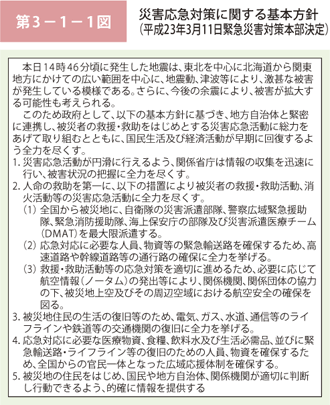
また、同日中、さらに2回の緊急災害対策本部会議が開催され、第3回緊急災害対策本部会議の後には、官房長官から「帰宅困難者の対策に全力をあげるため、駅周辺の公共施設を最大限活用するよう全省庁は全力を尽くすこと。」との指示がなされ、東京都を中心に所在する国の施設を帰宅困難者の一時滞在施設として開放するなどの対応が行われた。
発災当日の夜から翌朝にかけて、宮城県、福島県及び岩手県への政府調査団の派遣が次々と決定され、消防庁からも各県1名ずつ職員を派遣した。3月12日6時には、宮城県に政府現地対策本部が設置された。
東北地方太平洋沖地震の後に発生した静岡県東部を震源とする地震(3月15日発生)、宮城県沖を震源とする地震(4月7日発生)、福島県浜通りを震源とする地震(4月11日発生)及び福島県中通りを震源とする地震(4月12日発生)の発生直後にも、緊急参集チーム協議が行われ、被害情報の収集や人命救助に全力を挙げること等がその都度確認された。
一方、原子力災害への対応については、3月11日15時42分に東京電力(株)より福島第一原発において原災法第10条に基づく事象が発生したとの通報を受けて、官邸対策室を設置するとともに、既に地震の発生直後に招集されていた緊急参集チームを拡大し、協議を行った。その後、被害がさらに拡大し、東京電力(株)から原災法第15条に基づく事象が発生したとの通報を受け、11日19時3分内閣総理大臣は原子力緊急事態宣言を発令し、原災法制定以来はじめて、内閣総理大臣を本部長とする原子力災害対策本部及び原子力災害現地対策本部が設置された。
12日7時45分には、福島第二原発についても原子力緊急事態宣言が発令された。
