4.救助体制の課題
(1) 体制の整備
消防機関の行う救助活動は、火災、交通事故、水難事故、自然災害からテロ災害などの特殊な災害にまでおよぶものであり、消防庁ではこれらの災害に対して適切に対応できるよう所要の体制の整備を進めている。特に平成16年10月に発生した新潟県中越地震、平成17年4月に発生したJR西日本福知山線列車事故等を踏まえて全国的な救助体制の強化の必要性が高まり、平成18年4月に救助省令を改正し、新たに東京消防庁及び政令指定都市消防本部に特別高度救助隊を、また、中核市消防本部等に高度救助隊を創設した。これらの隊には従来の救助器具に加え、地震警報器や画像探索機などの高度救助用器具を備えることとし、関係消防本部において着実に整備が進められてきた。また、この特別高度救助隊及び高度救助隊の隊員の構成については、人命の救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた隊員で構成することとし、その隊員の教育を消防大学校や各都道府県、各政令指定都市の消防学校等における教育訓練に取り入れた。
(2) 車両及び資機材の整備
国内外においてテロの発生が危惧される中で、有毒化学物質や細菌等の生物剤、放射線の存在する災害現場においても迅速かつ安全な救助活動を行うことが求められている。こうした状況を踏まえ消防庁では、救助隊の装備の充実を図るため、消防組織法第50条(国有財産等の無償使用)に基づき、主要都市に特殊災害対応自動車や化学剤検知器など所要の車両及び資機材を配備している(第2-6-4表)。
また、大規模地震や特殊な事故に備え、同じく無償使用により、ウォーターカッター装置*2と大型ブロアー装置*3を搭載した特別高度工作車等の車両・資機材を配備している(第2-6-4表)。
*2 ウォーターカッター装置:研磨剤を含む高圧の水流により切断を行う器具。切断時に火花が発生しないため危険物や可燃性ガスが充満した場所でも使用可能
*3 大型ブロアー装置:車両積載の高性能大型排煙機。排煙と同時に噴霧消火等も可能
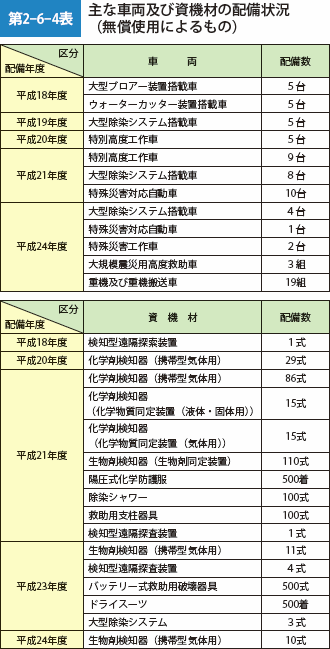
さらに、東日本大震災において、津波が引いた後の泥水中での活動が求められたことや、がれきに阻まれて大型の救助資機材を搬送することが困難であったこと等を踏まえて、ドライスーツ、小型・軽量のバッテリー式救助用破壊器具等を整備するとともに、重機*4及び重機搬送車並びに大規模震災用高度救助車*5を配備し、緊急消防援助隊の充実強化を図っており、各消防本部では、これらの資機材等を活用した訓練が実施されている。
*4 重機:がれき、土砂等の障害物を除去することにより、道路の啓開、救助隊等と連携した効果的な救助活動を行う。
*5 大規模震災用高度救助車:大規模震災時において、活動が困難な救助現場に対処するため、圧縮空気を動力源とした破壊工作器具や小型・軽量・高性能な救助資機材を積載した走破性の高い四輪駆動タイプの救助活動用の車両
(3) 救助技術の高度化等
多様な救助事案に全国の消防本部が的確に対応しうることを目的に、救助技術の高度化等を推進するため、「救助技術の高度化等検討会」(第1回開催:平成9年度(1997年度))及び「全国消防救助シンポジウム」(第1回開催:平成10年度(1998年度))を毎年度開催している。平成26年度は、近年、異常気象に伴う大規模な気象災害(豪雨、土砂災害等)が頻発していることを踏まえ、気象災害への対応力の強化を図ることを目的として、それぞれ実施している。
救助技術の高度化等検討会のテーマは、「土砂災害時の救助活動のあり方」である。
大規模な土砂災害の救助活動においては、二次災害の危険性が高い中で、長時間にわたり広範囲におよぶ活動が必要であり、また、その実施においては、救助機関、医療機関、土木担当部署等との緊密な連携が不可欠となるが、このような救助活動の手法は現在のところ標準化されておらず、過去の活動の教訓等も体系的に整理されていない。
このため、平成26年8月に発生した広島市土砂災害などの実災害での経験を踏まえ、国内外の先進的な取組も参考としつつ、大規模な土砂災害での救助活動を安全かつ効率的に実施するための活動要領の策定に向けた検討を行っている。
一方、全国消防救助シンポジウムは、テーマを「頻発する気象災害への対応能力の向上を目指して」とし、気象災害にいかに対処していくべきかについて、専門家による講演や消防本部による事例研究発表、パネルディスカッションを行い、全国の消防本部の経験・知見・技術を共有することにより、対応能力の向上に資する機会とする。
