3 消防と医療の連携推進
(1)消防と医療の連携推進
全国各地で救急搬送時の受入医療機関の選定に困難を来す事案が報告されたことから、消防庁では、平成19年10月に産科・周産期傷病者搬送の受入実態について調査を行い、結果を公表するとともに、平成20年3月に産科・周産期傷病者に加え、重症以上傷病者、小児傷病者、救命救急センター等への搬送者に関する搬送の受入実態についての調査を行い、結果を公表したところであり、これらの傷病者の搬送における受入医療機関の選定が、大変厳しい状況にあることが明らかとなった(第2-4-7表、第2-4-8表)。
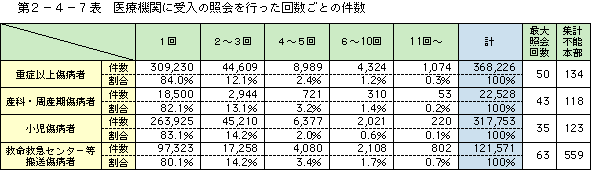
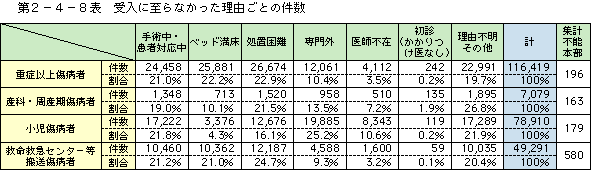
このような状況を踏まえ、消防庁では、円滑な救急搬送・受入医療体制の確立を目指すため、平成19年に「消防機関と医療機関の連携に関する作業部会」を開催し、平成20年度も継続して検討を行っている。同作業部会では、平成19年度の検討成果として、早急に講じるべき対策等について中間報告を取りまとめた。
早急に講じるべき対策としては、救急搬送の適切な実施を確保するためには、医療機関による救急医療情報システムへの情報の迅速・正確な入力、救急隊による正確な傷病者観察とそれに基づいた適切な医療機関選定・情報伝達、コーディネーターによる受入調整、救急搬送に関する検証・協議の場の設置等が必要であるといった指摘がなされた。
消防機関、医療機関が連携した検証・協議の場としては、メディカルコントロール協議会の活用が考えられるところであり、その位置づけの強化について、平成20年度、「救急業務高度化推進検討会」のもとに「メディカルコントロール作業部会」を開催し、具体的に検討を進めている。
また、消防庁では、市民が救急車を呼ぶべきかどうか迷った場合に、24時間365日相談できる窓口の消防機関への設置を推進していくこととしている。
(2)救急医療体制
傷病者を受け入れる救急病院及び救急診療所の告示状況は、平成20年4月1日現在、全国で4,370箇所となっている(附属資料36)。
また、厚生労働省では、傷病の重症度に応じて、多層的に救急医療体制の整備強化が進められている。
初期救急医療体制としては、休日、夜間の初期救急医療の確保を図るため休日夜間急患センターが511箇所(平成19年3月末現在)で、第二次救急医療体制としては、病院群輪番制方式及び共同利用型病院方式により418地区(平成19年3月末現在)で、第三次救急医療体制としては、救命救急センターが210箇所(平成20年7月末現在)で整備されており、また、広範囲熱傷、指肢切断、急性中毒等の特殊疾病傷病者に対応できる高度救命救急センターは、そのうち21箇所(平成20年7月末現在)で整備されている。
救急告示制度による救急病院及び診療所の認定と初期・第二次・第三次救急医療体制の整備については、都道府県知事が定める医療計画のもとで一元的に実施されている。
