2 危険物施設の事故防止対策の推進
(1)危険物事故の動向と調査体制の整備
危険物施設(火災危険性の高い物質として消防法で規制されるガソリンや軽油などの「危険物」を、指定数量以上貯蔵し又は取り扱う製造所、貯蔵所及び取扱所)で発生した火災・流出事故は、平成6年まで減少傾向を示したが、平成7年から増加傾向に転じ、平成19年中の発生件数は、火災が169件、流出事故が443件と、平成6年と比べて火災が約1.5倍、流出事故が約2.5倍になり、統計を取り始めてから過去最多となった。
このような危険物事故の増加傾向を踏まえると、大規模地震発生時に、危険物施設における危険物流出事故や施設の破損事故等に起因する火災・爆発の災害が発生する可能性は高まっているといえる。そのような災害による被害を防止するためには、平時からの危険物流出等の事故防止対策が必要であり、その第一歩として、それぞれの事故原因を精確に調査し、その結果の蓄積・分析に基づく危険物に係る技術基準の見直しや施設点検技術の向上など、的確な事故防止対策につなげることが不可欠である。
しかし、これまで消防機関による火災原因調査の制度はあったが、火災にまで至らない危険物流出等の事故についての原因調査の制度が未整備であったため、精確な原因調査を行政機関が行うことは困難であった。
そこで、危険物施設における危険物流出等の事故の原因を効果的・効率的に究明できるよう、平成20年8月に改正消防法が施行され、火災にまで至らない危険物の流出等の事故について、危険物施設に対する許可を行う市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)が原因調査を行うことができるようになった。
(2)危険物流出等の事故の原因調査制度の概要
ア 市町村長等による原因調査
危険物施設で発生した、火災にまで至らなかった危険物の流出等の事故について原因調査を実施するため、市町村長等は、事故が発生した危険物施設や、その事故の発生と密接な関係があると認められる場所の所有者、管理者又は占有者に対して資料の提出を命じ、又は報告を求めることができ、また、職員にこれらの場所に立ち入らせ、所在する危険物の状況や当該危険物施設など事故に関係のある工作物や物件を検査させ、関係のある者に質問させることができる。
イ 消防庁長官による原因調査
市町村長又は都道府県知事は、自らの調査体制では事故の原因究明が困難な場合などに、消防庁長官による事故の原因調査を求めることができる。消防庁長官は市町村長又は都道府県知事からの求めに応じて、市町村長等が事故の原因調査を行う場合と同様の権限を行使して、事故の原因調査を実施できる。
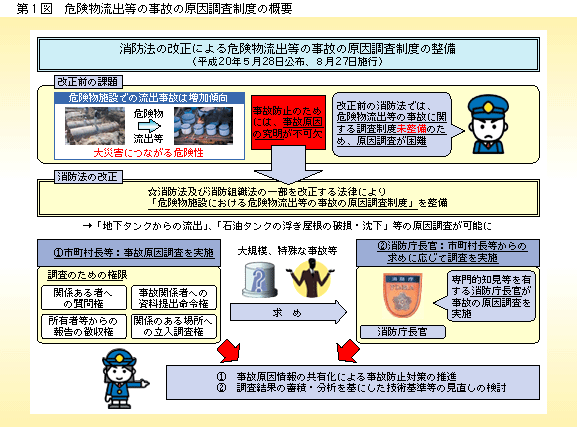
(3)危険物事故の防止に向けて
新たに整備された危険物流出等の事故原因調査制度の活用により、個別の事故の精確な原因を把握し、調査結果を蓄積・分析して、より的確な事故防止対策の企画・立案につなげることが重要である。
消防庁では、各消防機関が効率的・効果的に事故調査を行う上での参考とすることや、調査を実施する消防職員を養成するための都道府県消防学校等での教育における活用等も期待して、危険物流出等の事故原因調査マニュアルを作成・配布するとともに、消防大学校における教育カリキュラムの見直しを進めているところである。今後、原因調査を通じて得られた知見が多方面で効果的に活用されるよう、オンラインによる情報共有化の取組や、必要な技術基準の見直しの検討等を行い、消防機関のみならず、官民一体となった事故防止対策を推進していくこととしている。
