2 各都道府県の推進計画の概要~将来の消防本部~
各都道府県においては、基本指針に基づき、平成19年度中に推進計画を策定することとされており、期限とされていた平成20年3月末時点では、30団体が推進計画の策定に至った。平成20年3月末時点で推進計画未策定の17団体においても関係者の合意形成を図りながら実現可能性のある推進計画の策定に向けて取り組んでいるところであり、平成20年11月1日現在では、38団体において推進計画が策定されている。以下、平成20年11月1日時点で策定されている38都道府県の推進計画に示されている広域化によって将来見込まれる消防本部の姿について概説する。
(1)消防本部の規模
消防本部の数は673本部から184本部へと約7割減少し、各消防本部の管轄人口に着目すると、管轄人口が30万人未満の消防本部の比率が減少する一方、管轄人口が30万人以上の消防本部の比率が大幅に増加する見込みである(第1表参照)。
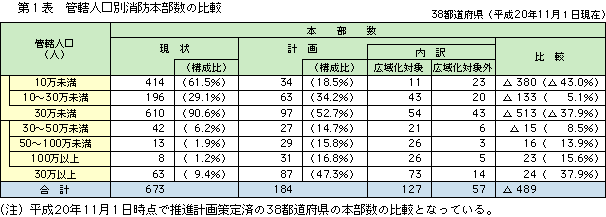
これまで、小規模消防本部とされてきた管轄人口10万人未満の消防本部は414本部から34本部に大きく減少し(減少率は91.8%)、全消防本部に占める構成比は61.5%から18.5%にまで下がる見込みである。
また、基本指針においては、管轄人口の観点から言えば、おおむね30万人以上の規模を目標とすることが適当とされていたところであるが、管轄人口30万人以上の消防本部は63本部から87本部に増加し(増加率は38.1%)、全消防本部に占める構成比は9.4%から47.3%へと上昇し、消防本部の約半数は、管轄人口30万人以上となる見込みである。
さらに、管轄人口100万人以上の消防本部は8本部から31本部となり、4倍近くに増加する。
なお、管轄人口100万人以上の消防本部の区域内人口は現在の約2,600万人から約5,900万人(38都道府県の人口約1億400万人の約56.7%)となり、住民の約6割は、現在の政令指定都市並みの規模の消防本部の管轄下に入る見込みである。
(2)都道府県全域を管轄区域とする消防本部
都道府県ごとの広域化後の消防本部数は、各地域の特性等に応じて様々であるが、県全域を管轄する1つの消防本部(以下「県域消防本部」という。)の設置を計画する都道府県は、12団体に及んでいる。また、今回の期限内(平成24年度まで)では、県域消防本部となっていなくとも、将来は県域消防本部を目標とする、あるいは、望ましいとしている推進計画も複数見受けられるところである。
(3)広域化する消防本部の数
今回の計画で広域化の対象となっている消防本部の数は、38都道府県の673本部中、616本部であり、91.5%の消防本部が広域化の対象となっている。また、38都道府県のうち、21の都道府県においては、県内のすべての消防本部が広域化の対象となっている。
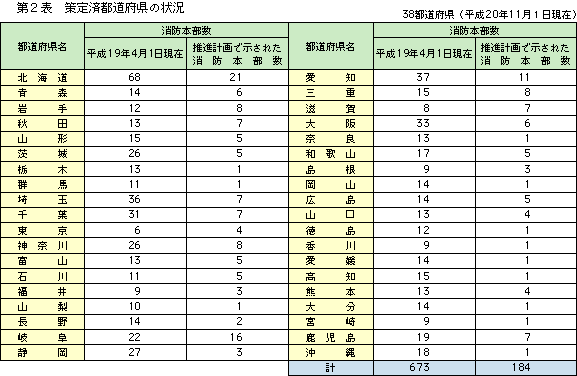
(4)非常備町村の常備化
平成20年4月1日現在、全国で12都府県40町村あった非常備町村は、11府県34町村において解消されることとなり、離島にある一部の町村を除いては、消防の常備化が達成されることとなる。
