トピックスIII 消防と医療の連携の推進~迅速な救急搬送を確保するために~
1 救急業務の現状
救急業務は、国民の生命・身体を事故や災害等から守り、安心・安全な社会を確保するものであり、我が国においては、昭和38年に法制化されて以来、国民にとって必要不可欠な行政サービスとして定着している。
現在、少子高齢化社会の進展や住民意識の変化及び核家族化等に伴って救急需要が拡大しており、平成19年中の救急出場件数は約529万件で、平成9年からの10年間で約52%増加している。一方で、全国の救急隊数は、平成10年からの10年間で約8%の増加にとどまっている(第1~3図参照)。
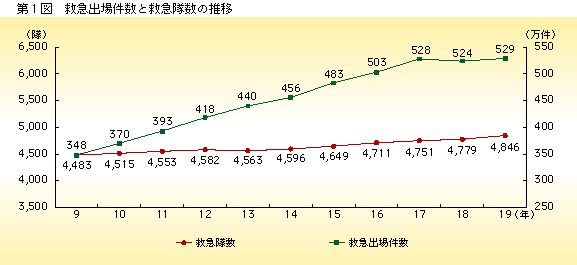
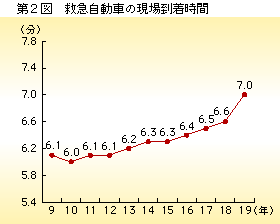
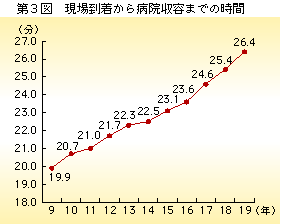
このため、緊急性のある傷病者の搬送には、迅速かつ的確な対応が必要とされるにもかかわらず、救急隊の現場到着時間は平成9年の平均6.1分に対し、平成19年では7.0分であった。また、現場到着から病院収容までの時間は平成9年の平均19.9分に比べ、平成19年では26.4分と遅延傾向にあり、特に心肺機能停止状態の傷病者の発生など一刻を争う局面においては、今後、地域によっては、救急隊の到着が遅れるおそれがあり、深刻な問題となっている。
このような現状を受け、消防庁においては、「救急搬送業務における民間活用に関する検討会」(平成17年度)や「救急需要対策に関する検討会」(平成17年度)を開催し、救急需要対策について総合的な検討を行うとともに、「救急業務におけるトリアージに関する検討会」(平成18年度)を開催し、119番通報受信時における緊急度・重症度の選別(コールトリアージ)について検討を加えた。平成20年度は、これらの検討を踏まえ改良されたトリアージプロトコル(トリアージの運用要領)に基づき、4消防本部で実証検証を行うなどコールトリアージの導入に向けた具体的な取組を進めている。
