2 救急搬送における医療機関の受入状況
全国各地で救急搬送時の受入医療機関の選定に困難を来す事案が報告されたことから、消防庁では、平成19年10月に産科・周産期傷病者搬送の受入実態について調査を行い、結果を公表した。また、平成20年3月には、
〔1〕重症以上傷病者搬送事案
〔2〕産科・周産期傷病者搬送事案
〔3〕小児傷病者搬送事案
〔4〕救命救急センター等搬送事案
に調査対象を拡大し、平成19年中の受入れ実態について調査を行い、結果を公表した。
当該調査によって、例えば〔1〕の重症以上傷病者搬送事案において、医療機関に受入れの照会を4回以上行った事案が14,387件あること、地域別の状況をみると、首都圏、近畿圏等の大都市周辺部において照会回数が多く、4回以上の事案の占める割合が全国平均(3.9%)を上回る団体(10都府県)における4回以上の事案数が、全国の事案数の85%を占めるなど、選定困難事案が一定の地域に集中して見られる傾向があることが判明した。また、受入れに至らなかった主な理由としては、処置困難(22.9%)、ベッド満床(22.2%)、手術中・患者対応中(21.0%)等の理由が挙げられた。
さらに3次救急医療機関と2次以下の救急医療機関における受入れに至らなかった理由の割合について、これらを区分して集計することが可能であった7都県において分析を行ったところ、3次医療機関で受入れに至らなかった理由において、「ベッド満床」が37.8%、「手術中・患者対応中」が34.5%と高いのに対し、2次以下の医療機関では「処置困難」が39.0%と高く、両者において受入れに至らなかった理由の傾向が異なることが明らかになった(第4図参照)。
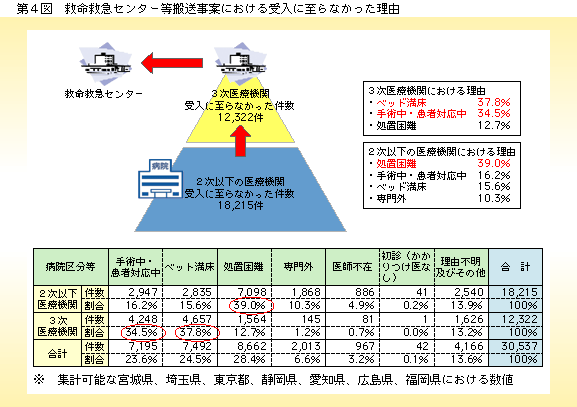
救急搬送における受入医療機関の選定が、大変厳しい状況にあることを踏まえ、消防庁では、平成19年度に「消防機関と医療機関の連携に関する作業部会」を「救急業務高度化推進検討会」に設け、平成20年度も引き続き、円滑な救急搬送・受入医療体制を確保するための対策について検討を行っている。
