特集 消防と医療の連携の推進 ~消防と医療の連携による救急搬送の円滑化~
1 はじめに
救急業務は、国民の生命・身体を事故や災害、疾病等から守り、安心・安全な社会を確保するものであり、国民にとって必要不可欠な行政サービスとして定着している。
近年、医療の進歩とともに、傷病の発生初期に実施すると効果的である医療技術が発達し、救急搬送における病院選定から医療機関における救急医療の提供までの一連の行為を円滑に実施することが、傷病者の救命率の向上及び予後の改善等の観点から、重要な課題とされている。このため、消防庁としては、救急救命士を含む救急隊員により実施される救急業務の高度化、医学的な観点からの質の向上に向けて取り組んでいる。

少子高齢化、核家族化の進展や住民意識の変化等に伴い、救急需要が増加し、平成20年中の救急出場件数は約510万件で、平成10年からの10年間で約38%増加している。また、救急搬送に長時間を要した事案も発生しており、平成20年中の救急隊の現場到着時間は平均7.7分で平成10年の平均6.0分に対し1.7分長くなり、病院収容時間は平成20年において平均35.0分で平成10年の平均26.7分に対し8.3分長くなるなど、遅延傾向にある。
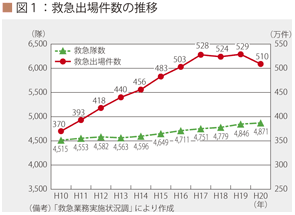
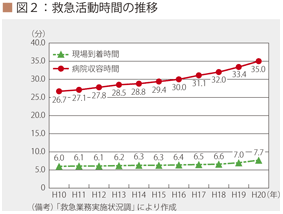
このような中、平成18年及び平成19年に奈良県(大淀町、橿原市)で、平成20年に東京都(江東区、調布市)で発生した妊婦の救急搬送事案など傷病者を受け入れる医療機関が速やかに決まらない事案(以下「受入医療機関の選定困難事案」という。)が発生しており、国民の安心・安全確保の観点から、円滑な救急搬送及び受入れの体制を構築し、受入医療機関の選定困難事案を解消することは喫緊の課題となっている。
