[危険物行政の課題]
(1)官民一体となった事故防止対策の推進
危険物施設の火災及び流出事故は、平成6年(1994年)頃を境に増加傾向に転じ、平成21年には平成6年(1994年)を中心とした5年間(平成4年(1992年)から平成8年(1996年))の平均331件の約1.6倍となる件数にまで増加している。このような状況を踏まえ、関係業界や消防機関等により構成される「危険物等事故防止対策情報連絡会」において策定された「危険物事故防止アクションプラン」(消防庁ホームページ参照 URL:http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi2203/pdf/220325_ki45.pdf)に基づいて、事故に係る調査分析や事故防止技術の調査研究、各種情報の共有化を進めるとともに、各都道府県における事故防止の取組など、官民一体となって事故防止対策を推進していく必要がある。
また、産業災害の背景要因として、人員や設備投資等の削減、雇用形態の変化や保守管理業務のアウトソーシング等が指摘されていることから、幅広い視点からの実態の把握による対策を講じ、各事業所の実態に応じた安全確保を図るため、危険要因を把握して、これに応じた対策を講ずることが必要である。
(2)腐食等劣化への対策
近年の流出事故増加については、危険物施設の老朽化等に伴う腐食等劣化が大きな要因となっている。このような流出事故を未然に防止するため、地下タンクの流出危険性に応じ、腐食防止・抑制対策を講ずることが消防法令に新たに規定された。このことを踏まえ、制度の周知を図り、腐食防止・抑制対策の早期実施を推進していく必要がある(P.72囲み記事「地下タンクの危険物流出事故防止対策」参照)。
(3)科学技術及び産業経済の進展等を踏まえた安全対策の推進
近年、科学技術及び産業経済の進展に伴い、危険物や指定可燃物と同様の性状を有していながらその潜在的危険性が認識されていない新規危険性物質の出現、危険物の流通形態の変容、危険物施設の大規模化、多様化、複雑化、新技術の開発など、危険物行政を取り巻く環境は大きく変ぼうしている。
こうした状況に的確に対応するため、新規危険性物質についての早期把握や必要に応じた危険物規制に関する技術基準の見直しを引き続き図るとともに、温室効果ガス削減のため、次世代自動車である電気自動車や燃料電池自動車の普及に向け、電気自動車の急速充電設備や燃料電池自動車の水素充てん設備がガソリンスタンドに設置される場合の安全対策について、新技術の導入を踏まえ、必要に応じ見直していく必要がある。
(4)屋外タンク貯蔵所の安全対策
大量の危険物を貯蔵し又は取り扱う屋外タンク貯蔵所において流出事故が発生した場合には、周辺住民の安全や産業及び環境に対して多大な影響を及ぼすおそれがあることから、その安全対策は重要な課題である。容量1万kl(キロリットル)以上の液体の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱う屋外タンク貯蔵所は、消防法令の規定により、一定期間ごとに市町村長等による検査を受けることとされている。検査は屋外タンク貯蔵所から危険物を全て取り除き、タンクの劣化状況を調べ構造が消防法令に適合していることを確認するものであるが、管理経費削減の観点から検査の周期を延長することが要請されており、消防庁ではこの検査の周期について検討をしている(P.15トピックス「屋外タンク貯蔵所の保安検査の周期についての調査検討」参照)。
また、固定された屋根を持つ屋外タンク貯蔵所のなかには、貯蔵物の蒸発の抑制や品質保持のために、液面上に浮体(「内部浮き蓋」)を浮かべてあるものがある(以下「内部浮き蓋付き屋外貯蔵タンク」という。)。近年、このような内部浮き蓋付き屋外タンク貯蔵所において、地震等に伴う液面揺動に起因すると考えられる内部浮き蓋の沈下、傾斜、損傷等の事故が発生している。消防庁では、内部浮き蓋に係る耐震性の評価など必要な安全対策について検討している。
地下タンクの危険物流出事故防止対策
危険物施設における危険物の流出事故件数は、最近5年間(平成17年(2005年)から平成21年(2009年))の平均が389件で、総事故件数の最も少なかった平成6年(1994年)を中心とした5年間(平成4年(1992年)から平成8年(1996年))の平均205件と比較して約1.9倍と、高い水準で推移しています。特に、流出事故原因のうち物的要因に着目した場合、施設の老朽化による腐食等劣化に起因する事例が最も多くなっています。
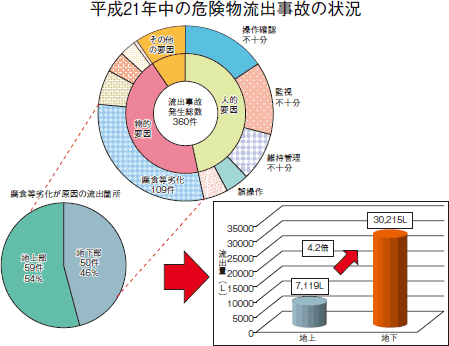
このうち、地下に埋設されている地下タンク等では、腐食等劣化の進行状況を直接目で確認することができず、また、仮に危険物の流出が発生した場合、その発見が遅れ、多量の危険物が周囲に流出する危険性を有しています。
そこで、平成22年6月に危険物の規制に関する規則等を改正し、地盤面下に直接埋設された地下タンクのうち、設置年数、塗覆装(地下タンクの外面を保護しているアスファルトなどの被覆)、板厚が一定の要件を満たすものについて、「腐食のおそれが特に高い地下タンク」又は「腐食のおそれが高い地下タンク」として区分し、下図のとおり当該区分に応じた、内面コーティング又は電気防食等の流出事故を未然に防止するための対策を講ずることとされました。
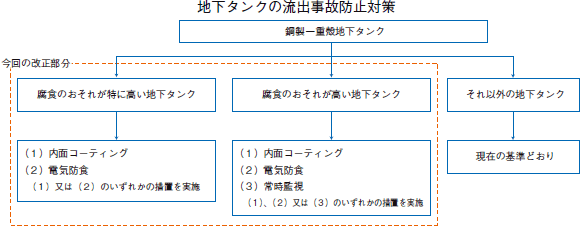
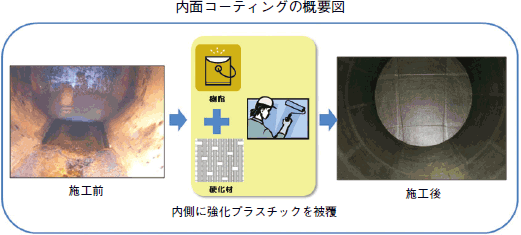
地下タンクの流出事故防止対策に係る改正については、平成25年2月1日より規定が適用されますが、流出事故時の被害の大きさにかんがみれば、できるだけ早い時期に対策を講ずることが望まれます。
