3 危険物施設の被害
(1) 危険物施設の被害概況
消防庁が行った調査によると、東日本大震災によって被害を受けた危険物施設(以下「被災施設」という。)数は3,341施設であり*1、調査対象地域における危険物施設数(211,877施設*2)の1.6%で被害が発生している。被災施設のうち、地震による被害を受けた被災施設数は1,409施設(被災施設の42%)、津波による被害を受けた被災施設数は1,821施設(同55%)であった(第2-2-1図)。なお、都道府県別の被害状況については第2-2-2図のとおりである。
*1 消防庁が平成23年5月から8月の間に、東日本大震災で特に被害を受けたと考えられる16都道県(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県)を対象に行った調査結果に基づいている。調査を行った地域のうち、福島第一原子力発電所の周辺地域については調査が困難であるため、被害状況は不明である。また、山梨県における危険物施設の被害はなかった。
*2 平成22年3月31日現在
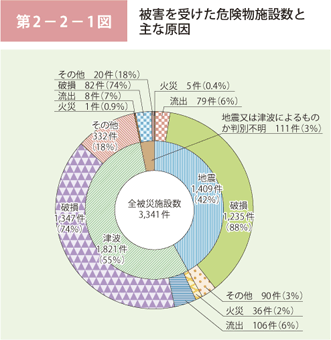
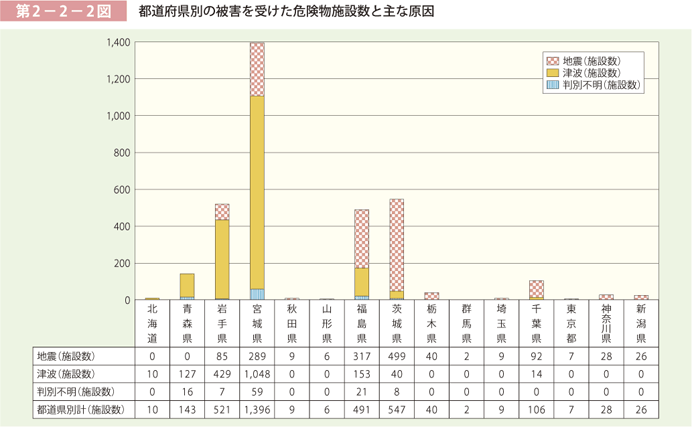
(2) 危険物施設の原因別被害状況
ア 地震による被害の状況
地震による被害を受けた被災施設(1,409施設)の被害*3の主な内訳は第2-2-4表のとおりである。
*3 調査では、危険物施設が受けた被害を以下のように区分している。
火災:危険物施設から出火した場合
流出:危険物施設から危険物が漏えいした場合(容器等からの漏えいも含む。)
破損:危険物施設の設備等の破損(防火塀や防油堤、建築物の破断等)や、危険物が入った容器等が施設外に流出した場合。
その他:火災、流出、破損に分類できない被害
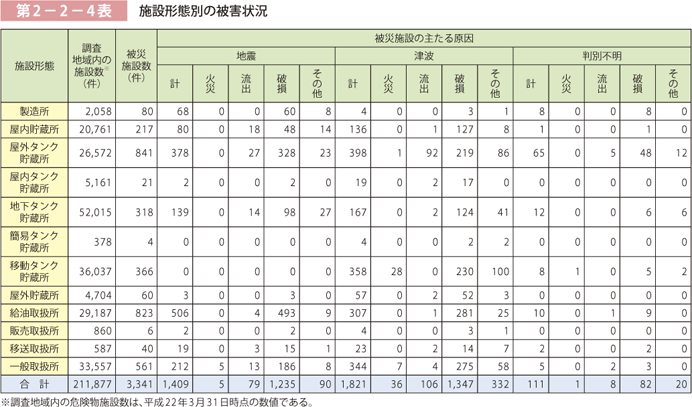
地震による火災は全て一般取扱所で発生しており、うち2件が危険物に起因するものであった。また、地震による流出の主な原因は、配管の破損のほか、屋外タンク貯蔵所における浮き屋根や浮き蓋の配管等の破損、屋内貯蔵所における容器の落下等が挙げられる。
イ 津波による被害の状況
津波による被害を受けた被災施設(1,821施設)の被害の主な内訳は第2-2-4表のとおりである。
津波による火災36件は、全て同一の製油所で発生したものである。また、津波による流出の主な原因は、配管やポンプ設備等の破損であった。
