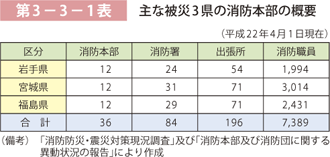第3節 被災地域の消防機関の活動
1 初期の状況
地震の発生とともに、被災地域の各消防本部では早期に初動対応を行い、全職員による災害対応体制の確立に努めた。沿岸部の消防本部の多くは、過去の災害経験から、津波災害に関する活動計画を定めており、津波被害の想定をもとに訓練を実施していたが、想定を大きく超えた規模の津波により、消防本部の活動は困難を極めるものとなった。
災害通報については、地震被害が甚大であった地域の消防本部では地震直後から119番通報が絶え間なく入電され、鳴り続ける通報の対応に追われた。津波被害を受けた沿岸部であっても、地震の揺れによる被害が少なかった地域では、地震直後は119番通報が普段と同程度しか入電しなかったが、津波襲来後は、119番通報が絶え間なく入電する状況となった。また、沿岸部の消防本部においては、津波等により被害を受けた公衆通信網の中継局もあるため電話回線が途絶する地域もあり、一定期間119番通報の受信が止まった消防本部もあったため、高所見張りをはじめ、消防車両による広報活動や関係機関等との連絡により、早期の災害覚知に努めた。119番受信内容にあっては、地震直後には救急、救助、火災及びガス漏れ等の災害通報が続いたが、沿岸部の本部では津波発生後、救助の要請が後を絶たず、多くの要救助者が発生しているという内容を受信している。
これらに対処するため、災害受信件数が膨大であった消防本部においては、受信内容に応じて優先度の判定が行われ、また、部隊運用を消防指令センター(本部)から消防署へ切り替えて実施するなど、同時多発する災害への対応に追われた。
災害対応体制については、各消防本部において地震直後から対策本部を設置し、勤務時間外職員の招集により消防力の増強に努めた。数分間に及ぶ地震動により庁舎の停電が発生したことから、非常用自家発電機を稼働させ、必要最低限の電源を確保したが、不安定な電圧により通信機器が故障し、災害対応に支障をきたした事例も見られ、さらには、自家発電機の使用が長期化することとなり、燃料確保に苦慮する事態が発生した。