第2節 福山市ホテル火災を踏まえた防火安全対策
(1) 広島県福山市ホテル火災の概要
平成24年5月13日早朝、広島県福山市のホテルにおいて、死者7名、負傷者3名(うち従業員1名)という重大な人的被害を伴う火災が発生した。7名の死者が発生したホテル火災は、昭和61年の静岡県東伊豆町における火災(死者24名)以来である。
消防庁では、消防法第35条の3の2の規定に基づく消防庁長官の火災原因調査を実施するため、現地に職員を派遣し、福山地区消防組合消防局と連携して火災原因調査を行った。
火災の発生した建物は、昭和35年に木造2階建てが建築され、昭和43年に別棟として鉄筋コンクリート造4階建てが建築され、その後、木造部分と鉄筋コンクリート造部分が一体利用され、建築基準法違反の建築物となっていた。建築基準法に適合していない項目として、建築構造の不適、階段の防火区画(たて穴区画)の未設置など、8項目が指摘されている。
また、消防法上の不備事項としては、平成15年の最終査察時に消防用設備等の点検報告の未報告や自衛消防訓練の未実施、屋内消火栓の一部不備が指導されており、これら3項目を同時に指導した回数は昭和56年から25回に上っている。

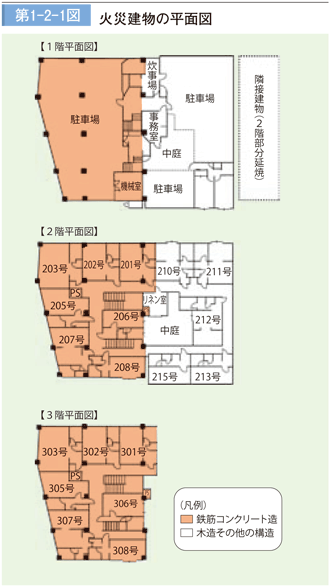
(2) 全国のホテル等に対する緊急調査の結果
この火災を踏まえ、全国の消防本部において、3階建て以上で防火管理者の選任義務を要するホテル・旅館等のうち、昭和46年以前に建築されたもの(現行の建築基準法の建築構造、防火区画及び階段の規定に適合しているものを除く。)について、建築部局と連携を図り緊急調査を行った。緊急調査を実施した797施設のうち、549施設(68.9%)において何らかの消防法令違反が発見された。このうち自動火災報知設備が過半にわたり未設置など重大な違反があるものは、47施設(5.9%)となっている(第1-2-1表、第1-2-2表)。
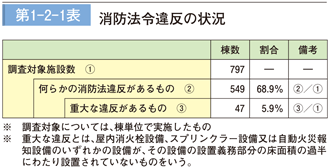
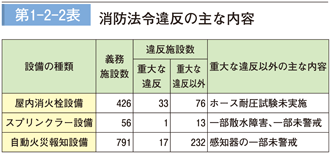
緊急調査結果において消防法令違反のあるものについては、消防本部において重点的に是正の徹底を図ることとしている。
(3) ホテル火災を踏まえた検討
このホテル火災を踏まえ、消防庁では「予防行政のあり方に関する検討会」の下に有識者から構成される「ホテル火災対策検討部会」を発足させ、ホテル・旅館等の火災被害拡大防止対策及び火災予防行政の実効性向上等に関する検討を行った。
本検討部会では、中間報告においてホテル・旅館等における火災予防上の課題及び対応の考え方について提言が取りまとめられている(平成24年10月10日公表、消防庁ホームページ参照 URL:http://www.fdma.go.jp/)。
(4) ホテル・旅館等における火災予防上の課題及びその対応の考え方
ホテル火災対策検討部会の中間報告の概要は以下のとおりである。
消防庁においては、これを踏まえ、関係機関とも連携しながら、実施に向けた検討を進めている。
ア 多数の死者、負傷者の発生した要因について
出火原因等を含め、調査を継続しているところであるが、この火災における多数の死者、負傷者が発生した被害拡大の要因として以下の事項が考えられる。
● 建築物の構造が耐火構造でないことから、出火室及びその近傍において、火災が上階に燃え抜けて拡大したこと。
● 階段部分の防火区画(たて穴区画)が設けられておらず、火災や煙が階段を経由して上階に拡大し、煙が各客室に流入したこと。
● 消火器及び屋内消火栓設備を用いた消火活動が行われていないこと。
イ 各種規制について
現行の建築基準法の防火基準への不適合、適切な初期消火活動等の未実施等が、早期の延焼の拡大及び煙の拡散の要因と推定されることを踏まえ、現行の各種規制について適切に遵守させることが必要である。
また、火災の早期の覚知が重要であることから、小規模なホテル・旅館等(300m2未満)への自動火災報知設備の設置義務化について検討が必要であり、その際には、他の小規模就寝施設に係る規制についても総合的な検討が必要である。
ウ 立入検査と違反処理の推進方策について
危険性の想定される防火対象物でありながら消防本部の立入検査が最近9年間未実施となっていたことを踏まえ、建築構造の適合性も含め、的確に人命危険の高い対象物のふるい分けを行い、計画的な立入検査が実施される体制の整備が必要である。
また、以前の立入検査において、毎回、同じ違反内容を繰り返し指摘するにとどまり、違反処理の法的プロセスへ移行しなかったことを踏まえ、危険性・悪質性の高い違反について選別して厳格な違反処理に移行する体制の整備が必要であり、国においても、違反処理に携わる職員の育成に係る研修等の実施が必要である。
エ 火災予防上の危険に係る公表制度のあり方について
今回の火災にかんがみても建築構造の適合性は防火安全上極めて重要であるが、旧適マーク制度廃止後、建築構造を含めた適合性を情報提供する制度がない。
こうした必要性から、平成15年まで実施していた「旧適マーク制度」の仕組みを再評価し、新たな制度として構築することも一つの方策となり得るものと考えられる。このため、「旧適マーク制度」の点検項目を基本とし、事業者の申請に基づき消防機関が認定する制度を、防火対象物定期点検報告制度等を活用して消防の検査等の負担の軽減を図り整備することが必要である。
