3.情報処理システムの活用
消防庁では、消防制度、基準の企画・立案、都道府県・市区町村への消防に関する助言・指導等を所管事務として担ってきたが、最近では、大規模災害発生時の緊急消防援助隊のオペレーションや武力攻撃・大規模テロなどの緊急事態に対応するための計画の策定、情報収集なども新たな業務として担っている。
これらの消防防災業務を効率的・効果的に遂行するため、現在まで、多くのシステムを整備・運用しているが、各種災害にきめ細かく対応してきた結果、消防庁所管のシステムの多様化、機能の重複等が課題となっている。予算効率の高い透明性の高いシステムを構築することを基本理念とし、消防防災業務の業務・システムの最適化計画を策定(平成20年3月28日総務省行政情報化推進委員会決定)し、最適化に取り組んでいる。
(1) 災害時対応支援システムの導入と活用
ア 地震被害想定システム
消防庁では、災害発生時に正確かつ迅速な状況判断の下に的確な応急活動を遂行する必要がある。そのため、災害発生時はシミュレーションにより被害を推測することができ、かつ、平時には円滑な災害対応訓練に活用できるシステムを導入することが有効であることから、地震被害想定システム等の開発・普及に努めている。
特に、消防研究センターで開発した「簡易型地震被害想定システム」(第2-10-6図)は、地震発生時に自動的に被害を推計することが可能であり、迅速な状況判断、初動措置の確保、日常の指揮訓練等に役立つシステムである。
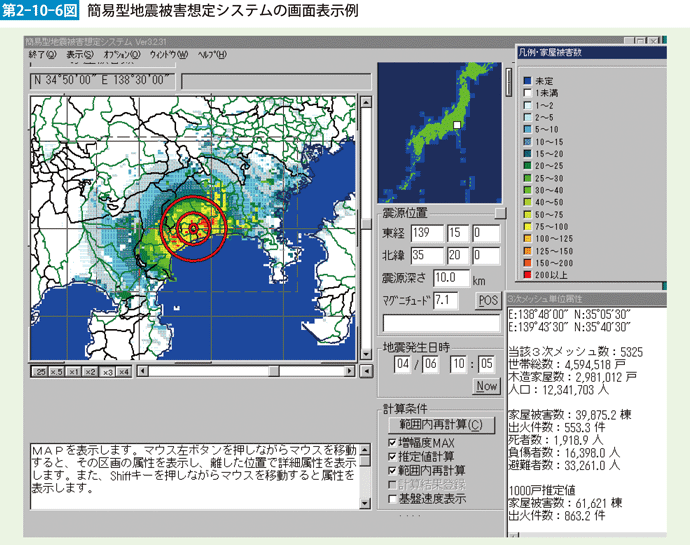
消防庁では、当該システムによる被害推定結果を全都道府県等にメール配信するなど活用を図っている。
地震直後の自動推計においては、気象庁が公開している点震源を用いていることから、本システムは平成23年東北地方太平洋沖地震のような一定規模を超えた巨大地震への適用には限界を有している。
広い範囲の断層の破壊現象によって引き起こされる巨大地震に対応するために、震度情報や線震源モデルなどを活用し、地震発生直後においても精度の高い被害推計が可能なシステムへの改良について研究開発を行っている。
イ 震度情報ネットワーク
全国の市町村で計測された震度情報を消防庁へ即時送信するシステム(震度情報ネットワーク)は、平成9年(1997年)4月から運用しており、本システムで収集された震度データは、緊急消防援助隊の派遣等、広域応援活動に活用するとともに、気象庁にも提供され震度情報として発表されている。
(2) 各種統計報告オンライン処理システム
行政事務の情報化に対応し、統計事務の効率化・迅速化を図るため、平成14年度から各種統計報告を行っており、平成15年度から順次運用を開始している。
- 火災報告等オンライン処理システム
- 防火対象物実態等調査オンライン処理システム
- ウツタイン様式調査オンライン処理システム
- 「危険物規制事務調査」及び「危険物に係る事故及びコンビナート等特別防災区域における事故報告」オンライン処理システム
- 救急救助調査オンライン処理システム
- 石油コンビナート等実態調査オンライン処理システム
- 消防防災・震災対策現況調査オンライン処理システム
消防庁では、これらのデータを迅速かつ的確に収集・整理することにより、都道府県、消防本部への速やかな情報提供を行い、各種施策への反映を支援している。
さらに、平成24年1月からは、消防防災業務の業務・システム最適化計画に基づき、各システムを統合した「統計調査系システム」として、ハードウエア等の管理を一元化し、入力の利便性の確保を行うことなどにより効率的な運用を行っている。
