[消防防災科学技術の研究の課題]
消防防災の科学技術は、火災等の災害現場における消防防災活動や防火安全対策等に不可欠なものであり、火災等の災害の発生に伴い緊急的な研究ニーズが出現すること、また、その対象とする研究領域が著しく広く、様々な知見が必要であることなどが特徴である。こうした消防防災科学技術の研究の特性に対応する上では、研究体制の運営の機動性、柔軟性が必要であるとともに、競争的研究資金制度の一層の充実による消防防災科学技術の研究領域に関する競争的な研究環境の創出、大学、研究機関等との産学官連携の推進が求められる。さらに、研究成果を火災等の災害現場における消防防災活動や防火安全対策等に利活用するためには、成果の解説、具体的な活用事例等に関する情報の共有化の推進が必要である。特に、新技術等を積極的に導入するためには、消防ニーズを積極的に発信するとともに、これらに関する技術シーズを有する大学、研究機関、企業等と連携して研究を行う必要がある。
国勢調査などの各種社会統計を活用した新たな火災危険性の分析手法の研究
火災は物的損失を生じるのみならず、人の生命や身体を脅かす災害です。火災による被害を低減させるためには、1件1件の火災の経験や教訓を、同様の火災が再発するのを防ぐために役立てることが大切です。
全ての火災は互いに異なる状況下で発生しますが、個々の事案について共通の傾向や教訓を見いだすことができれば、防火安全対策等に活用することができます。その最初の手がかりとなるのが統計であると言えます。
これまで消防庁は全国で発生した火災の統計について分析を行い、その結果を火災予防施策の立案に活用してきました。現在これに加え、国勢調査による我が国の人口構造や世帯構造などの各種社会統計を活用した、新たな火災危険性を分析するための手法の研究を行っています(下図参照)。
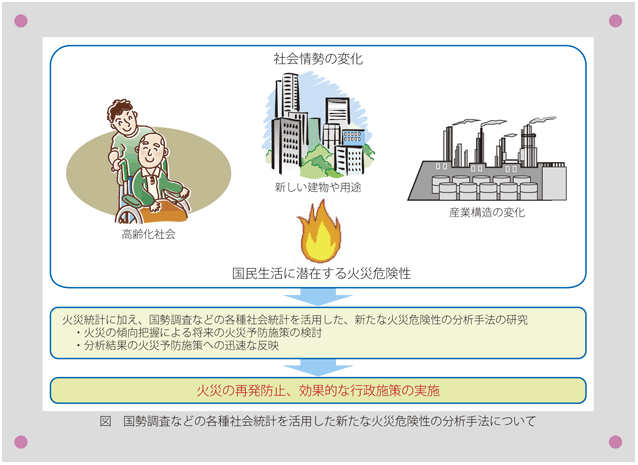
当該研究により、例えば、火災による死者の約6割を占める住宅火災における死亡率※1は、過去25年間女性に対して男性が常に1.5~2倍程度高い値※2を示していることや、死亡率を年齢別に見た場合、50歳前後の男性の死亡率の上昇傾向が顕著※3であるといった、今まで認識されていなかった火災の傾向が明らかになっています。
※1死亡率は、単位人口(10万人)あたりの死者数を示す。消防庁資料及び総務省統計局人口推計年報及び長期時系列データ(http://www.e-stat.go.jp/)より算出。
※2平成20年は、女性の死亡率0.68に対して男性の死亡率は1.09。
※3若年層や高齢層の死亡率が軒並み低下傾向を示す中、50歳前後の男性の死亡率は上昇傾向にあり、例えば50~54歳男性の死亡率は、1980年代前半の平均が0.81であったのに対し、2000年代前半の平均は1.01となっている。
このように、国勢調査などの各種社会統計を有効活用することによって、火災の統計だけではわからなかった火災の傾向をいち早く認識することができるようになり、これにより社会情勢の変化等によって新たに発生しつつある火災の予防施策の立案を迅速に行うことが期待されています。
今後とも、消防庁では、国民生活に潜む新たな火災危険性を的確に分析し、火災予防施策に迅速に反映することを可能とする手法の研究に努めます。
