[林野火災対策の課題]
効果的な林野火災対策を推進するためには、出火防止対策の一層の徹底を図るとともに、特に次の施策を積極的に講じる必要がある。
〔1〕 気象台から発せられる気象情報や火災気象通報を踏まえて、林野火災発生の可能性を勘案し、必要に応じて火災警報の効果的な発令を行うなど、火気取扱いの注意喚起や制限を含めて適切に対応すること。
〔2〕 林野火災を覚知した場合、早急に近隣の市町村に対して応援要請を行うなど、林野火災の拡大防止を徹底すること。特に、ヘリコプターによる偵察及び空中消火を早期に実施するため、迅速な連絡及び派遣要請に努めるとともに、ヘリコプターによる空中消火と連携した地上の効果的な消火戦術の徹底を図ること。また、ヘリコプターの活動拠点の整備促進を図ること。
〔3〕 林野火災状況の的確な把握、防ぎょ戦術の決定、効果的な部隊の運用と情報伝達及び消防水利の確保等を行うため、林野火災の特性及び消防活動上必要な事項を網羅した林野火災防ぎょ図を、GIS(地理情報システム)の活用も視野に入れて整備するなど、関係部局においてその共有を図ること。
〔4〕 防火水槽等消防水利の一層の整備を図ること。特に、林野と住宅地とが近接し、住宅への延焼の危険性が認められる地域における整備を推進すること。
〔5〕 周辺住宅地及び隣接市町村への延焼拡大防止を考慮した有効な情報連絡体制の整備を図るとともに、これを活用した総合的な訓練の実施に努めること。


平成21年の林野火災
[野焼き等による死傷者]
平成21年3月、大分県由布市において、野焼きを実施している住民が火に巻き込まれ7人の死傷者が発生しました。平成22年3月にも、静岡県御殿場市において、野焼き中の住民が火に巻き込まれ3人の死者が発生しています。
近年、林野火災は、毎年2,000件前後発生しており、これらの火災において10人以上の方が亡くなっています。
林野火災の出火原因は、上位からたき火、火入れ、放火(放火の疑いを含む)、たばこ、火遊びの順となっており、これらの原因で全体の約7割を占めています。死傷者が発生した林野火災に限ると、たき火と火入れが多くなっており、両者で約7割となっています。(下図参照)
たき火や火入れによる林野火災の発生や拡大を防止し、死傷者の発生を防ぐことが必要です。
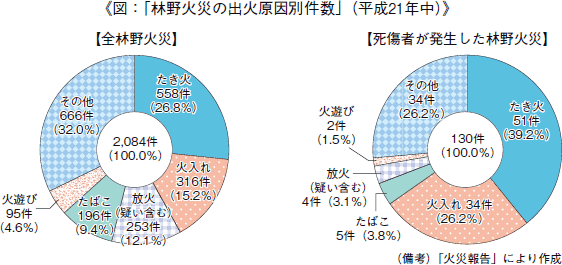
[大規模林野火災の発生]
平成21年は、宮城県角田市で102ha、山梨県甲州市で91haを焼損するなど大規模な林野火災が続発しました。焼損面積が20ha以上の林野火災は、近年減少傾向にあり、平成19年は6件、平成20年は3件でしたが、平成21年には大きく増加し11件発生しています。(下図参照)
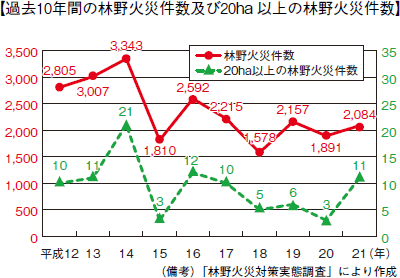
大規模な林野火災においては、消防防災ヘリコプター等による空中消火が有効であり、平成21年には140回行われています。
今後も、大規模な林野火災の減少のため予防対策と消防力を強化していくことが必要です。
