2 実施基準の状況
(1)実施基準の策定状況等
実施基準を策定等するための協議会については、平成22年11月1日現在において、全都道府県で設置されており、実施基準の策定については、平成22年11月1日現在において、7団体が実施基準を策定済であり、平成22年内にさらに16団体が策定を見込み、平成23年3月までには、全団体において策定を見込んでいるところである。
(2)策定された実施基準の内容
実施基準の策定は、傷病者の搬送及び受入れについて、地域における現状の医療資源等を活用し、消防機関、医療機関等が共通の認識の下で、当該都道府県における対応方策を決定していくことを意味するものであり、その具体的な内容については、それぞれの地域における医療提供体制の現状、受入医療機関の選定困難事案の発生状況、傷病者の搬送及び受入れの状況等の地域の実情に応じて定められることになる。
<1>実施基準策定における区域の設定
実施基準は、都道府県全体を一つの区域として定めるほか、医療を提供する体制の状況を考慮して、都道府県の区域を分けて定める区域(医療圏)ごとに定めることもできるものである。
策定された実施基準においても、6都県においては、都道府県全体を一つの区域として定めているが、1県(愛媛県)では、医療圏ごとに実施基準を定めているところである。
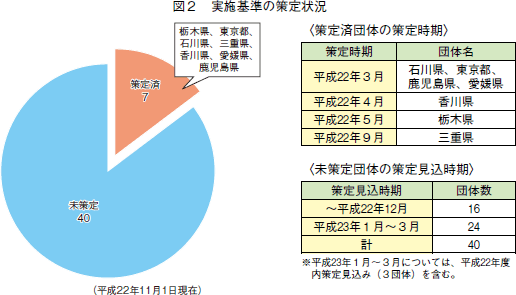
<2>分類基準
分類基準は、傷病者の状況に応じた適切な医療の提供が行われることを確保するために医療機関を分類する基準である。
分類基準としてどのような項目を設定するかについては、地域の実情に応じて決定すべきものであり、各地域で救急搬送について問題となっている点について協議会として認識(調査・分析)し、その認識に基づきどの症状等について分類基準を策定することが必要かを協議会が決定することが重要である。
策定された実施基準においても、その分類基準は様々となっている。
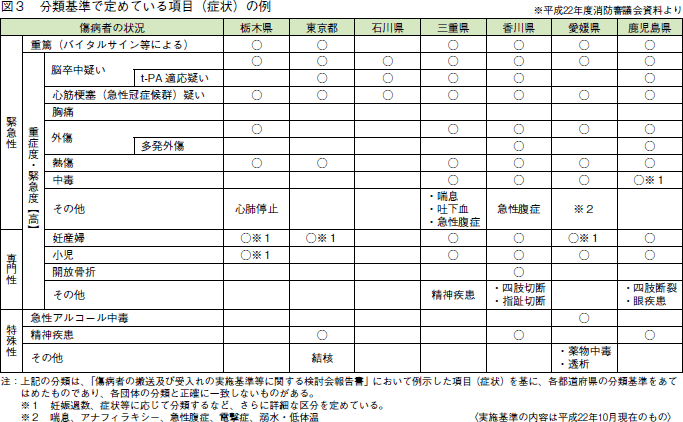
<3>医療機関リスト
医療機関リストは、分類基準に基づき分類された医療機関の区分ごとに、当該区分に該当する医療機関の名称を具体的に記載するものである。
策定された実施基準においては、医療圏単位で記載したり、所在地を示した上で全県単位で記載したり様々となっている。また、都道府県の区域を越えた搬送について、医療機関リストに隣接都道府県の医療機関の名称を記載している例もある。
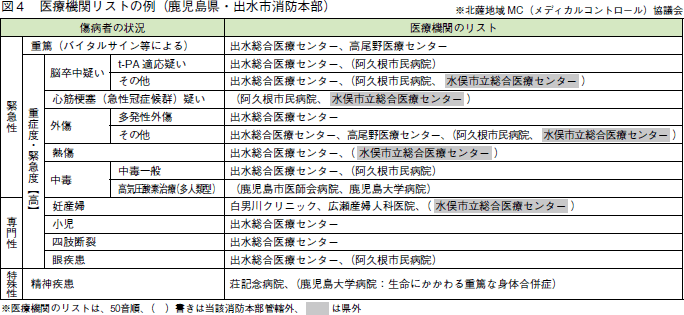
<4>受入医療機関確保基準
受入医療機関確保基準は、傷病者の受入れに関する消防機関と医療機関との間の合意を形成するための基準その他傷病者の受入れを行う医療機関の確保に資する事項を定めるものである。 このルールについては、コーディネーターや基幹病院による調整、一時受入れ・転送等の方法が考えられるものであり、策定された実施基準においても、搬送先医療機関が速やかに決定しない場合の設定や、その場合に受入医療機関を確保する方法については様々なものとなっている。
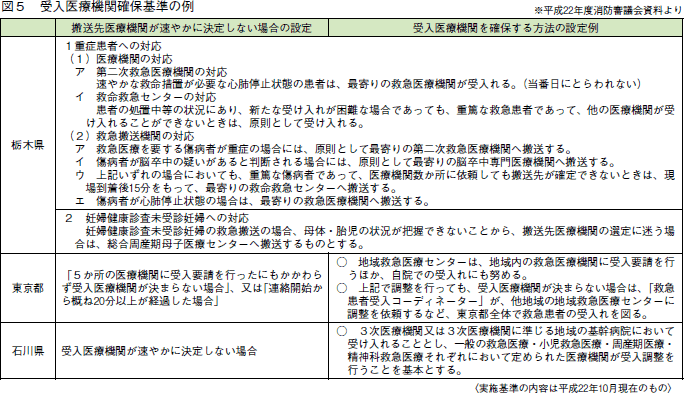
<5>都道府県間の調整
傷病者の搬送及び受入れが都道府県の区域を越えて広域的に行われている現状を踏まえ、実施基準において、隣接都道府県及び隣接都道府県の医療機関と連携し、都道府県の区域を越えた広域の対応を定めることもできるものである。
策定された実施基準においても、地理的条件や医療資源の状況等から隣接する都道府県への搬送について定めている県がある。
実施基準のこの他の項目についても、地域の実情に応じて定められることになる。
