[震災対策の現況]
1.震災対策の推進
東日本大震災を踏まえ、中央防災会議をはじめとする各機関により対策が講じられている(詳細は、第I部第1章参照)が、これまでにも、特に甚大な被害を及ぼすと想定されている東海地震、東南海・南海地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震及び中部圏・近畿圏直下地震について法律や地震対策大綱等が整備され、対策が講じられている(第1-7-3表)。
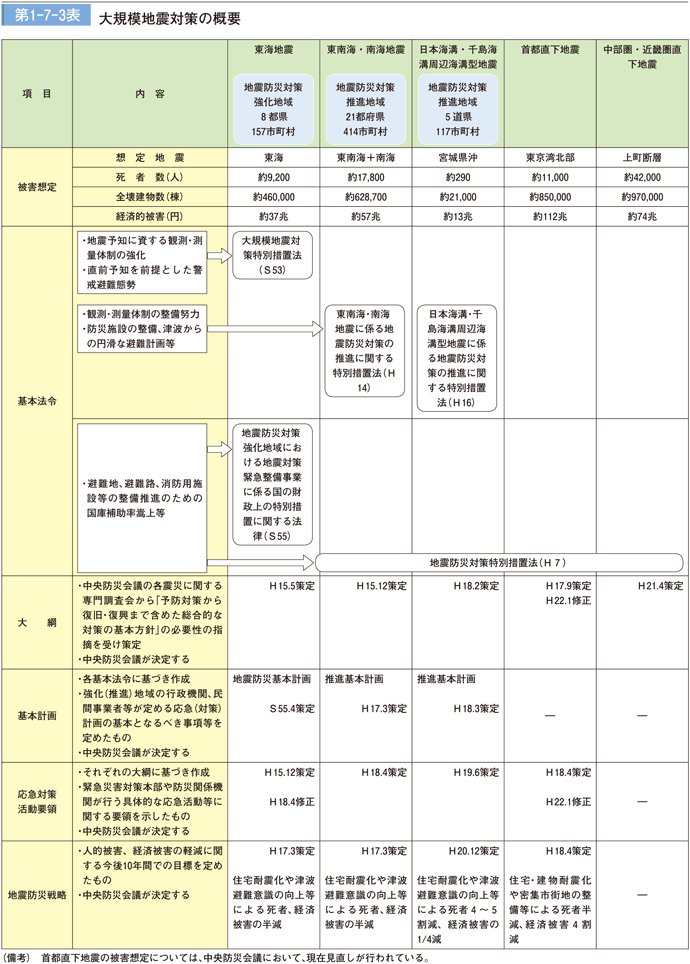
消防庁では、これらの法律等に基づき、震災対策に係る国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡、地域防災計画及び地震防災強化計画等に関する助言、防災訓練の実施、防災知識の普及啓発、震災対策に関する調査研究等の施策を推進しているほか、緊急消防援助隊の充実強化、震度情報ネットワークの整備(P.264参照)、地方公共団体における防災基盤の整備及び公共施設等の耐震化を促している。
(1) 南海トラフ*1巨大地震対策等
ア 東海地震対策
東海地震については事前の予知の可能性があることから、昭和53年(1978年)12月に施行された大規模地震対策特別措置法により、東海地域を中心とする1都7県の157市町村(平成24年4月1日現在)が地震防災対策強化地域として指定され、東海地震の予知情報が出された場合の地震防災体制を整備し、地震による被害の軽減を図ることとしている。
また、東海地震に関連する現象について調査が行われた場合に「東海地震に関連する調査情報(臨時)」が、観測された現象が東海地震の前兆現象である可能性が高まった場合に「東海地震注意情報」が、東海地震が発生するおそれがあると認められ、内閣総理大臣により警戒宣言が発せられた場合に、「東海地震予知情報」がそれぞれ発表されることとなっており、これらの情報が発表された場合には政府として防災対応を行うこととされている(第1-7-1図)。
*1 南海トラフ:フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈みこむ場所で、水深4,000m級の深い溝(トラフ)
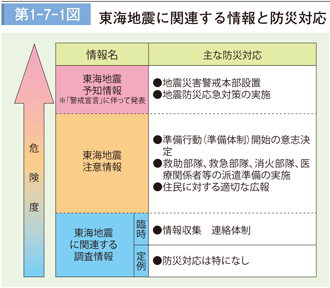
消防庁においても「東海地震に関連する調査情報(臨時)」が発表された場合にはあらかじめ指定された職員が参集し災害対策室を設置するほか、「東海地震注意情報」及び「東海地震予知情報」が発表された場合には全職員が参集し災害対策本部を設置して災害応急対応にあたることとしている。
イ 東南海・南海地震対策
東南海・南海地震は、歴史的にみて100年から150年の間隔で発生しており、その規模はマグニチュード*28クラスとされている。
*2 マグニチュード:震源での地震エネルギーの大きさを示す値。マグニチュードが大きくても、震源が深かったり遠かったりすれば、揺れは一般的に小さくなる。マグニチュードが1増えると、エネルギーは32倍になる。
昭和19年(1944年)に東南海地震、昭和21年(1946年)に南海地震が発生して以降、すでに60年以上が経過していることから、今世紀前半にも発生が懸念されている(第1-7-2図)*3。このため、東南海・南海地震が発生した場合は著しい地震被害が発生する可能性のある地域を「東南海・南海地震防災対策推進地域」として1都2府18県の414市町村(平成24年4月1日現在)を指定し、地震防災対策の強化が図られている。
*3 今後30年以内に発生する確率(平成24年1月1日時点)は、地震調査研究推進本部の地震調査委員会の公表によると、東南海地震70%、南海地震60%程度となっている。
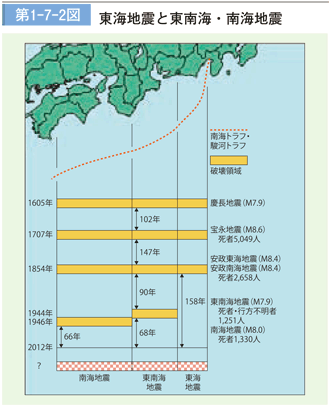
ウ 南海トラフ巨大地震対策
東日本大震災の教訓を踏まえて、平成23年8月に「南海トラフの巨大地震モデル検討会」が内閣府で開催され、科学的知見に基づき南海トラフの巨大地震対策を検討する際に想定すべき最大クラスの地震・津波の検討を進めることとされた。同モデル検討会は、同年12月に南海トラフの巨大地震モデルの想定震源域・想定津波波源域の設定の考え方などの「中間とりまとめ」を公表し、平成24年3月には、最大クラスの震度分布・津波高(50mメッシュ)の推計結果を第一次報告として公表した。続いて、同年8月に10mメッシュによる津波高及び浸水域等の推計結果を第二次報告として公表した。
一方、南海トラフ巨大地震に対する対策を検討するため、平成24年4月、中央防災会議「防災対策推進検討会議」の下の「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」が開催され、同年7月には、当面取り組むべき対策等を取りまとめた中間報告を、同年8月には、モデル検討会の10mメッシュによる津波高等の公表に合わせて、第一次被害想定(人的被害及び建物被害)と「最大クラスの地震・津波」への対応の基本的考え方を公表した。
(2) 首都直下地震対策等
ア 東日本大震災以前の取組
首都地域は、人口や建築物が密集するとともに、我が国の経済・社会・行政等の諸中枢機能が高度に集積している地域であり、大規模な地震が発生した場合には、被害が甚大となり、かつ影響が広域に及ぶものとなるおそれがある。平成15年から開催された中央防災会議「首都直下地震対策専門調査会」によると、南関東地域においては、200~300年に一度、大正12年(1923年)の関東地震と同様のマグニチュード8クラスのプレート境界型地震が発生し、その間にマグニチュード7クラスの地震が数回発生する可能性が高いとされている(第1-7-3図)*4。
*4 南関東で発生するマグニチュード7程度の地震が今後30年以内に発生する確率(平成24年1月1日時点)は、地震調査研究推進本部の地震調査委員会の公表によると、70%程度となっている。
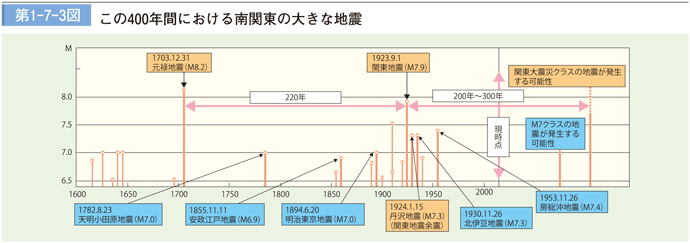
このため、マグニチュード7クラスの首都直下地震が発生した場合の被害想定を行う(平成16年12月及び平成17年2月)とともに、平成17年9月に、首都地域の特性を踏まえた首都中枢機能の継続性確保や膨大な被害への対応を対策の柱とする首都直下地震対策大綱が策定された。
その後、首都直下地震において想定される膨大な数の避難者・帰宅困難者への対策を検討するため、平成18年8月から中央防災会議「首都直下地震避難対策等専門調査会」が開催され、平成20年10月に同調査会報告書が取りまとめられた。それを受け、平成22年1月の中央防災会議において、大綱の修正がなされ、地方公共団体の連携による広域的な避難体制の整備、翌日帰宅や時差帰宅による一斉帰宅の抑制、帰宅困難者等一時滞在施設の確保等の具体的な対策の必要性が盛り込まれた。
イ 東日本大震災の教訓を踏まえた取組
平成23年9月に、内閣府と東京都を共同事務局とし、関係府省庁、地方公共団体及び経済団体等からなる「首都直下地震帰宅困難者等対策協議会」が設置され、平成24年9月には、帰宅困難者対策を官民が連携・協働して実施するための報告書・ガイドラインが取りまとめられた。
一方、平成24年3月には、中央防災会議「防災対策推進検討会議」の下に「首都直下地震対策検討ワーキンググループ」が、同年5月には、内閣府に「首都直下地震モデル検討会」が設けられた。同ワーキンググループは、同年7月に被害想定を待たずとも取り組むべき対策と今後重点的に検討すべき課題を中間報告として取りまとめた。
また、同モデル検討会においては、最新の科学的知見を踏まえて、従来検討していた18タイプのマグニチュード7クラスの首都直下地震の見直しと、相模トラフ沿いで発生する最大クラスの地震・津波を新たに想定対象に加えた検討が進められている。
(3) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策
日本海溝・千島海溝周辺では、過去において大津波を伴う地震が多数発生しており、東北地方太平洋沖地震もこの領域で発生している。日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に備え、地震防災対策を推進する必要がある地域を「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域」として1道4県の117市町村(平成24年4月1日現在)を指定し、地震防災対策の強化が図られている。
(4) 中部圏・近畿圏直下地震対策
中部圏・近畿圏の内陸には多くの活断層があり、次の東南海・南海地震の発生に向けて、中部圏及び近畿圏を含む広い範囲で地震活動が活発化する可能性が高い活動期に入ったと考えられるとの指摘もある。この地域の市街地は府県境界を越えて広域化しており、大規模な地震が発生した場合、甚大かつ広範な被害が発生する可能性がある。中部圏・近畿圏直下地震への防災対策については、中央防災会議「東南海、南海地震等に関する専門調査会」において検討された。
同専門調査会では、地震が発生した場合の「応急対策」等具体的に検討するための地震として、中部圏・近畿圏に存在する11の活断層で発生する地震と、名古屋市直下及び阪神地域直下に想定したマグニチュード6.9の地震について、想定震度分布等を公表するとともに、建物被害、死者数等の推計結果(第1-7-4表)をはじめ、文化遺産の被災可能性、経済、交通、ライフライン被害等の推計結果、上町断層帯による浸水可能性の評価結果を公表している。これらの被害想定結果を踏まえ、平成20年12月には、被害軽減を図るための対策を含んだ「中部圏・近畿圏の内陸地震に関する報告」(参照URL:http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/nankai/36/shiryou/shiryou3.pdf)が取りまとめられた。なお、平成21年4月、中部圏・近畿圏直下地震対策のマスタープランである「中部圏・近畿圏直下地震対策大綱」が中央防災会議で決定された。
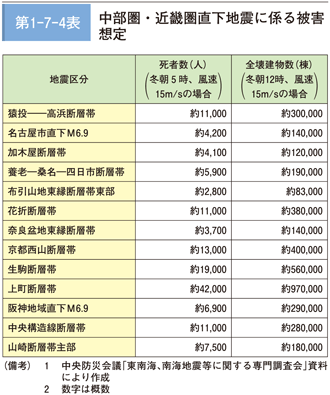
(5) その他
ア 防災基盤の整備と耐震化の推進
平成7年(1995年)1月に発生した阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、総合的な地震防災対策を強化するため、同年7月に「地震防災対策特別措置法」が施行された。同法に基づき地域防災計画に定められた事項のうち、地震防災上緊急に整備すべき施設等に関して、すべての都道府県において「地震防災緊急事業五箇年計画」が作成され、これらの計画に基づき、避難地、避難路、消防用施設、緊急輸送路の整備、社会福祉施設・公立小中学校等の耐震化及び老朽住宅密集市街地対策等が実施されてきている。同計画は、第1次地震防災緊急事業五箇年計画(平成8年(1996年)度~平成12年(2000年)度)、第2次地震防災緊急事業五箇年計画(平成13年度~平成17年度)、第3次地震防災緊急事業五箇年計画(平成18年度~平成22年度)、第4次地震防災緊急事業五箇年計画(平成23年度~平成27年度)と策定され、防災基盤の整備に向けた事業への積極的な取組が続けられている。
消防庁では、大規模地震発生時に、避難所や災害対策の拠点となる公共施設等の耐震化について、耐震率(平成23年度末79.3%)を平成25年度までに85%とすることを目指し、単独事業として行われる耐震改修事業に対し、地方債と地方交付税による財政支援を行っている。平成21年度からは、地震による倒壊の危険性が高い庁舎及び避難所について、事業費の90%を起債対象とし、その元利償還金の2/3を交付税算入とする地方財政措置の拡充を行った。さらに、東日本大震災の教訓を踏まえて平成23年12月に新たに設けられた緊急防災・減災事業(単独)の対象とすることとした。同事業は、東日本大震災からの復興に関し必要な財源の確保に関する臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)等により確保される財源により実施されており、事業費の100%を起債対象とし、その元利償還金の70%を交付税算入することとされている。
また、耐震診断・改修工事の効果的な実施手法や事例を紹介する「防災拠点の耐震化促進資料(耐震化促進ナビ)」を平成17年度に作成し、すべての地方公共団体へ配布するとともに、消防庁ホームページにおいて公表している(参照URL:http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/taishin/index-j.html)。
イ 消防力の充実強化
〔1〕 耐震性貯水槽の整備
大規模地震発生時には、地震動による配水管の破損、水道施設の機能喪失等により消火栓の使用不能状態が想定され、消火活動に大きな支障を生ずることが予測される。
このため、消防庁では、地震が発生しても消防水利が適切に確保されるよう、国庫補助による耐震性貯水槽の整備を進めているところであり、平成24年4月1日現在、全国で、94,959基が整備されている。
〔2〕 震災対策のための消防用施設等の整備の強化
地震防災対策強化地域における防災施設等の整備や地震防災緊急事業五箇年計画に基づく防災施設等の整備については、国の財政上の特例措置が講じられている。また、地方単独事業についても地方債と地方交付税の措置により地方公共団体の財政負担の軽減が図られてきた。大規模地震発生後における防災活動が迅速かつ的確に行われ震災被害を最小限に抑えるためには、今後とも中・長期的な整備目標等に基づき、より一層の消防防災施設等の整備促進を図っていくことが必要である。
ウ 津波対策の推進
我が国においては、地震とそれに伴い発生する津波によって、過去にも大きな被害が生じている。東日本大震災においても津波によって甚大な被害が発生した。
これを受け、第177回国会において、議員立法により、津波対策を総合的かつ効率的に推進するために「津波対策の推進に関する法律」が成立し、平成23年6月に公布・施行された。同法律では、津波対策に係る基本的認識や11月5日を津波防災の日とすること等が定められた。
同年12月には、1)都道府県知事が、最大クラスの津波が悪条件下において発生することを前提に津波防災地域づくりを実施するための基礎となる津波浸水想定を設定、2)その上で、津波浸水想定を踏まえて、市町村による推進計画の作成、津波災害警戒区域・津波災害特別警戒区域等のハード・ソフト施策を、地域の実情に応じ、適切かつ総合的に組み合わせることにより、最大クラスの津波への対策を効率的かつ効果的に講ずることなどを主な内容とする「津波防災地域づくりに関する法律」が成立し、同月公布・施行された。
一方、中央防災会議「防災対策推進検討会議」の下の「津波避難対策検討ワーキンググループ」は、津波避難対策の基本的な考え方及び具体的な方向性について示した報告を平成24年7月に取りまとめた。同報告が示した津波避難対策の基本的考え方は、「素早い避難」が最も有効で重要な津波対策であること、津波による人的被害を軽減するためには、住民等一人ひとりの迅速かつ主体的な避難行動が基本となること、その上で、海岸保全施設等のハード対策や確実な情報伝達等のソフト対策は、全て素早い避難の確保を後押しする対策と位置付けるべきものであることである。
実効性のある津波避難対策を実施するためには、都道府県が津波浸水想定区域図を作成すること、それに基づき、市町村が避難対象地域の指定、避難場所等の指定、避難指示等の情報伝達、避難誘導等を定めた具体的な津波避難計画を策定する必要がある。
消防庁では、平成14年3月に策定した「津波対策推進マニュアル検討報告書」について、東日本大震災を踏まえた見直しを行うため、地方公共団体等の協力を得て、平成24年6月より「津波避難対策推進マニュアル検討会」を開催している。
なお、平成16年度に開催した「防災のための図記号に関する調査検討委員会」では、津波避難に係る標準的図記号として、「津波注意」、「津波避難場所」、「津波避難ビル」の3種の図記号を決定した(第1-7-4図)。これらの図記号は、平成20年7月に国際規格化(ISO化)されるとともに、平成21年3月にJIS(日本工業規格)化されている。

さらに、津波避難タワーの設置や津波浸水想定区域内からの公共施設等の移転などについては、地方債と地方交付税による財政支援を行っている。
エ 地域防災計画(震災対策編等)の策定・見直しへの取組
地震災害は地震動による建築物の損壊のみならず、津波、火災、山崩れ等による二次的災害も含んだ複合的な災害であり、被害も広範囲に及ぶという特性を有するものであるため、地域防災計画において、他の災害とは区分して「震災対策編」等として独立した総合的な計画を策定しておく必要がある。
さらに、平成23年12月の防災基本計画の修正により、これまで震災対策編の一部とされていた津波災害対策について、新たに独立して「津波災害対策編」が設けられた(震災対策編は「地震災害対策編」とされた。)。
また、地域防災計画の策定・見直しにおいては、被害想定に基づく防災体制の見直しや、近隣地方公共団体における計画との整合性に留意するとともに、職員参集・配備基準をはじめ各種応急体制の整備・充実、災害時における職員の役割や関係機関等との連絡体制等を明確にするなど、地域防災計画の実効性の向上に努めることが重要である。
