2.消防団の安全対策と充実強化
(1) 大規模災害時における消防団活動
東日本大震災において、被災地の消防団員は、自らも被災者であったにもかかわらず、郷土愛護の精神に基づき、水門等の閉鎖、住民の避難誘導、救助、消火、避難所の運営支援、行方不明者の捜索、発見されたご遺体の搬送・安置、さらには信号機が機能しない中での交通整理、夜間の見回りまで、実に様々な活動に献身的に従事した。一方で、254名*1にも上る消防団員が犠牲となったことを重く受け止め、その教訓を今後に活かすことが必要である。
*1 平成24年9月11日現在、死者・行方不明者254名。うち公務中198名

(2) 東日本大震災を踏まえた大規模災害時における消防団活動のあり方
東日本大震災を受け、消防庁では、消防審議会での議論も踏まえつつ、平成23年11月から、有識者、地方公共団体関係者及び関係省庁からなる「東日本大震災を踏まえた大規模災害時における消防団活動のあり方等に関する検討会」を開催し、平成24年3月には、津波災害時の消防団員の安全確保対策を中心とした中間報告書を取りまとめ、都道府県を通じ、市町村における津波災害時の消防団活動・安全管理マニュアルの作成や地域ぐるみの津波避難計画の策定などを推進するよう通知した。また同中間報告書を基に、9月から、47都道府県において、災害対応指導者育成支援事業を開催している。
同検討会では、8月には、消防団の装備・教育訓練等の充実、若者が入りやすい消防団に向けた取組、地域の総合的な防災力の向上のための取組などについての報告書を取りまとめたところであり(第2-2図)、国、都道府県、市町村、地域それぞれの立場で消防団の充実強化、地域の総合的な防災力の向上の推進が望まれる。その一環として、平成24年度には、全国10箇所で、消防団・自主防災組織の理解促進シンポジウムを開催することとしている。
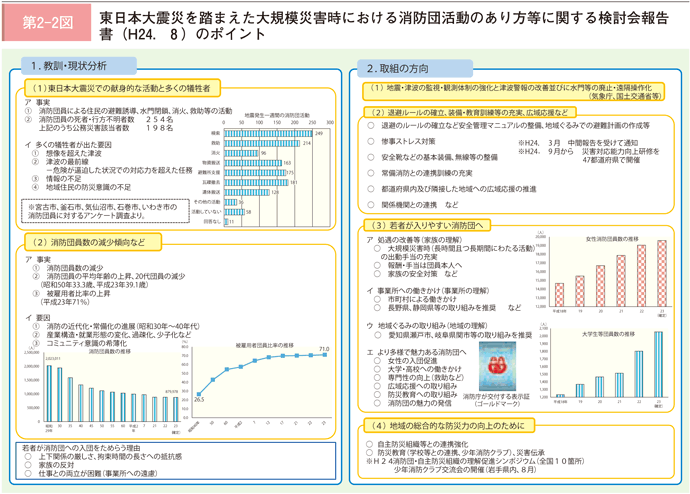
また、消防団の装備・施設の充実強化を図るため、これまでも消防車両や無線機器等の装備や活動拠点となる施設に対する財政支援を行ってきており、平成23年度補正予算(第3号)においては、東日本大震災を踏まえ、消防団員の活動中の安全確保のための装備の整備を支援する補助制度を設け、トランシーバー、ライフジャケット、投光器などの配布を行った。
さらに、平成24年度からは、ライフジャケット等の安全装備品に対する地方交付税措置の拡充を図ったところであり、引き続き、消防団の安全対策の強化を進めていく。
