トピックス3 熱中症への対応
1.熱中症と救急業務の関わり
(1) 熱中症とは(病態、予防、応急対応)
熱中症とは高温環境下でおきる体の変化(血液分布の変化、汗による水分や塩分(ナトリウムなど)の喪失等)に対して、適切に対応できなかった場合に発症する、筋肉のこむらがえりや失神、頭痛、嘔気等の様々な症状を発症した状態であり、最終的に熱の産生と熱の放散とのバランスが崩れた場合には、体温が著しく上昇し、臓器障害から死に至る恐れのある疾患である。
熱中症を引き起こす条件として、<1>からだ(体調、性別、年齢、暑熱順化の程度など)<2>環境(気温、湿度、ふくしゃ熱、気流など)<3>行動(活動強度、持続時間休憩など)の3条件があるとされ、熱中症予防においては、年齢及び持病等の個人のリスクに応じて、気象条件を踏まえながら適切な予防行動をとることが重要である。具体的には、こまめな水分補給、エアコン・扇風機を用いた室温調整等及び適切な休息を取ることが挙げられる。特に高齢者や子どもは熱中症弱者とされることから、関係者と一体となった予防啓発活動が重要である。
重症度の観点からは、Ⅰ度からⅢ度に分類され、Ⅰ度はめまい、こむら返り等、Ⅱ度は頭痛、吐き気、倦怠感、Ⅲ度では意識障害等が出現する。熱中症を疑った時には、涼しい場所で体を冷やし、水分補給をしながら様子を観ることが重要であるとされるが、重症例を見逃さないという観点から、分類にこだわらず「意識がない、全身のけいれんがある」又は「自分で水が飲めない、脱力感や倦怠感が強く動けない」場合には、ためらわず救急要請をする必要がある(トピックス3-1表)。
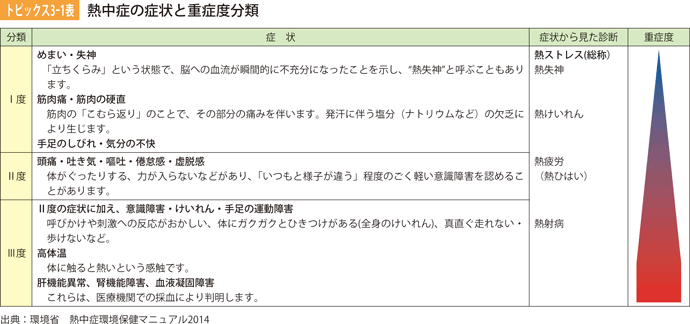
(2) 消防機関の行う救急業務との関わり
消防庁が実施している夏期における熱中症による救急搬送人員数の調査によれば、例年、夏期に4万人以上の救急搬送が発生し、救急搬送人員数の中で相当の比重を占める状況となっており、熱中症への対応は、国民の生命と安全にとって極めて重大な課題となっている。さらに、夏期の一定の時期に集中して発生することから、救急業務の円滑な実施の観点からも、消防機関が熱中症傷病者を迅速かつ適切に医療機関に搬送するとともに、保健所及び医療機関、福祉施設等と連携した予防啓発活動等を実施することが重要である。
