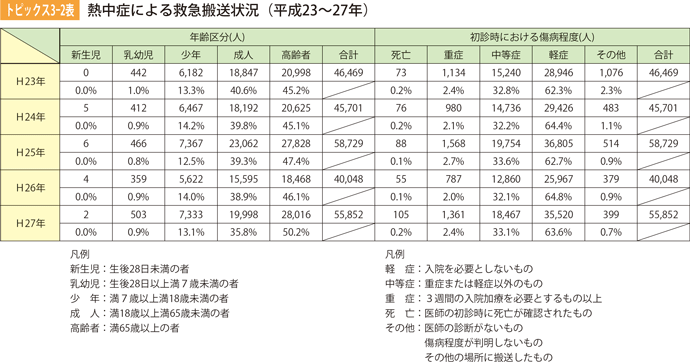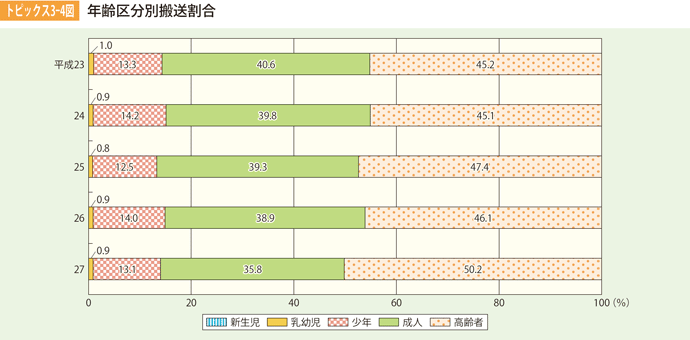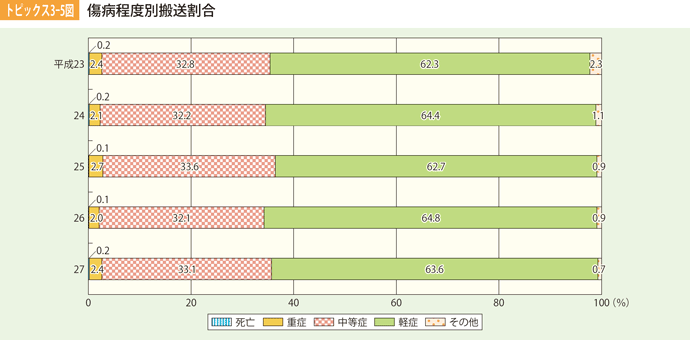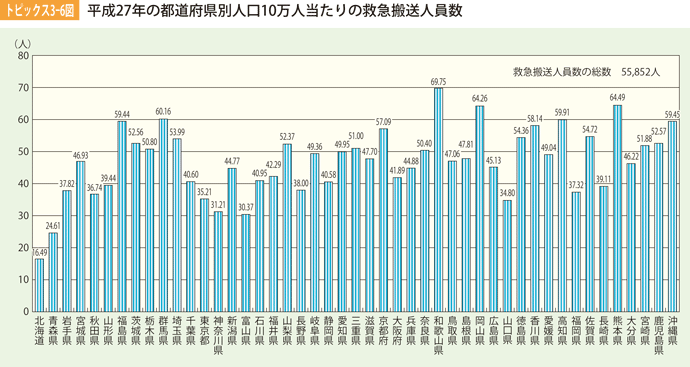2.夏期における熱中症による救急搬送人員数の調査
(1) 調査の趣旨と概要
消防庁では、政府一丸となった熱中症予防対策の一環として、平成20年から熱中症による救急搬送人員数の調査を実施している。本調査の目的は、全国の熱中症による救急搬送の実態を明らかにし、メディア及び研究機関を含む関係機関に情報提供することにより、熱中症予防の普及啓発活動の推進及び科学的知見の発展に寄与することである。
本調査は、熱中症の救急搬送人員数が増加する夏期に行っており、毎週、全国の各消防本部では、月曜日から日曜日までの熱中症による救急搬送人員数をサーベイランス調査として消防庁に報告している。調査結果は、速報値として週ごとにホームページ上に公表するとともに、各月ごとの集計・分析についても公表している。
本調査は、全国の消防機関の協力により、熱中症による救急搬送人員数の速やかな公表が可能となっており、熱中症に対する社会的関心を高め、熱中症予防を広く国民に呼びかけることにより、熱中症による救急搬送人員数の減少につながることが期待されている。調査の傷病区分は医師の初診時の判断であるため、最終的な診断名が熱中症でない可能性があるなどの限界はあるものの、悉皆性と速報性を有しており、熱中症の発症状況の全体像を把握するうえで重要な調査となっている。
熱中症による救急搬送人員数は、各年度により調査期間が異なるものの例年4万人以上となっており、特に暑さが厳しかった平成22年、25年及び27年の救急搬送人員数は5万人を超えた。熱中症による救急搬送人員数については、梅雨明けの時期、最高気温が35度以上の猛暑日が全国でどれくらいの地域に及ぶか、気温の上昇の訪れにいかに体の順応が追いつくかなど様々な影響を受ける。
(2) 平成27年の調査結果
例年、熱中症による救急搬送人員数が急増するのは梅雨明け後であるが、ゴールデンウィーク前後の時期に熱中症が発生することが指摘されていることから、平成27年は調査開始時期を前年から前倒しし、4月27日から10月4日までの期間について調査を実施した。
調査期間中の熱中症による救急搬送人員数は5万5,852人であり、前年の同期間の4万48人と比べて、約4割増となった。特に7月中旬から8月上旬までは全国的に猛暑であったことを受けて、7月の救急搬送人員数は2万4,567人と平成20年の調査開始以降7月としては最も多い救急搬送人員数となり、7月27日から8月9日までの期間の救急搬送人員数は2週続けて1週間当たり1万人を超えた。また、8月上旬の10日間の救急搬送人員数は8月全体の救急搬送人員数の半数以上を占め、8月の救急搬送人員数は2万3,925人となった。9月に入ると気温が下がったため、9月の救急搬送人員数は1,424人となり、平成20年の調査開始以降、平成21年に次いで2番目に少ない救急搬送人員数となった(トピックス3-1図、3-2図、3-3図)。
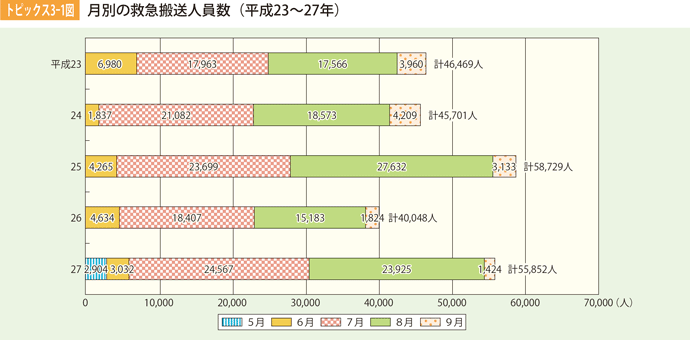
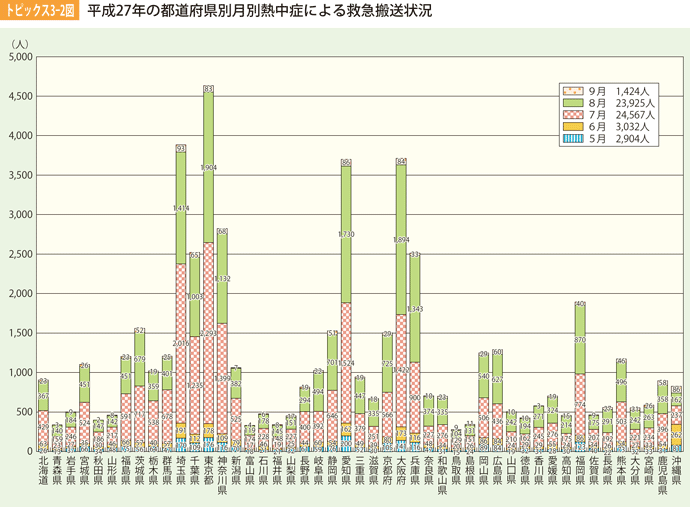
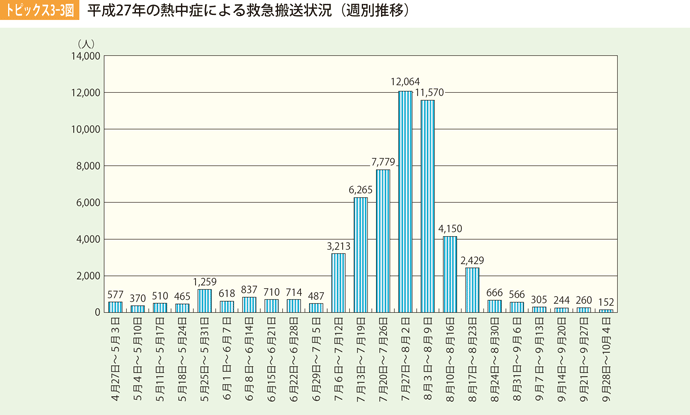
年齢区分別では合計5万5,852人のうち、高齢者(65歳以上)が2万8,016人と最も多く、次いで成人(18歳以上65歳未満)が1万9,998人、少年(7歳以上18歳未満)が7,333人、乳幼児(生後28日以上7歳未満)が503人、新生児(生後28日未満)が2人の順となった。熱中症による救急搬送人員数の半数以上を高齢者が占めており、調査開始以降初めて5割超を記録した。傷病程度別には、軽症が3万5,520人と最も多く、次いで中等症1万8,467人、重症1,361人、死亡105人の順となった。死亡者数については、記録的な猛暑日を観測した平成22年の171人に次ぐ人数となった。都道府県別人口10万人当たりの救急搬送人員数は和歌山県が最も多く、69.75人であり、次いで熊本県64.49人、岡山県64.26人の順となった(トピックス3-2表、3-4図、3-5図、3-6図)。