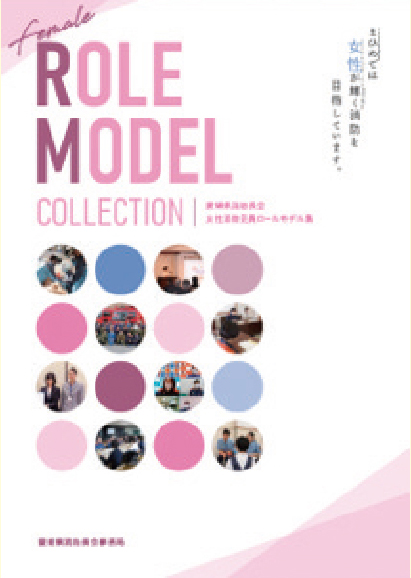Topics2 消防における女性の活躍推進に向けた取組
消防庁では、消防分野において活躍する女性を知ってもらい、消防を目指す女性を増やすため、消防庁ホームページ内に「女性消防吏員の活躍推進のためのポータルサイト」を開設し、PR動画等の広報制作物を公開しているほか、男性育休の取得促進や、消防団入団促進広報等に取り組んでいる。さらに、令和6年4月1日には、消防庁での取組を包括的かつ分野横断的に推進するため、消防庁内にWPS(Women, Peace and Security)推進専門官を設置し、女性活躍推進のための体制を強化している。
■女性消防吏員の活躍推進
全国の消防吏員に占める女性の割合は、3.7%(令和6年4月1日現在)であり、全国で活躍する女性の消防吏員は年々増加している。消防庁では、まずは「消防本部における女性消防吏員の更なる活躍に向けた取組の推進について」(平成27年7月29日付け通知)で示した、令和8年度当初までに女性の割合を5%に引き上げることを目標に、消防を自らの職業として選択する女性の増加に向け、以下のような取組を行っている。
≪女性消防吏員活躍推進モデル事業≫
全国の消防本部にとって参考となる先進事例を構築し、取組の横展開を図っていくことを目的に、国の委託事業としてモデル事業を実施している。
画像をクリック(タップ)すると拡大表示します
女性消防職員募集のためのPR動画制作及び放映
西宮市(兵庫県)
画像をクリック(タップ)すると拡大表示します
女性の働き方に関する民間企業とのタイアップ研修
松江市(島根県)
画像をクリック(タップ)すると拡大表示します
女性消防吏員のロールモデル集の作成
松山市(愛媛県)
画像をクリック(タップ)すると拡大表示します
幅広い層へのPRを目的としたメタバースを用いた消防署見学
京都市(京都府)
≪PRポスター、パンフレットの作成≫
女性消防吏員をより身近に感じてもらうため、様々な業務で活躍する現役の女性消防吏員をモデルとして起用したポスター及びパンフレットを作成し、これまで消防が将来の職業の選択肢になかった女性をターゲットとした広報に取り組んでいる。
画像をクリック(タップ)すると拡大表示します
PRポスター
画像をクリック(タップ)すると拡大表示します
パンフレット
≪女性救急隊員の職務環境の整備促進≫
消防庁では、「救急業務のあり方に関する検討会」において、女性救急隊員の職務環境の整備促進に係る取組として、身体的負担軽減が期待される電動ストレッチャーの導入や救急現場に持参する酸素ボンベの軽量化などの先進的な事例をとりまとめ、各消防本部へ周知している。
また、電動ストレッチャーの導入については、令和6年度からは緊急消防援助隊設備整備費補助金の対象として新たに追加し、女性救急隊員の更なる活躍につながる取組を促進している。
≪女性消防吏員同士の交流≫
女性消防吏員が自主的に集まり、勉強会や情報交換を行うとともに、消防本部の枠を超えて相互に親睦を深める場としてJFFW(Japan Fire Fighting Women’sClub)交流会が開催されており、令和6年度は横浜市で開催された。
画像をクリック(タップ)すると拡大表示します
JFFW交流会
≪男性消防職員の育児休業の取得促進≫
女性活躍推進のためには、男性も含めて仕事と家庭の両立支援に取り組むことが重要である。消防庁では、育児休業取得率に関する政府目標である令和7年までに50%、令和12年までに85%(こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定))を達成するため、男性消防職員の育休取得率が高い消防本部が実施している取得促進策の横展開等に取り組んでいる。
≪緊急消防援助隊を受け入れる環境の整備≫
令和6年能登半島地震においても緊急消防援助隊として女性隊員が出動するなど、災害が激甚化・頻発化する中、男女問わず被災地へ派遣されることが想定される。そのため、緊急消防援助隊受援計画に宿営場所として位置付けられた消防庁舎における女性専用施設の整備について、令和6年度から緊急防災・減災事業債の対象に加えるなど、女性のための宿営環境の整備を促進している。
■女性消防団員の活躍推進
消防団員に占める女性の割合は、3.8%(令和6年4月1日現在)であり、全国で活躍する女性の消防団員は年々増加している。
消防庁では、消防団員に占める女性の割合について、10%を目標としつつ、当面、令和8年度までに5%(第5次男女共同参画基本計画(令和2年12月25日閣議決定))とする目標を掲げており、女性消防団員の入団促進に向けて、以下のような取組を行っている。
≪消防団入団促進広報≫
女性タレントを起用したポスター・PR動画を作成するなど女性が活躍できる場としての消防団の認知度向上を図っているほか、夏休みなどの長期休暇期間に、全国のショッピングモールにおいて、入団促進イベントを実施するなど、様々な取組を行っている。
画像をクリック(タップ)すると拡大表示します
入団促進イベント
≪消防団の力向上モデル事業≫
女性や若者をはじめとする幅広い住民の入団促進のため、社会環境の変化に対応した消防団運営の促進に向け、地方公共団体の先進的な取組を支援している。
令和5年度は、大阪府において女性消防団員の認知度向上と入団促進を目的に、女性消防団員によるワークショップ形式によるイベントを実施したほか、北茨城市では災害現場における活動内容の確認と団員間の連携強化を目的に、女性消防団員による傷病者等の応急手当訓練を実施するなど、多くの地方公共団体で女性団員の確保や活動活性化の取組が行われている。
引き続き、優良事例を横展開するとともに、今後は女性が活動しやすい環境づくりに向けた取組を重点的に支援していく。
画像をクリック(タップ)すると拡大表示します
ワークショップイベント
(大阪府提供)
画像をクリック(タップ)すると拡大表示します
応急手当訓練
(北茨城市提供)
≪女性消防団員の活動環境の整備促進≫
女性消防団員が活動しやすい環境を構築できるよう、緊急防災・減災事業債の活用を通じて、消防団拠点施設における女性用トイレや更衣室等の設置等を推進している。
また、消防団設備整備費補助金において、女性を含め、全ての団員が比較的容易に取り扱える小型化・軽量化された救助用資機材等の整備を推進していく。