[風水害対策の課題]
1 避難勧告等の発令・伝達
(1)避難勧告等の判断・伝達マニュアルの作成
政府としては、市町村に対し、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」(平成17年3月策定)を参考に、市町村において「避難準備(要援護者避難)情報」を地域防災計画に位置付けるほか、避難勧告等を発令する客観的な判断基準等を定めた避難勧告等の判断・伝達マニュアルの整備を求めている。しかしながら、平成20年10月1日現在、水害に関する避難勧告・指示の具体的な発令基準を策定済みの市町村は771団体(42.6%)、土砂災害に関しては636団体(38.9%)にとどまっている(第1-5-3表)。避難勧告等発令の判断については、平成21年7月中国・九州北部豪雨、平成21年台風第9号による大雨でも課題となったところであり、平成21年8月通知により、避難勧告等に係る発令の判断基準等を未だに定めていない市町村にあっては、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」に沿って、避難勧告等に係る発令の判断基準等を速やかに作成することなどについて求めたところである(詳細はP90参照)。
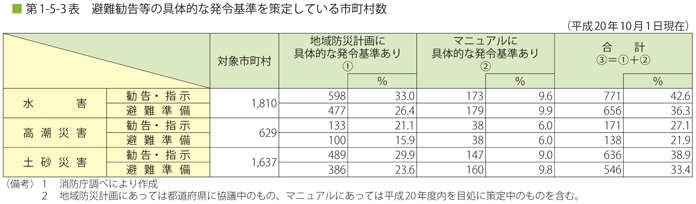
(2)放送事業者との連携体制の整備
消防庁では、市町村に対し、災害時における連絡方法、避難勧告等の連絡内容等について放送事業者とあらかじめ申し合わせるなど、放送事業者と連携した避難勧告等の伝達体制を確立するよう求めている。
(3)情報伝達体制の整備
気象情報の的確な収集を行うため、緊急防災情報ネットワーク、各種の防災気象端末等の活用を図るとともに、他の防災機関等との連携を図り、休日・夜間も含め、防災関係機関相互間及び住民との間の情報収集・伝達体制の整備が必要である。このため、全国瞬時警報システム(J-ALERT)及び防災行政無線(同報系)の整備等を図るとともに、実際の災害時に有効に機能し得るよう、通信施設の整備点検、市町村もしくは市町村消防機関により、防災行政無線を24時間迅速に起動できる運用体制の確保が重要である。 消防庁では、都道府県に対し、避難勧告・指示などの市町村からの災害に関する情報を迅速かつ的確に把握し、情報提供を行うととともに、自衛隊や緊急消防援助隊の出動要請を行う場合等においては、市町村と十分な調整を図ることを求めている(平成21年6月3日付消防災第232号「風水害対策の強化について(通知)」など)。 また、平成21年8月の台風第9号により、災害対策本部を設置する役場庁舎が浸水被害に遭った事例が見られたため、消防庁では、平成21年8月24日都道府県防災主管課長会議において、各都道府県、市町村において、都道府県庁や市町村役場が浸水被害に遭うことも想定し、災害対策本部の設置場所、防災行政無線等の通信機器及び電源の設置場所、広報車両の駐車場所等について、点検を十分行うよう要請した。 その他、平成21年8月通知において、都道府県に対し、大雨、洪水等の警報や土砂災害警戒情報など気象に関する情報については、市町村が避難勧告等を発令する際、より具体的に活用できるよう、平常時から気象台と連携し、できるだけわかりやすい情報提供に努めるとともに、それらの情報に対する市町村担当者の理解の向上を図ることを求めた。また、雨量や土砂災害危険度などの土砂災害警戒情報を補足する情報についても、その内容を市町村に周知徹底すること、市町村が災害対策本部を設置した場合には、必要に応じて職員を市町村に派遣するなど、専門的知見に基づく技術的助言、市町村からの情報収集、応援要請の調整などを行うことを要請した。 また、市町村に対しては、都道府県から通知される気象に関する情報を避難勧告等の発令にあたり重要な判断材料にすることや、災害対策本部を設置した場合には、必要に応じて、都道府県や気象台、学識経験者などにも出席を要請し、専門的知見に基づく技術的助言を求めることを要請した。
