2 避難体制の整備
(1)災害時要援護者の避難誘導体制の整備
政府としては、平成20年4月に中央防災会議で報告された「自然災害における『犠牲者ゼロ』を目指すための総合プラン」において、平成21年度までを目途に、市町村において災害時要援護者の避難支援の取組方針(全体計画)などが策定されるよう促進することとしている。 消防庁では、内閣府等関係府省庁と連携し、全体計画などが策定されていない市町村の割合が高い都道府県において、平成21年7月から11月にかけて、内閣府、消防庁、各都道府県の共催による市町村担当者との意見交換会を開催したり、随時、災害時要援護者対策に関する情報提供を行ったりするなど、市町村における災害時要援護者対策が早急に進められるよう支援を行った。 市町村は、「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」(平成17年3月策定、平成18年3月改訂)等を参考に、自主防災組織等との連携の下、一人ひとりの災害時要援護者に対して複数の避難支援者を定める等、具体的な避難支援計画(避難支援プラン)を早急に策定する必要があるが、平成21年3月31日現在、市町村において、「全体計画」(災害時要援護者の避難支援対策についての基本的な取組方針等を定めたもの)を策定しているのは576団体(32.0%)、策定中の団体を含めると1,125団体(62.5%)であった。一方、民生委員、自治会・町内会等が災害時に安否確認等に活用する「災害時要援護者名簿」の整備を進めているのは1,196団体(66.4%)あり、避難支援者と要援護者を関連づけ、災害時に要援護者一人ひとりの避難支援に活用される「個別計画」の作成を進めているのは726団体(40.3%)である(第1-5-2図)。
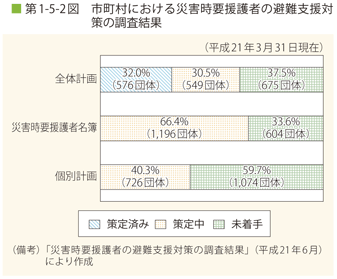
なお、災害時要援護者関連施設については、平成21年7月中国・九州北部豪雨において、山口県防府市内の特別養護老人ホームで土砂災害により多数の死者が発生したことを受けて、平成21年8月通知で、都道府県、政令指定都市及び中核市においては、社会福祉施設等の災害対策を推進するため、施設の立地条件や非常災害に対する具体的計画の策定の再点検等を実施するよう求めた。 また、消防庁では、市町村に対して、平常時より立地条件の把握、施設周辺のパトロール体制の確認をはじめ、施設への適切な情報提供、的確な避難誘導体制等の再点検を行うよう求めている。 さらに、避難が夜間になりそうな場合には日没前に避難が完了できるように努めるなど、警戒避難体制等の防災体制を整備するよう求めている。
(2)避難路・避難所の周知徹底及び安全確保等
消防庁では、市町村に対し、避難路・避難所については、住民が円滑かつ安全に避難できるよう、周知徹底するとともに、豪雨災害等の特性を踏まえた安全性の確保、移送手段の確保及び交通孤立時の適切な対応を求めている。 また、避難者が多数発生するなど、一時的に避難所の確保が困難となる場合には、避難所として指定されていない他の公共施設等を一時避難所として確保するよう求めている。
