5 救急業務体制の整備の課題
(1)救急救命士の養成
救急救命士は、平成3年(1991年)の制度導入以降、着実に養成され、各地の救急現場において活躍しているところであるが、全国すべての救急隊に少なくとも救急救命士が1人配置できるよう、今後も引き続き救急救命士の養成を積極的に進めていく必要がある。
救急救命士の資格は、消防職員の場合、救急業務に関する講習を修了し、5年又は2,000時間以上救急業務に従事したのち、6か月以上の救急救命士養成課程を修了し、国家試験に合格することにより取得することができる。資格取得後、救急救命士が救急業務に従事するには、病院実習ガイドラインに従い160時間の病院実習を受けることとされている。
救急救命士は、現在、財団法人救急振興財団の救急救命士養成所で年間約800人、政令指定都市等における養成所で年間約400人が養成されているところである。一方で、平成18年度からは救急救命士の処置範囲が拡大(薬剤投与)したため、各養成機関での救急救命士の新規養成に加え、医療機関と連携しつつ、薬剤投与のための追加講習を行う等、円滑かつ着実に講習内容の更新が進められている。
平成21年3月には、あらかじめ自己注射が可能なアドレナリン(エピネフリン)製剤を処方されている者に対し、救急救命士が該当アドレナリン(エピネフリン)製剤の投与を行うことが可能となった。これを受け、消防庁では「消防機関における自己注射が可能なアドレナリン(エピネフリン)製剤の取扱いに関する検討会」を開催し、自己注射可能なアドレナリン製剤の投与に関するプロトコール例を提示するなど、対応体制の構築を図っている。
(2)救急用資器材等の整備
救急業務の高度化に伴い、高規格の救急自動車、高度救命処置用資器材等の整備が重要な課題となっている。
近年、国庫補助金が廃止、縮減される中においても、これら高規格の救急自動車、AED等に対する財政措置は不可欠であり、地方交付税措置など、必要な措置が講じられている。今後も引き続き、高規格の救急自動車及び救急救命士の処置範囲の拡大に対応した高度救命処置用資器材の配備を促進する必要がある。
(3)救急業務における感染防止対策
救急隊員は、常に各種病原体からの感染の危険性があり、また、救急隊員が感染した場合には、他の傷病者へ二次感染させるおそれがあることから、救急隊員の感染防止対策を確立することは、救急業務において極めて重要な課題である。
消防庁では、救急業務に関する消防職員の講習に救急用器具・材料の取扱いの科目を設置しているとともに、重症急性呼吸器症候群(SARS)等を含めた各種感染症の取扱いについて、感染防止用マスク、手袋、感染防止衣等を着用し、傷病者の処置を行う共通の標準予防策等の徹底を消防機関等に要請しているところである。特に、新型インフルエンザ対策として、救急隊員等搬送従事者用に感染防止用資器材の備蓄を進めるべく、平成20年度に、新型インフルエンザ対策のための感染防止用資器材の配備を実施している。また、消防機関の搬送後に感染症に罹患していたことが判明する場合もあることから、医療機関等と消防機関との連絡体制、救急自動車等の消毒方法、救急隊員の健康診断等の感染防止体制について一層強化していく必要がある。
(4)救急需要の増加への対応
救急自動車による救急出場件数は年々増加し、平成20年中は509万7,094件に達し、平成16年以降5年連続で500万件を超えている。今後も、高齢化の更なる進展や住民意識の変化に伴い、救急需要は高い水準にあるものと考えられる。このことから、救急自動車の現場到着時間も遅延することが予想され、地域によっては、傷病者が発生した場合に、救急自動車による迅速な対応が困難となるおそれがある。
このような状況を踏まえ、消防庁においては、平成20年度に、「救急業務高度化推進検討会」で119番受信時における緊急度・重症度の選別(トリアージ)について検討を行い、同検討会の報告書において、コールトリアージプロトコールやコールトリアージ導入の制度設計に向けた提言を行ったところである。平成21年度には、前年度の検討を活かし、トリアージに伴うPA連携などの救急隊の運用や、救急要請すべきかどうか迷った場合の相談に対応する窓口の設置など、緊急度の低い相談から緊急度の高い通報に対応する体制の整備について検討を行っている。
さらに、消防庁においては、平成21年度に市民が救急要請すべきかどうか迷う場合の相談に対応する窓口を設置する「救急安心センターモデル事業」を3つのモデル団体(愛知県、奈良県、大阪市)で実施しており、今後、この成果を活かして、全国的に展開し、真に必要な救急要請に適切に応えられる体制の確保に努めることとしている。
(5)災害時における消防と医療の連携
平成17年のJR西日本福知山線列車事故のような多数傷病者発生時や地震等の大規模災害発生時の救急救助活動については、消防機関と医療機関の連携方策や、災害現場における救急救助活動に有用である医療行為など様々な検討を行うことが必要である。
このため、消防庁においては、学識経験者、医療関係者、消防関係者等により構成される「災害時における消防と医療の連携に関する検討会」において、幅広い検討を重ね、平成20年度の検討会報告書において災害対策本部等における消防と医療の連携体制について提言を行った。
今後は、緊急消防援助隊ブロック訓練など消防機関と医療機関が参画する合同訓練等を通じ、より一層の連携体制を構築するとともに、大規模災害時における救命率の向上を図るために、心肺機能停止前における静脈路確保など、救急救命処置の拡大等について検討することとしている。
(6)救急搬送におけるヘリコプターの活用推進
消防防災ヘリコプターを活用した救急業務については、平成10年(1998年)3月の消防法施行令の一部改正により、消防法上の救急業務として明確に位置付けられた。さらに、消防庁は、平成12年(2000年)2月にヘリコプターによる救急出動基準ガイドラインを示し、各都道府県はこれを基に出動基準を作成し、それぞれの地域の実情を踏まえた救急業務を行っている。 平成20年中における全国の消防防災ヘリコプターの救急活動実施状況は、救急出動件数3,276件(前年比3.4%増)、搬送人員2,811人(同0.7%減)であり、消防防災ヘリコプターによる救急出動件数は年々増加する傾向にある(第2-4-1表)。特に、離島、山間部等からの救急患者の搬送や交通事故等による重症患者の救命救急センター等への救急搬送、さらには、大規模災害時における広域的な救急搬送等に大きな効果を発揮している。地域社会の安心・安全を確保する上で大きな期待が寄せられていることから、今後とも医療機関等との連携を強化しながら、消防防災ヘリコプターの機動力を活かした救急活動を推進することが求められている。
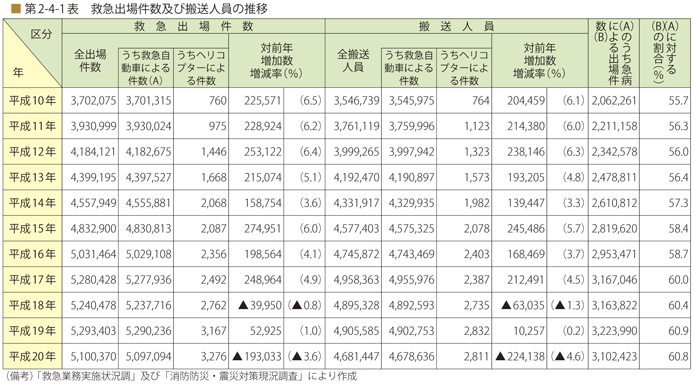
また、平成21年3月にとりまとめられた「消防防災ヘリコプターの効果的な活用に関する検討会」の報告書においては、消防防災ヘリコプターの救急活動への積極的な活用のための方策がとりまとめられ、医師搭乗体制の整備やドクターヘリとの連携の必要性が示されている。
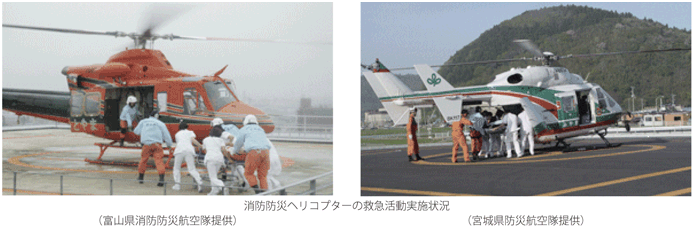
なお、厚生労働省では、平成13年度からドクターヘリ導入促進事業を実施しているが、平成19年には、更にドクターヘリを用いた救急医療の全国的確保を図るため、議員立法により、「救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法」が成立しており、平成21年3月末現在16道府県で18機のドクターヘリ運用が行われている。
消防機関では、119番通報のうち傷病者の重症度・緊急度が高いものについて、傷病者の情報を伝達しドクターヘリの出動要請を行うとともに、救急自動車からドクターヘリへ傷病者を円滑に引き渡すなど、緊密な連携を図っている。
