第3章 国民保護への取組
1 国民保護法の目的等
(1)国民保護法制定の経緯
国民の保護に関する法制は、平成15年6月に公布・施行された「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)」及び衆参両院での附帯決議において速やかに整備することとされた。これを受け、平成16年6月には国民保護法(P.121参照)が成立し、関係政令とともに9月17日に施行された。
これにより、武力攻撃事態等(武力攻撃事態*1及び武力攻撃予測事態*2をいう。以下同じ。)や大規模テロ等の緊急対処事態*3に対処するための法的基盤が整えられた。
*1 武力攻撃事態:武力攻撃とは、我が国に対する外部からの武力攻撃をいい、武力攻撃事態とは、武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。
*2 武力攻撃予測事態:武力攻撃事態には至っていないが、事態が切迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。
*3 緊急対処事態:武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態(後日対処基本方針において武力攻撃事態であることの認定が行われることとなる事態を含む。)で、国家として緊急に対処することが必要なものをいう。
国民保護法の目的は、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするため、国、地方公共団体、指定公共機関等の責務をはじめ、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置等について定めることにより、国全体として万全の態勢を整備すること(第一条)にある。
なお、緊急対処事態に関しては、武力攻撃事態等への対処と同様の措置をとることとされている。
(2)国民保護法に係る地方公共団体の役割
国民保護法に基づき、地方公共団体は、警報の伝達や避難の指示、救援の実施等の国民の保護に関する措置(以下「国民保護措置」という。)の多くを実施する責務を有するなど、大きな役割を担うこととされている。また、平時においても、いざというときに迅速に国民保護措置が実施できるよう、国民の保護に関する計画(以下「国民保護計画」という。)の作成や必要な組織の整備、訓練の実施などが求められている。
特に消防機関は、市町村長の指揮の下に避難住民を誘導し、国民の生命、身体及び財産を武力攻撃による火災から保護し、武力攻撃災害を防除及び軽減することが規定されるなど、重要な責務を負うこととされている(第3-1図)。
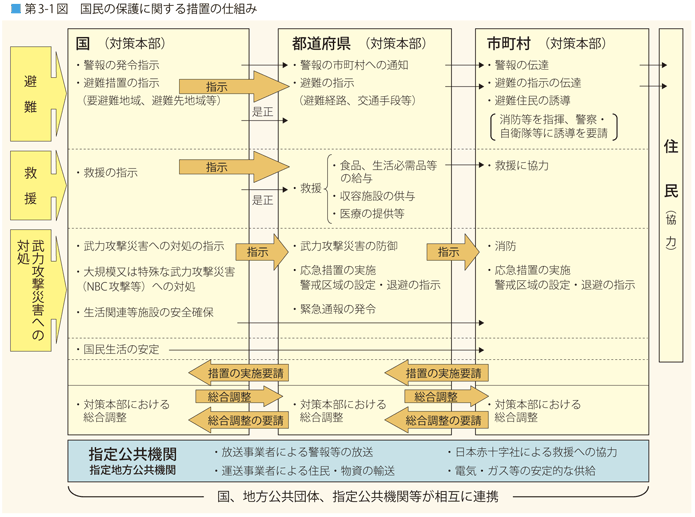
(3)国民保護に係る消防庁の役割
消防組織法及び国民保護法に基づき、消防庁は、武力攻撃事態等において、国、地方公共団体が相互に連携する上で大きな役割を担うこととされている。
そのうち、主なものを挙げると以下のとおりである。
〔1〕 内閣総理大臣が行った国民保護対策本部を設置すべき都道府県及び市町村の指定等を、都道府県知事及び市町村長に通知
〔2〕 対策本部長(内閣総理大臣)による警報の発令の通知及び避難措置の指示の内容の都道府県知事への通知
〔3〕 県境を越える避難に際し、必要と認める場合には、関係都道府県知事に勧告
〔4〕 都道府県知事から報告を受けた安否情報について、照会に応じ情報提供
〔5〕 武力攻撃災害を防除するための消防に関する措置及び消防の応援等に関し、都道府県知事又は市町村長へ指示
〔6〕 被災情報を自ら収集し、又は都道府県知事等から報告を受け、対策本部長に報告
〔7〕 都道府県知事からの求めに応じ、国や他の地方公共団体の職員の派遣について、あっせんを実施
〔8〕 国民保護法に基づく地方公共団体の事務に関し、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整
このほか、消防庁では、国民保護法において国・政府・指定行政機関(各省庁)の役割として規定されている事項(国民に対する情報の提供、救援の支援、国民保護の重要性の啓発、訓練の実施等)について、「国民の保護に関する基本指針」、「消防庁国民保護計画」等に基づき対策を実施することとされている。
