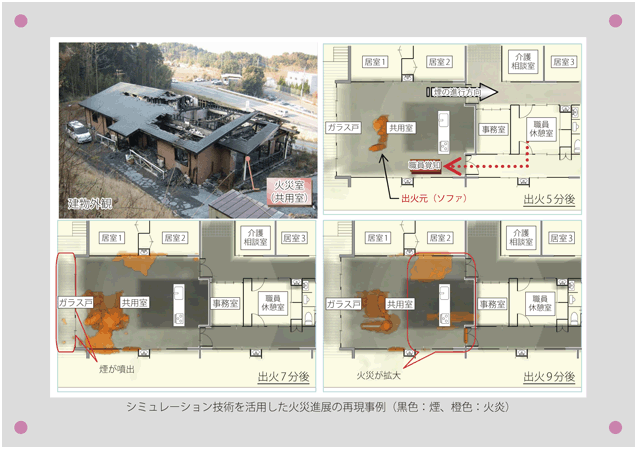3 研究成果をより広く役立てるために
消防研究センターでは、研究によって得られた成果を、全国の消防職員をはじめとする消防関係者はもとより、一般の方々にも広く役立てることを目的に、以下の活動を行っている。
(1)一般公開
毎年4月の「科学技術週間」にあわせて、消防研究センターの一般公開を実施している。平成21年度は4月17日に実施し、674人の参加を得た。
一般公開では、実験施設や実験場などの公開、展示や実演による研究の紹介を行っている。平成21年度は全24項目にわたる内容を公開し、中でも、泡消火のメカニズムについて紹介するために行った小規模石油タンク模型を用いた消火実験などが、参加者の注目を集めた。
(2)全国消防技術者会議
全国の消防技術者の研究発表、意見交換等の場として昭和28年(1953年)から「全国消防技術者会議」を毎年開催している。
この会議では、各地の消防本部で実施された研究成果の発表、消防機器の開発・改良に関する紹介、火災原因調査の事例紹介などを行っている。平成20年度は、10月23日及び24日の2日間、東京都港区虎ノ門のニッショーホールにおいて開催された。平成21年度は、11月25日及び26日の2日間にわたり開催することとしている。
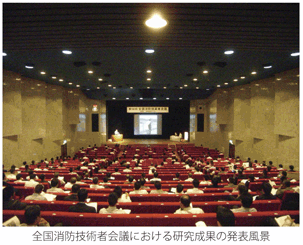
(3)消防防災研究講演会
消防研究センターの研究成果の発表及び消防関係者や消防防災分野の技術者や研究者との意見交換を行うため、平成9年(1997年)度から「消防防災研究講演会」を開催している。
この講演会では毎年特定のテーマを設けており、平成20年度は「地震等災害情報の収集・伝達・活用」をテーマとして研究発表及び討論を実施した。平成21年度は、平成22年1月29日に開催の予定である。
(4)火災調査技術会議
消防本部が消火活動の後に実施する火災調査の技術の向上を目的として「火災調査技術会議」を開催している。
この会議は、全国の主な都市で年間5回程度開催しており、各地の消防本部における特異な火災事例の紹介や、最新の調査技術、機器に関する情報交換を行っている。平成20年度は、東京、名古屋、新潟、大阪、福岡の5都市で開催した。
平成21年度は、「調査技術会議」と名称を変更し、危険物流出等の事故調査の事例紹介を含めて情報交換を行っている。
(5)消防防災機器の開発等及び消防防災科学論文の表彰
消防防災科学技術の高度化と消防防災活動の活性化に寄与することを目的として、消防職員や一般の方による消防防災機器の開発や改良及び消防防災に関する研究成果のうち特に優れたものを消防庁長官が表彰する制度を平成9年度から実施している。応募の資格に制限はなく誰でも応募することができるため、多くの人に開かれた発表の機会となっている。
平成20年度は63編の応募があり、14編の作品が表彰された。

火災調査高度化のための火災進展シミュレーション技術の活用について
火災調査では、火災の発生原因や延焼拡大状況の究明、避難行動や消防活動の評価、予防に向けた対策など、状況に応じて様々な課題があります。それらの課題に対して、限られた情報だけでは全体的な火災進展状況を判断することが難しい場合もあります。そこで消防研究センターでは、計算機を用いて火災進展状況を再現するシミュレーション技術を、火災調査を高度に支援する技術として研究開発しています。
シミュレーション手法として、数値流体力学(CFD:Computational Fluid Dynamics)に基づいた計算方法を採用しています。数値流体力学は、火災現象の一つである流体現象を律している質量、運動量、エネルギー量などの基礎方程式の解を、計算機を用いて求めることで流体現象を再現する学問分野です。そして、火災現場の状況に応じた適切な火源条件をはじめとする計算条件を設定すれば、火災の拡大や煙の伝播、物体への放射受熱量などの経時変化を計算し予測することが出来ます。
そのシミュレーション技術を適用した火災調査事例として、長崎県大村市グループホーム火災、兵庫県宝塚市カラオケボックス店火災、大阪市浪速区個室ビデオ店火災などが挙げられます。その一例を下の図に示します。図から、出火からの火災の拡大や煙の伝播の様子が視覚的にわかり、火災発生時の実際の情報と合わせて、当時の在館者の避難行動の把握や、その時に在館者が曝露されている煙濃度や温度などの周囲環境の判断が出来ます。調査を実施する上でも、火災では時間経過とともにどのようなことが起こっていたかなどの共通認識を持つ上では非常に有用な技術です。
また、消防研究センターではシミュレーションの火源条件として活用できる火災実験データベース(http://firedb.fri.go.jp/)を整備し、種々の可燃物の燃焼に係るデータの充実に努めています。