3 住警器の普及に向けた取組
(1) 住警器の普及状況
住警器の普及状況については、各地域においてアンケート等の方法により調査が行われているところであるが、消防庁においてその結果を収集し、独自の方法で平成21年3月時点における全国の普及率を推計した結果は、45.9%となっている。前回調査を行った平成20年6月時点から推計普及率は10ポイント程度伸びており、各地域における取組が進んでいるが、既に義務化されている地域においても普及率が55.2%に留まる等、一層の取組が必要である。
なお、効果的な普及策の展開等のため、各地域においては、住警器の普及状況を定期的に把握し、公表していくことが求められる。
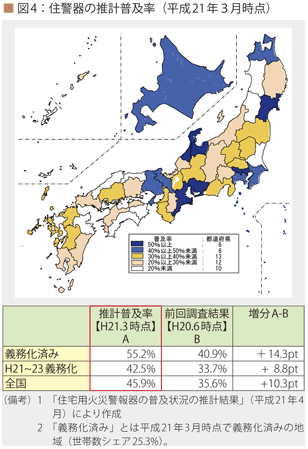
(2) 国民運動的な取組の展開
住警器の早期普及のためには、消防機関のみならず、あらゆる主体が総力を結集して、国民運動的に取り組むことが必要である。消防庁では、平成20年12月17日に「住宅用火災警報器設置推進会議」を開催し、同会議において、「住宅用火災警報器設置推進基本方針」を決定するとともに、基本方針に基づいた早期普及に係る取組を推進している。
ア 地域に密着した取組のための体制整備
住警器の設置を推進するためには、消防署又は消防本部と消防団、婦人(女性)防火クラブなどの関係者が、当該地域の実情に応じて、地域社会に密着した取組を一体となって展開できるよう、相互の密接な連携を図ることが不可欠である。このため、「住宅用火災警報器設置推進基本方針」では、「消防署又は消防本部を単位とした地域推進組織を地域ごとに整備する」としており、各地域において地域推進組織の整備が進められている。
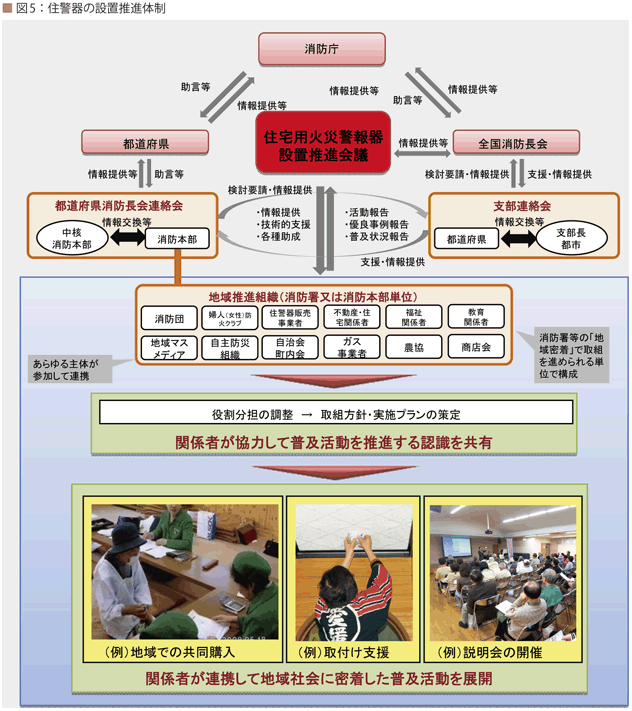
イ シンポジウムの開催
消防庁では、消防団や婦人(女性)防火クラブ、自主防災組織等の地域コミュニティのリーダー等を対象として、住警器の普及を呼びかけるシンポジウムを全国各地で開催している。シンポジウムでは、他地域での地域力を活かした先進的な取組事例の紹介も行っており、住警器の普及を推進するための知恵や工夫を参加者が持ち帰り、自らの地域での取組に活用することにより住警器の普及が加速することが期待される。
