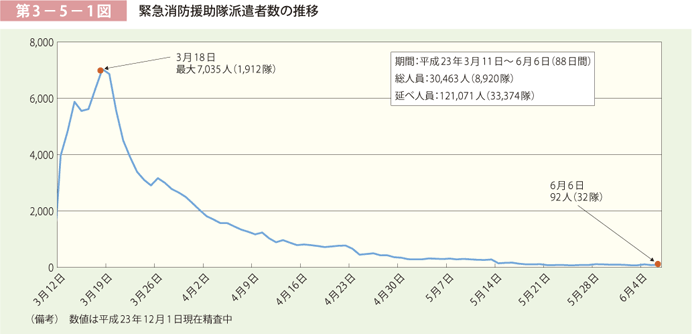第5節 緊急消防援助隊の活動
東日本大震災においては、震度6弱以上を観測した都道府県が8団体と多数にのぼり、うち数県では通信網に支障をきたしているような状況で、さらに広い範囲で津波警報(大津波)が発表されていた。
そのため、消防庁としては、緊急消防援助隊派遣の根拠として、消防組織法第44条第5項の規定に基づく消防庁長官の出動指示権を行使すべきと判断し、3月11日15時40分、20都道府県に対して陸上部隊の出動指示を行った。その後も情報収集を進め、甚大な被災状況が判明するに従い部隊の追加投入を決定していった(第3-5-1表)。
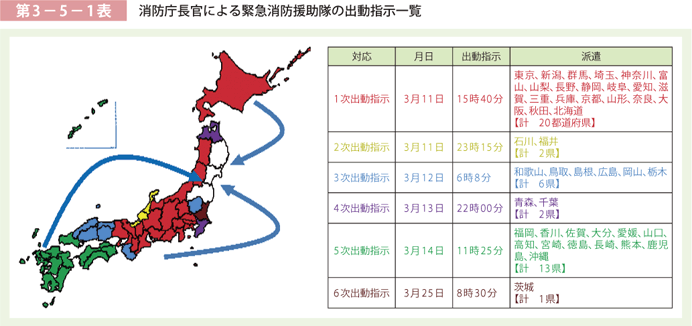
並行して消防防災ヘリコプターについては、直ちに全国規模の派遣を念頭に調整を開始し、日没までに到着できない場合でも、関東に設けた進出拠点までの出動を指示するなど、被災地への迅速な投入に向けて懸命の努力を行った。
本震発災後しばらくは余震等の活動が活発であり、12日未明には新潟県及び長野県、15日深夜には静岡県富士宮市において、最大震度6弱以上を観測する大規模な地震が発生したが、これらの地域を所管する各消防本部の一部の部隊は、緊急消防援助隊として本震に対する応援活動に対応するため、東北地方を中心とした被災地へ向け既に出動しており、これらの地震への対応が懸念された。これらの事案に対して、本震に対する応援出動のため付近を東進していた陸上部隊を直ちにこれらの地域に転進させ被害状況の確認等を実施させるなど、機動的な対応をとることができた。
主な被災3県に集結した緊急消防援助隊は、発災直後の降雪といった天候不良、山積するがれきが行く手を阻む厳しい環境下において、大きな余震や津波への警戒を続けながら、地元消防や関係機関との連携のもと消防活動に従事した。
「水利が破壊された中、市街地火災ヘと発展した気仙沼市における海水利用型消防水利システムを活用した消火活動」や「福島第一原子力発電所における事故対応(詳細は、本章第10節を参照)」、「ヘドロ状の浸水状況が続く中で、発災9日後の石巻市で奇跡的に倒壊家屋から2名を救出した人命救助活動」、さらには「地域の医療機関が被災したことなどによる遠距離救急搬送」など日本の消防活動史に残る懸命の応援活動が実施された。
また、津波により消防力が低下した消防本部において、緊急消防援助隊が常備消防力の補完的活動にも引き続き従事した。
消防防災ヘリコプターについては全国から58機*1が被災地に応援出動し、機動力を生かした活動に従事したところであるが、大津波の被害が特徴的な今次災害において、発災後数日中の孤立建物からの救助活動でその能力は如何なく発揮されたほか、陸上自衛隊のヘリコプターによる救助活動と連携して、例のない深夜の空中消火の実施により、仙台市の孤立した小学校を火災延焼の危機から救った。
*1 平成23年3月11日時点において、消防防災ヘリコプターは全国に71機配備されており、そのうち1機は、津波により被災し、使用不能となった。
また、平成7年の緊急消防援助隊創設以来初めて、消防艇から構成される水上部隊が千葉県市原市で発生した大規模コンビナート火災に出動、陸上部隊や他機関と連携して活動を行い、被害の拡大防止に重要な役割を果たした(詳細は、本章第9節参照)。
こうして緊急消防援助隊の1日の最大派遣数は1,912隊7,035人にのぼり(3月18日)、被災地の消防活動のニーズと調整しながら、最終的には6月6日までの88日間、44都道府県の712消防本部から3万人を超える(数値は平成23年12月1日現在精査中)消防職員が、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、新潟県、長野県及び静岡県の8県において緊急消防援助隊による応援活動を実施、6月30日19時までに消防庁が把握している救助者数は、地元消防本部等と協力したものを含め5,064人に上った。
地震動や津波により、主な被災3県における23消防本部(主な被災3県のうち64%)において、消防救急無線の機器や基地局が被害を受けたため、緊急消防援助隊として出動している部隊と消防応援活動調整本部との通信、同県内で活動している部隊同士の通信、緊急消防援助隊として出動している部隊と受援消防本部との通信に問題が生じ、消防救急無線の代替手段として衛星携帯電話等を使用することで通信を行った。また、公衆通信網が被害を受けたため、緊急消防援助隊として出動している部隊と派遣元の消防本部との通信にも問題が生じた。
このように緊急消防援助隊にとっては、質・量・期間の全ての面において過去に類のない出動事例となり、様々な課題や教訓を得たところであるが、東海地震など巨大地震の切迫性が指摘される中、さらなる活動能力の向上に生かしていくことが求められるところであり、消防庁では、緊急消防援助隊の施設・設備や運用等のあり方について検討を行っている(詳細は、第4章第3節参照)。